バブルの時の日経平均は3万8915円でしたが、今は3万9000円強とバブル期を超えました。
これには新NISAだけでなく、円安や中国からの資金シフトの影響もあるといわれています。
特に新NISAの影響で個人資産が動き始め、FPや投資会社に女性からの相談が増えているそうです。
NISAなら資産1億円も決して夢ではないといった話を聞き、20代でも積立投資を始めたい人が増えています。
毎月の積立額と期間や利回りを考慮して設定をすれば、1億円は可能な額といえます。
投資が初心者の人は、まずは投資の基本といわれる投資信託を学ぶことから始めてみてはいかがでしょう。
なぜ今、投資が必要なのか

投資をすると単純にお金が殖えるというものもありますが、重要なのは物価上昇に対処するということです。
インフレで現金の価値は下がる
インフレというのは物価が上昇をしていくことですが、インフレがあっても何もしなければお金の価値は目減りしていきます。
たとえば、現在100万円を持っているとして、タンスに貯金していれば20年後も100万円なので、価値が変わらないように見えます。
しかし、この間も物価上昇が2%、3%続いていたとしたら、物価の上昇で今まで変えたものが買えなくなることが考えられます。
何もしないことが最大のリスク
現在100万円で買える物が、物価上昇で20年後には150万円出さないと手に入らなくなるかもしれません。
仮に2%のインフレが今後20年起きたとすると、タンスに貯金していた100万円は実質的に20年で3分の2の67万円の価値になってしまいます。
- 2%のインフレ→見た目は100万円→実質的な価値67万円
これが3%だったら20年後には半分近くになってしまうので、インフレに対して何かしらの対処が必要になります。
こういったことがインフレ時代に現金で保有していることのリスクです。
投資信託の仕組みとは

投資信託はお金をまとめてプロが運用する仕組み
投資信託は、投資家から集めた資金を運用の専門家が証券や債券に分散投資し、その利益を投資家に分配する仕組みです。
信託は財産を受託者に渡して運用してもらうことですが、法律上は受託者の財産として運用します。
投資信託には様々な種類があり、信託契約型の投資信託は委託者指図型投資信託、委託者非指図型投資信託に分かれ、委託者指図型投資信託は証券投資信託とそれ以外の投資信託があります。
証券会社に上場されているETF(株価指数連動型上場投資信託)から、外国の投資信託や不動産投資信託など様々あります。
投資対象は株式・債券・不動産など
投資信託には一つの商品で分散投資の効果が期待できます。
投資対象は、株式、債券、不動産、コモディティなどがあります。
日本国内だけでなく、先進国、新興国、世界中を投資対象としたものまであります。
少額・分散・ほったらかしが可能
日本の株だと単元株式(100株が多い)が定められていることが多く、それなりの資金がないと始められませんが、投資信託であれば少額から投資できます。
すでに分散投資されてるので少額でも分散効果が期待できます。
毎月決まった額を設定しておけば、あとはほったらかしで定額の積み立て投資も可能です。
一方で指値注文ができなかったり、保有してるだけで信託報酬といった維持コストがかかるといったデメリットがあります。
投資の知識がない人でも平均リターンを得られるのは、投資信託の最大のメリットです。
投資信託にかかる費用と注意点

投資信託は保有してるだけで維持費用がかかります。投資信託に係る費用には、税金以外では手数料、信託報酬、信託財産留保額、監査費用、売買委託手数料などがあります。
購入時にかかる費用(手数料)
手数料は、商品を購入した時に負担する費用ですが、ネット証券だと手数料がかからないノーロードのファンドも多く出ています。
保有中にかかる費用(信託報酬)
信託報酬は、委託者報酬、受託者報酬、販売会社報酬からなり、日々投資信託の残高から差し引かれます。
保有してる限りかかる信託報酬には特に注意が必要です。
保有している投資信託の〇%といった形でかかるので、パフォーマンスに影響します。
例えば、毎月5万円を25年間利回り5%で積み立てたとしたら、信託報酬が0.5%だったら25年後に約2700万円になりますが、信託報酬が2%だったら約2200万円にしかなりません。同じ金額を同じ期間積立てたのに、信託報酬の違いで500万円の差は大きいです。
解約時にかかる費用(信託財産留保額)
信託財産留保額は、解約時に差し引かれる費用です。
監査費用や売買委託手数料は投資家が間接的に負担する費用です。
パッシブ運用とアクティブ運用の違い

投資信託は運用方法でパッシブ運用とアクティブ運用に分かれます。
パッシブ(インデックス)運用とは
パッシブ運用は、あらかじめ定めた指標に連動するように運用を行い、代表的なのはインデックス運用です。
アクティブ運用とは
アクティブ運用は、目安となる指標(ベンチマーク)を上回る収益を目指す運用です。
初心者はどちらを選ぶべきか
アクティブ運用と比べて一般的にパッシブ運用のコストは低いといわれてます。
| パッシブ運用 | アクティブ運用 | |
| 運用目標 | 指標に追従・連動 | 指標を上回る |
| コスト | 低い | 高い |
市場平均以上の運用成績を上げるのは難しく、アクティブ運用でインデックス運用を上回るファンドは2割未満といわれています。
そうであれば、初心者は最初から市場の平均リターンが約束されているインデックスファンドを選ぶのが合理的といえます。
投資信託を選ぶ前に必ず見るポイント

目論見書は投資家が投資をする判断基準となる情報が記載された資料です。目論見書は交付目論見書、請求目論見書の2つがあります。
目論見書でチェックすべき3点
投資信託を雑誌やネットでおすすめされてたから買ったでもいいですが、最低でも投資対象、運用方法、費用については確認したほうがいいでしょう。
- 投資対象
- 運用方法
- コスト(購入時・保有時・売却時)
分配金あり/なしの考え方
長期積立てを目標に複利効果に期待するのであれば、分配金なしのファンドがおすすめです。
反対に分配金を受け取りながら老後生活していきたいような人は分配金ありを選ぶといいかもしれません。
為替ヘッジあり・なし
海外の指数に連動したファンドは為替のリスクがあるので、為替ヘッジあり・なしの投資信託があります。
為替ヘッジはコストがかかります。長期積立て投資が目的なら、ドルコスト平均法を活用して積立てれば、為替ヘッジなしでも良いと思います。
NISAでなぜ投資信託がおすすめとされるのか?投資信託なら初心者でも資産形成が始められる
まとめ
- 投資しないとインフレでお金が目減りしていく。
- 投資信託なら投資の知識がなくても始めやすい。
- 運用手法にはパッシブ運用とアクティブ運用がある。
- 投資信託の投資対象は様々ある。
- 投資信託は保有してると維持費がかかる。
- 投資信託の費用には、手数料、信託報酬、信託財産留保額、監査費用、売買委託手数料などがある。
- 投資信託を選ぶ前に目論見書で基本情報を確認する。
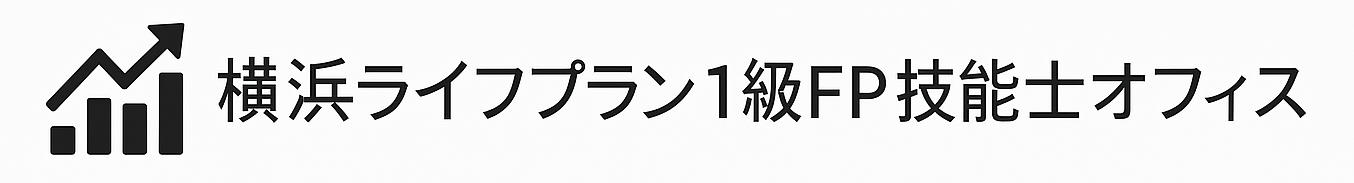




コメント Comments
コメント一覧
コメントはありません。
トラックバックURL
https://yokohama-lifeplan.com/money/what-is-an-investment-trust/trackback/