目次[閉じる]
遺言書がない相続で起きやすい問題

法定相続分どおりでも「もめる相続」は多い
遺言書がない場合は、亡くなった人(被相続人)の財産は法律に定められた相続人が相続します。また、相続分も法律によって決められています。
遺言書に法律で定められた相続分と異なる内容が書いてあれば、遺言書の内容が優先されます。
家族の状況をよく知ってるのが被相続人なので、遺言書も状況に合った内容にするのがもめない相続のためのポイントかもしれません。
遺言書があったほうがいい理由

遺言やエンディングノートは、家族同士が余計な争いを起こさないために有効です。
以下のような場合には、遺言書があることで相続トラブルや手続きの煩雑さを防ぐことができるとされています。
理由① 遺された家族同士の紛争防止になる
遺言を残すのは財産の多い富裕層と思っている人がいますが、財産が多くなくてもトラブルに発展するケースは多いです。
法定相続人が一人であればまだしも、複数の相続人がいると遺産分割でお互いが納得しないことが多く、それがもとで裁判に発展することもあります。
訴訟にならなかったとしても、しこりを残して仲良しだった家族の付き合いがなくなることもあります。
遺言によって誰が何を相続するか明確にしておけば、もめ事の防止につながります。
理由② 相続手続きがスムーズになる
遺産分割対策では、生前贈与、分割しやすい資産への組み換え、遺言書が有効とされています。生前に財産を贈与するのが生前贈与です。
日本では財産に占める割合が多いのが不動産です。不動産があると公平な分割ができにくく、トラブルが起きやすいとされています。
したがって不動産から現金・有価証券などの価格が分かりやすい資産に組み替えることが遺産分割対策になります。
遺言によって遺産分割協議が不要になれば、不動産の名義変更もスムーズになります。
-
不動産は分割しにくい
-
名義変更に遺産分割協議書が必要
-
相続人全員の参加が必要
理由③ 本人の意思を反映できる
例(順番の入れ替え)
-
内縁の配偶者
-
介護してくれた子
-
事業承継
財産は遺言で誰に残すか決めることができます。
例えば、内縁関係の人、特定の子供に残すこともできますし、スムーズな事業承継にも遺言は有効とされています。
生前によく世話をしてくれた家族に多く残すこともできます。
遺留分には注意が必要

遺留分とは?最低限認められる分
ただ、法定相続人には最低限受けることができる遺留分というものがあります。
遺留分は配偶者、直系卑属および直系尊属に認められています。
兄弟姉妹には遺留分がない
兄弟姉妹には認められてないので、配偶者の他に兄弟姉妹だけしかいなければ、兄弟姉妹を除くことができます。
夫の葬式中に、今まで会ったこともない兄弟を名乗る人が夫の遺産を請求してくるといった内容の番組を時々見ますが、兄弟姉妹には遺留分が認められてないので、遺言書があれば阻止できます。
遺留分の割合は、相続人が直系尊属だけなら基礎となる財産の1/3、それ以外は財産の1/2とされています。
法定相続分と遺留分の例
| 法定相続人 | 相続人 | 法定相続分 | 各遺留分 |
| 配偶者のみ | 配偶者 | 1/1 | 1/2 |
| 配偶者と子供2人 | 配偶者、子供 | 2/4、1/4、1/4 | 2/8、1/8、1/8 |
| 配偶者と父母 | 配偶者、父、母 | 4/6、1/6、1/6 | 4/12、1/12、1/12 |
| 配偶者と姉妹2人 | 配偶者、姉、妹 | 6/8、1/8、1/8 | 1/2、0、0 |
遺言書がないとどうなる?

遺言書がなければ、相続人全員の合意がなければ分割できないので、不仲な相続人がいると手続きが長引いたりもめる原因になります。
-
家族関係が悪い
-
連絡が取れない相続人がいる
相続をめぐってトラブルを起こさないためには遺言書が有効とされています。
遺言書が特に有効なケース
- 家族の仲が悪い
- 内縁の妻や息子の妻などの相続人以外に財産を与えたい
- ある相続人に法定相続分以上に財産を与えたい
- 特定の財産を与えたい(事業を継がせる後継者がいる)
- 先妻の子供、後妻の子供がいる
- 相続人がいない
- 子供がいない(直系尊属や兄弟姉妹が相続人となる場合)
遺言書の種類と特徴

遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つがあります。
自筆証書遺言であれば気軽に作れますが、遺言書の書き方にはルールがあります。本などを参考にルールに則って作成することが大事です。
自筆証書遺言書保管制度を利用してチェックしてもらうこともできます(後述)。
自筆に不安がある場合は公証人が作成してくれる公正証書遺言がいいかもしれません。ただ、数万円かかります(遺産の額による)。
エンディングノートは遺言書の補完として使う
遺言書ではありませんが、最近はエンディングノートを書くことも流行ってます。
FPの勉強会でも取り上げるほどです。先日も行政書士を招いて行いました。
エンディングノートは法的な効力はありませんが、家族へのメッセージや葬式の方法などを残しておけます。
エンディングノートは遺言書の補完的に使われます。
- 家族仲良くなどメッセージを残せる
- 遺言書の有無や保管場所
- 介護や医療処置について(延命処置はどうするか)
- 預貯金や有価証券の口座、資産や負債の状況など
- どのような葬式を希望するか
- クレジットカードや携帯会社の利用サービス
- など
自筆証書遺言書保管制度
数年前から始まった制度に自筆証書遺言書保管制度というものがあります。
制度の特徴
この制度は自筆証書を法務局が預かってくれる制度です。 遺言は後にしたものが有効なので、預けた遺言書であっても撤回をすることができます。
◎自筆証書遺言書保険制度の特徴
- 法務局でチェックしてくれる
- 遺言書を法務局で預かるので紛失や改ざんの心配がなくなる
- 家庭裁判所での検認が不要になる
- 死亡したら相続人に通知がいく
- 費用が3,900円かかる
申請に必要な書類
- 遺言書
- 申請書
- 本籍の記載がある住民票等
- 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
- 手数料分の収入印紙
まとめ|相続税がかからなくても遺言書は重要
・相続税がかからない場合も遺言書があったほうがよい
・遺留分について知っておく→兄弟姉妹に遺留分はない
・遺言書にはいくつか種類がある(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言)
・エンディングノートは遺言書にかけない希望を書ける
相続対策とは、節税だけでなく家族関係を守るためでもあります。
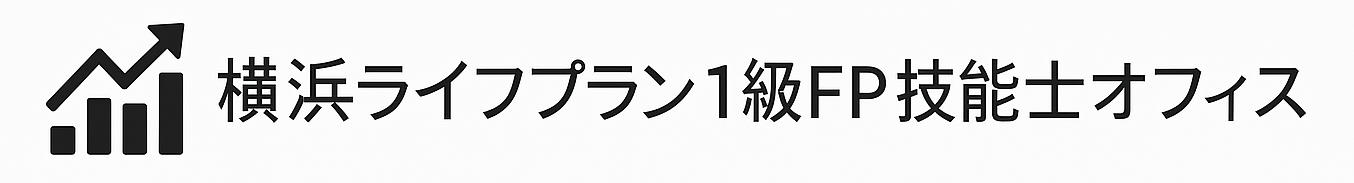



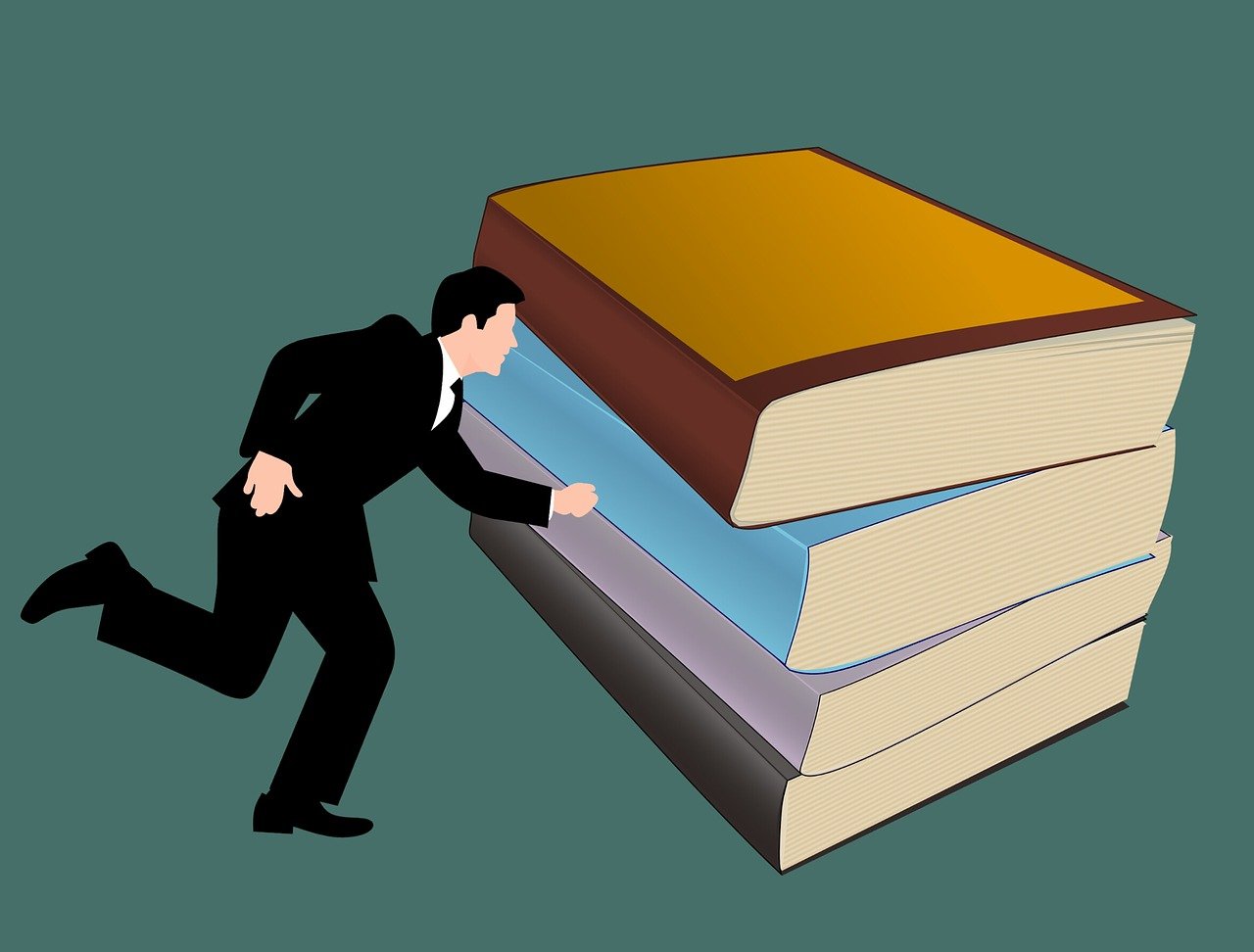
コメント Comments
コメント一覧
コメントはありません。
トラックバックURL
https://yokohama-lifeplan.com/money/reasons-for-writing-a-will-and-its-benefits/trackback/