老後におけるライフプランを立てる際に重要な一つが、将来受け取れるキャッシュフローを知ることです。
将来受け取れるキャッシュフローの一つに退職金の受け取りがあります。
退職金の税金は複雑と思われがちですが、ポイントを押さえれば節税も可能です。特に退職所得控除と受け取り方法は重要です。
退職金とは?

退職金は、長年の勤務に対する報酬として支払われる一時金です。
退職金は他の所得と異なり、受け取り方法が一時金と年金の2種類あります。また、他の収入と異なる税優遇もあります。
退職金は、大企業が多く、中小企業が少ない傾向にあるのも特徴です。
-
一時金で受け取る方法と、年金形式で受け取る方法がある
-
税金の計算方法が特殊で、控除が大きい
退職金の税金の計算方法
退職金の税金は、他の所得と異なる計算式で計算されます。
そのため、所得控除が大きく、税率も低くなるように設定されています。
退職所得の税金計算
退職金の税金と受取額は、次のように計算されます。 退職所得=(退職金ー退職所得控除額)×1/2 受取額=退職金ー(退職所得×税率)
1.退職所得控除額の計算
退職所得控除額は、勤続年数に応じて変わります。
80万円に満たない場合は80万円です。
勤続年数に1年未満の端数がある場合は1年に切り上げます。
| 勤続年数 | 控除額 |
| 2年未満 | 80万円 |
| 20年以下 | 勤続年数×40万円 |
| 20年超 | 800万円+70万円×(勤続年数-20年) |
・障害が直接の原因で退職した場合は100万円が加算されます。
・退職金が退職所得控除額以下の場合は、所得税および住民税は課税されません。
勤続年数が15年の人
勤続年数が15年の人の退職所得控除額は次のようになります。
15年 ≦ 20年 40万円×15年→600万円
勤続年数が30年の人
勤続年数が30年の人の退職所得控除額は次のようになります。
30年 > 20年 800万円+70万円×(30年ー20年)→1,500万円
2.税額の計算
退職金ー退職所得控除額×1/2=退職所得 退職所得×税率=所得税・住民税
所得税
| 課税所得金額 | 所得税率 | 控除額 |
| 1,000円~1,949,000円 | 5% | 0円 |
| 1,950,000円~3,299,000 | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000円~6,949,000円 | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000円~8,999,000円 | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000円~17,999,000円 | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000円~39,999,000円 | 40% | 2,796,000円 |
| 40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |
(国税庁 所得税の税率より)
さらに令和19年までは所得税額に2.1%の復興特別所得税が上乗せされます。
住民税は10%です。
- 課税所得金額×0.1=住民税
勤続38年退職金2,500万円の場合
- 退職所得控除額 → 800万円+70万円×(38-20)=2,060万円
- 退職所得 → (2,500万円ー2,060万円)×1/2=220万円
- 所得税 → 220万円×10%ー97,500円=122,500円
- 復興特別所得税 → 122,500円×2.1%=2,572円
- 住民税 → 220万円×10%=22万円
退職金の受け取り方法とそれぞれの違い

退職金の受け取り方には、一括受け取りと分割受け取りの二つあります。
退職金は老後の重要な資産なので、自分に合った受け取り方法を考える必要があります。
一時金で受け取り
- 退職所得控除が適用され、税金面で有利
- 一度に大きな金額を受け取って浪費してしまう人が多い
- うまく運用しないと目減りしていく
- 一時金が向いてる人→投資経験あり・管理が得意・まとまったお金が必要
- 有利な節税
分割で受け取り
- 分割で受け取る場合は、雑所得として公的年金等控除が適用される
- 雑所得=公的年金等の収入額ー公的年金等控除額
- 国民年金・厚生年金と合算した金額で計算される
- 国民健康保険・介護保険の保険料が増える
- 一時金受取より控除額が少ない
- 予定の金額を受け取れないことがある
- 分割受け取りが向いてる人→長期にわたって収入を得たい人
退職金の受け取りのポイント

1.一時金と分割を併用する→一部を一時金で受け取り、残りを分割して受け取るとリスクを分散できる
2.退職金控除を最大限活用する→退職所得控除額は勤務年数が長いほど大きくなる
3.他の収入を考慮する→副業で月数万円の収入増があると老後のライフプランが改善する
まとめ
・退職金の受け取りには一括と分割の2種類がる
・一括と分割とでは税金の計算が異なる
・どちらにもメリットとデメリットがある
・自分のライフプランにあった選択をする
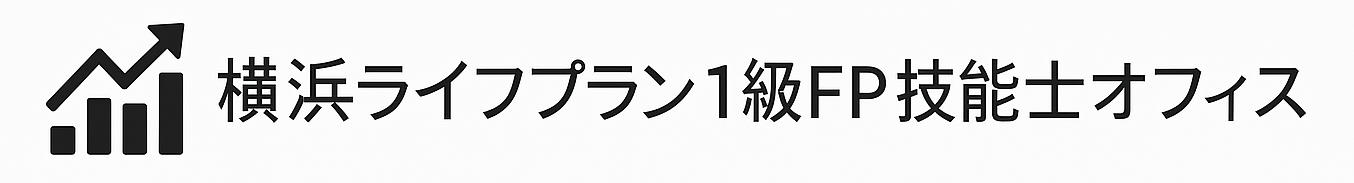



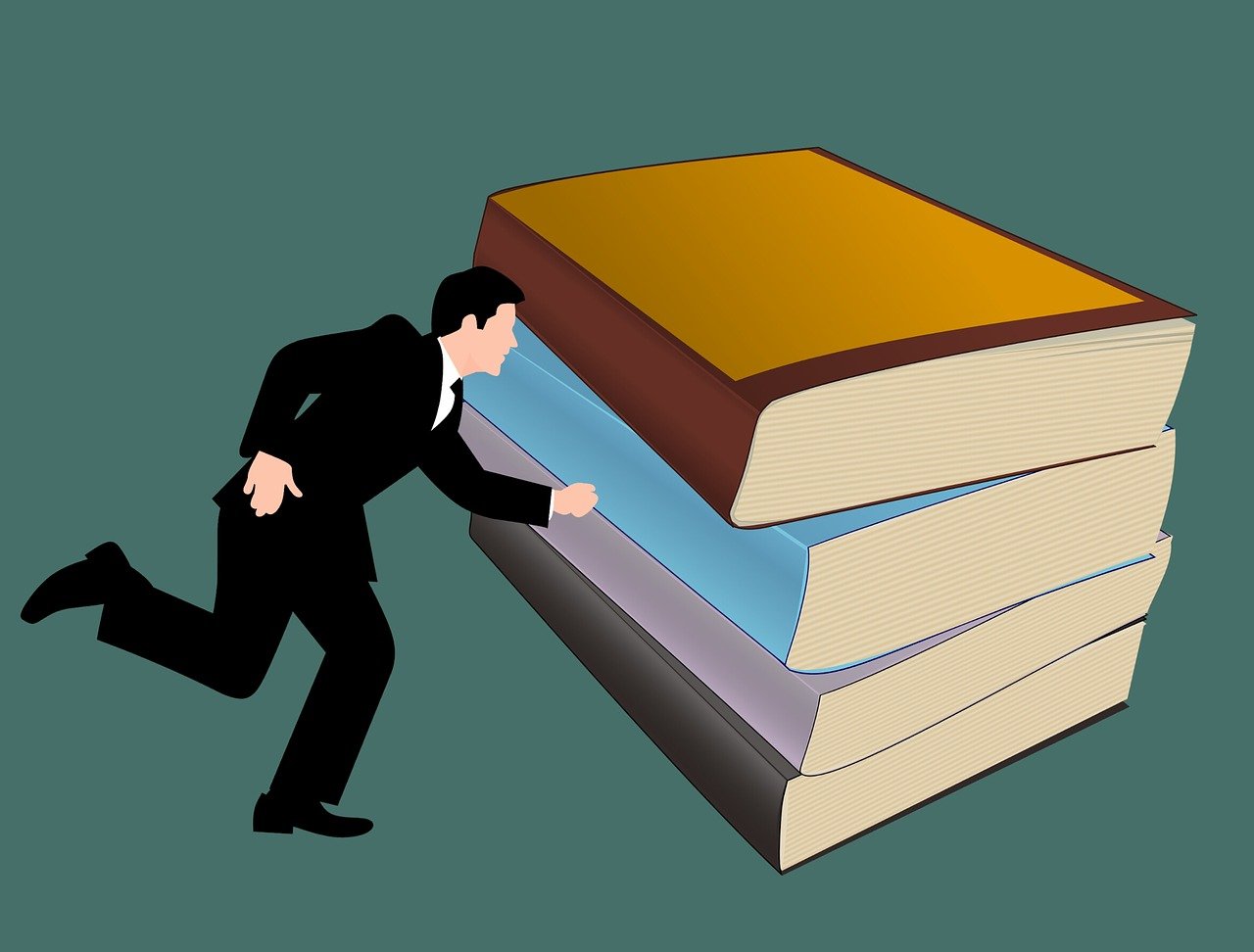
コメント Comments
コメント一覧
コメントはありません。
トラックバックURL
https://yokohama-lifeplan.com/money/receiving-retirement-benefits/trackback/