社会保険制度だけだと老後の生活費が不足することが知られるようになりました。
また、銀行に預けているだけではいつまで経っても増えないので、投資に興味を持つ人が増えています。
加えて法律の改正によって、iDeCo(イデコ)の対象が拡大したことから、多くの人がiDeCoに興味をもっているようです。
ただ、名称がよくないせいなのか、メリットが多い割には利用している人はまだまだ少ないように見えます。
- 年金だけでは老後は生活できない →投資に興味を持つ人の増加 →iDeCoの対象拡大
iDeCoは国が推奨する老後対策
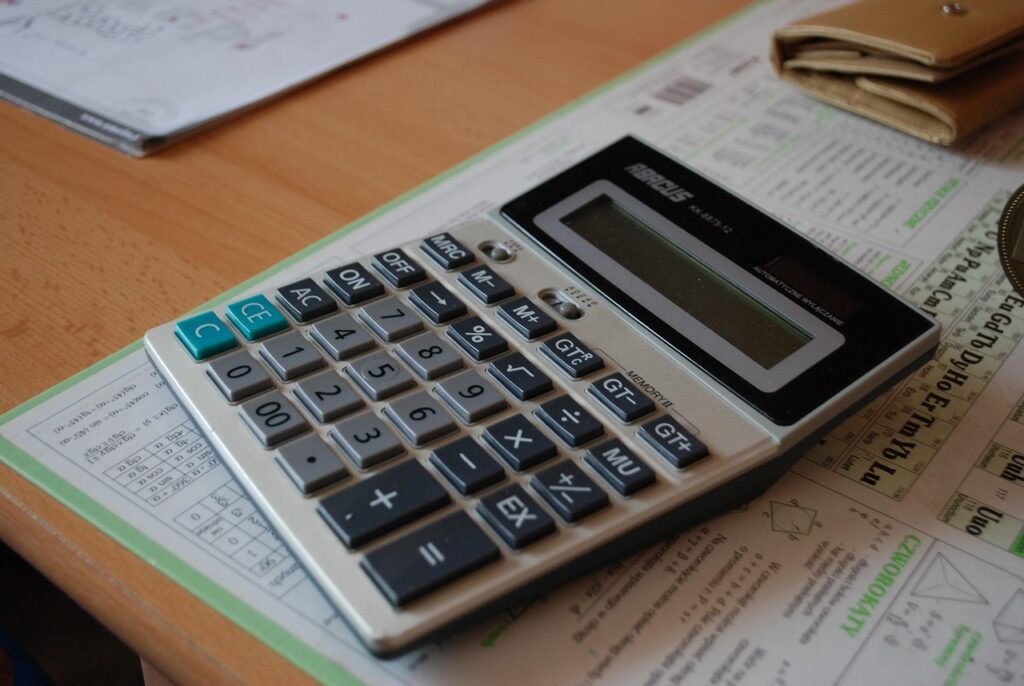
iDeCoは、国民年金の第1号被保険者~第3号被保険者まで利用できる制度です。
第1号被保険者は、20歳以上60歳未満の学生や自営業者、無職の人で国内に住所が有る人が対象になります。
第2号被保険者というのは、会社員や公務員等が対象です。
第3号被保険者は、20歳以上60歳未満で第2号被保険者に扶養されてる人が対象です。
つまり、日本は国民皆年金なので、国民年金の被保険者である20歳以上60歳未満であれば、全ての人が利用できることになります。
知名度が低いiDeCoですが、この制度をうまく使うことでたくさんのメリットを享受することができます。
ただし、iDeCoの目的が自助努力による老後資金の形成であることから、この制度なりのデメリットもあります。
メリットがあっても普及しないのは自分で資産運用するから?

メリットの割にiDeCoがイマイチ普及しないのは、自分で商品を選択しなければならないことにあるようです。
iDeCoでは、加入者自身が掛金額を決めて拠出し、自分で運用します。
そして、運用の結果が将来自分の受け取る年金となります。
つまり、運用した結果がイマイチで、自分の受け取る年金が少なかったり、マイナスであったとしても自己責任ということです。
これではiDeCoを利用する人の運用知識が、自分の老後生活に影響しかねないことになります。
自己責任で商品を選んで、自己責任で運用していくというのは、全くの初心者にはハードルが高い気がしますが、ポイントを知ればたいしたことありません。
iDeCo →投資信託を使った積立 →初心者向き
iDeCoの運用商品は運営管理機関ごとで異なる
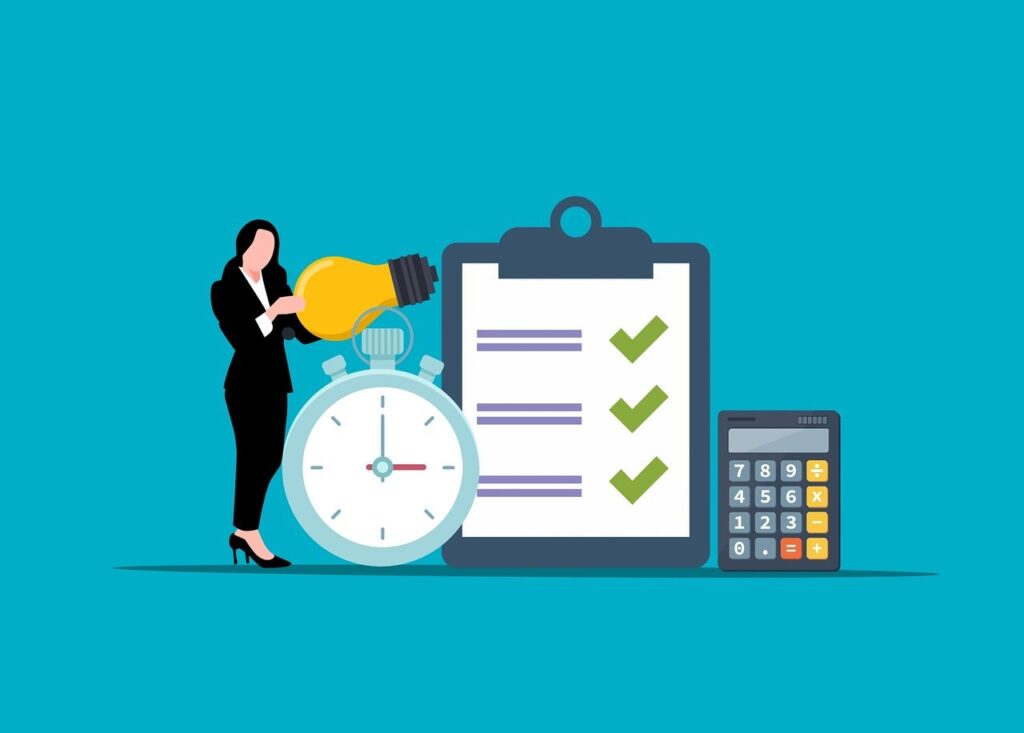
iDeCoでは、運営管理機関によって運用商品が異なっています。
運用商品の中には、預貯金といったリスクのないものから、投資信託といったリスクのあるものまであります。
加入者は、いくつかある運用商品の中から、3つ以上の商品を選択します。
中には、選択した運用商品がすべて元本確保型の商品を選択なんて人も多いようです。
リターンとリスクは比例するのが原則なので、元本確保型の商品ではリスクが少ない反面リターンも少なくなります。
将来の年金がたいして増えないということに気づいて勉強し始める人もいます。
iDeCoには加入者ごとに掛金の上限がある

税制上の優遇があることから、idecoには掛金に上限がもうけられてます。
掛金を拠出する場合は、自分が国民年金の何号被保険者にあたるのかや、会社に企業年金があるかどうかで掛金の上限額が異なります。
idecoの掛け金の上限は、以下の通りです。
| 対象者 | 拠出限度額 | |
| 第1号被保険者 | 自営業者等 | 月68,000円 |
| 第2号被保険者 | 確定給付型を実施している、公務員、私学共済加入者 | 月12,000円 |
| 第2号被保険者 | 企業型年金のみ実施 | 月20,000円 |
| 第2号被保険者 | 確定給付も企業型年金も実施していない | 月23,000円 |
| 第3号被保険者 | 専業主妻(夫)等 | 月23,000円 |
会社員などの厚生年金の適用者が第2号被保険者になります。
第2号被保険者の扶養配偶者が第3号被保険者になります。
※追記 2024年12月に一部の対象者に掛け金の引き上げがあります。
iDeCoの最大のメリットは、3種類の節税効果

iDeCoには、3種類の税制上の優遇措置が取られています。
iDeCoには、掛け金を拠出したとき、運用して運用益が出たとき、受け取りのときの3段階でそれぞれ税制上の優遇があります。
- 拠出時→所得控除
- 運用時→運用益非課税
- 受取時→税制優遇
投資では、「ハイリスクハイリターン、ローリスクローリターン」といったようにリスクとリターンは比例します。
しかし、iDeCoの税制上の優遇によって、ローリスクなのにミドルリターン、ミドルリスクなのにハイリターンが可能です。
iDeCoの掛け金を拠出したときの節税は所得控除
iDeCoでは、掛金を拠出した場合に所得控除として課税所得を減らすことができます。
拠出する掛金は全額非課税なので、所得が多く、拠出する掛金が多い人ほど大きな節税効果が期待できます。
特に第1号被保険者の自営業者等は、掛け金の上限が大きいので、所得が大きいほど大きな節税となります。
仮に年収が500万円であれば、所得控除20%と住民税10%で合計30%の利回りで運用したのと同じような効果です。
運用期間中に運用益や譲渡益が出たら節税
iDeCoでは、運用した掛金に譲渡益や配当益が出ても、将来の年金受け取りまで課税されません。
そのため、課税の繰り延べ効果が期待でき、複利効果もより期待できる仕組みです。
一見すると小さく見える利率でも、長期間になると無視できないレベルの効果を生みます。
掛け金の受け取り時は、退職所得控除や公的年金等控除の扱いで節税
iDeCoでは、掛け金を将来に受け取るときも税金が優遇されます。
年金として受け取る場合は、公的年金等控除として扱われ、他の雑所得よりも優遇されます。
一時金として受け取る場合は、退職所得として扱われ、退職所得控除が適用されるため節税効果は大きいです。
拠出金の受け取りは60歳以降というデメリット

いろいろと節税に期待できるiDeCoですが、iDeCoの目的は老後資金の形成、つまり年金のためです。
したがって、iDeCoでは途中で任意に脱退することは出来ず、拠出した掛け金は60歳以降にならないと受け取ることができません。
つまり、iDeCoは老後資金の形成目的としてしか使えないので、自営業者が資金繰りのために使うことはできません。
日本は、国民皆年金なので、全ての国民は原則的に年金が受け取れます。
しかし、実際に年金を受給している人の多くが公的年金だけでは生活が苦しいといっています。
ライフプラン相談を受けていても、資産がマイナスになるのは、ほとんどの人が老後になってからです。
これから益々平均寿命が延びていくことを考慮すると、受け取りを遅らせてでも運用して殖やすことを考えたほうがいいかもしれません。
特別法人税が復活する可能性
特別法人税は、企業年金の積立金に課税される税金です。
現在は、特別法人税が凍結されています。
特別法人税の税率は、1.173%となっており、この特別法人税の凍結が解除されたら、運用が利益を出しても損失を出しても税金が課税されます。
もし、特別法人税が復活したら、毎年最低でもこの税率を上回らないと資産は目減りしていくことになりますから、安全資産のみで運用していると厳しいかなと思います。
20代、30代であれば、今のうちにリスクとの付き合い方を学んでおくのがいいと思います。
今回のまとめ
・iDeCoは、20歳以上60歳未満であれば、ほとんどの人が利用できる。
・運用商品と手数料は、運営管理機関で違う。
・iDeCoでは、所得控除、運用益非課税、受け取り時優遇課税といった3つの時点で税制の優遇措置が取られている。
・iDeCoの目的は、老後資金の形成なので、長期運用、分散投資が基本となる。
・iDeCoの商品は元本確定型や投資信託と初心者向きのものが多い。
・国民年金の被保険者の種別等で掛金の上限が異なる。
いつまで経っても景気が良くならない政治、相次ぐ政治家の不祥事、収入が変わらないのに増税・社会保険料増額によって国民の生活は苦しくなるばかりです。
私は祖父が自民党員でしたが、最近の自民・公明を見てきて今の政権に期待することを止めました。
全く景気が良くならないのに、税金と社会保険料だけは増加しており、国民負担率だけが世界一になりつつあるのが今の日本です。
日本と同じくらい国民負担率が高い国では、老後は手厚く保障されているのが普通です。
日本のように国民負担は世界トップクラスなのに、保障はわずかという国は他にありません。
こうなると自分たちで身を守るしかありません。
iDeCoは数少ない自分でできる老後対策の一つです。



コメント