長期の積み立て投資では、長期間ほったらかしでよいと思われがちですが、実際は年に1回程度の見直しが推奨されています。
リスクがある資産形成では積立投資が推奨され、リスク対策にもなりますが、複数の投資信託・株式を何年も保有してると設定した資産配分とのズレが生じてきます。
最初に設定した資産配分とのズレを解消することはリバランスといわれ、年に1回、2~3年に1回程度することが推奨されてます。
リバランスは主にリスクコントロール目的で行われます。
目次[閉じる]
なぜ最初の資産配分は時間とともに崩れていくのか?

毎月5万円を将来の老後資金に貯めようと思った人がいた場合を例にリバランスについて解説します。
全部を世界株式を対象にしたインデックスファンドだとリスクが高いので、銀行預金と債券中心の投資信託も購入します。
初期の資産配分
- 銀行預金(20%)1万円(リターン0.02%)
- 債券投資信託(20%)1万円(リターン3%)
- 世界株式投資信託(60%)3万円(リターン8%)
- 全体のリターン(5.4%)
それぞれの利回りが違うので、ほったらかしの期間が長くなるほどバランスが崩れていきます。
10年後(例)
- 銀行預金 120万円(15%)
- 債券投資信託 139万円(17%)
- 株式投資信託 540万円(68%)
反対に市場が悪くなって株価が下落した場合もバランスは崩れます。
10年後→1年後に株式市場20%下落
- 銀行預金 120万円
- 債券投資信託 143万円
- 株式投資信託 432万円
株式市場ではマイナス20%は珍しいことではありません。
さらにNISAの成長投資枠で個別株やコモディティETFを購入すれば、価格の変動は大きくなり、全体のバランスも崩れやすくなります。
リバランスとは?|増えすぎたリスクを元に戻す作業

投資のリバランスは、資産配分を見直して調整することです。
積立投資で崩れた資産配分のリスクを適切に管理するため、最初に設定したバランスに戻るよう投資信託を売ったり購入します。
リバランスの例
- 普通預金20%・投資信託20%・株式60%
- 普通預金160万円・投資信託160万円・株式480万円
株式が15%値下がった → 普通預金160万円・投資信託165万円・株式408万円
元の比率に戻す → 普通預金147万円(20%)・投資信託147万円(20%)・株式440万円(60%)
リバランスをするとどう違う?例で比較

投資のリターンはリスクに比例するといわれてるので、株式の比率が増えるとリスクも増えることになります。
リバランスを定期的に行えば、増えたリスクを抑えることにつながります。つまり、リバランスの目的はリスクコントロールといえます。
また、株式が高騰していれば、利益を確定することにもなります。
リバランスをしない場合とした場合の比較
1年で株価が20%上昇→2年目株価が10%下落→3年目は株価が10%上昇した場合
●リバランスしない場合
| 普通預金160万円 | 債券160万円 | 株式480万円 | |
| 1年(株価20%上昇) | 160万 | 165万 | 576万 |
| 2年(株価10%下落) | 160万 | 170万 | 518万 |
| 3年(株価10%上昇) | 160万 | 175万 | 570万 |
資産合計905万円
●リバランスした場合
| 普通預金(20%) | 債券(20%) | 株式(60%) | |
| 1年(株価20%上昇) | 180万 | 180万 | 541万 |
| 2年(株価10%下落) | 170万 | 170万 | 511万 |
| 3年(株価10%上昇) | 181万 | 181万 | 544万 |
資産合計906万円
株式が好調なら株式を売却することになるので、その後も株式が好調ならリバランスをした分パフォーマンスは悪くなります。
しかし、株式市場では定期的に暴落があるので、あまりリスクを取り過ぎないということは大切です。
リバランスはパフォーマンスを良くする目的ではなく、主にリスクコントロールのために行われます。
◎リバランスの方法
- 1年、2年ごとに比率を調整
- 〇%乖離したら調整
- 売却しないで買い増して調整
リバランスのデメリット
・株価上昇する場面ではパフォーマンスが下がる
・売却時に課税、購入時に手数料がかかる(コストがかかる)
・リバランスのタイミングが難しい
・iDeCoではできない
リバランスは、積立投資やドルコスト平均法でも活用できる
 NIS
NIS
リバランスは、積立投資でも活用できます。
積み立て投資は毎月コツコツ買い続ける手法なので、一度始めるとその後は放置しやすい特徴があります。
投資信託や債券、株式を積立投資していれば、長期間の運用で値上がりした資産の比率が増え、資産の配分が偏ることがあります。
そこでリバランスによって、増えすぎた資産を売って、比率が下がった資産を買い戻せば、最初に決めたリスク水準へ戻すことができます。
つまり
-
ドルコスト平均法=買い方の工夫
-
リバランス=持ち方(リスク管理)の工夫
となり、この2つを組み合わせることで、ほったらかしに近いのに、リスクは取り過ぎない投資を実現できます。
まとめ|積立投資の成功法則=コツコツ積立+年1のリバランス
- 投資のリターンは資産配分による
- 複数の商品を積立投資してると資産配分にズレが出る
- リバランスは資産配分のズレを調整すること
- リバランスの目的はリスクコントロール
- リバランス時に課税・手数料がかかる
- 資産が大きく乖離する前に行うのがよいとされている(1年~3年に1回)
- リバランスのメリットとデメリットを理解して賢く行う
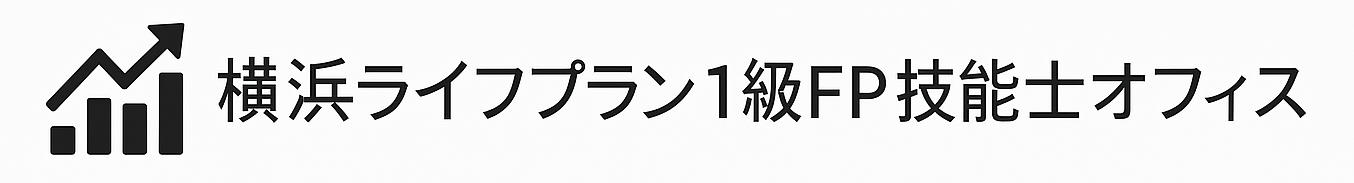




コメント Comments
コメント一覧
コメントはありません。
トラックバックURL
https://yokohama-lifeplan.com/money/adjustment-of-investment-balance/trackback/