「いつまで家賃を支払い続けるか?」
賃貸暮らしを続けていると、月々の家賃が無駄に思えてくることがあります。そして、住宅ローンを終えた持家なら、働かずに生活していくことも不可能ではありません。
持ち家を持つことは、ただ居場所を確保するだけではありません。家計の固定費を抑え、資産を形成する手段にもなります。
少し前にファイナンシャルプランナー(以下FP)の勉強会に参加した際に老後のライフプランについて話題になったのですが、その時に持家と賃貸とはどちらをすすめるかについてアンケートを取りました。
20人程度の勉強会でしたが、ほとんど(8割)は持家派でした。
勉強会なので普段は会社員として働いてる人もいましたが、FPとして活動してる人はみんな持家を支持してました。
私はいくつかのFP団体に所属してますが、他のFP団体でも持家派のFPが多かったです。
このサイトでは、持家の方が住宅のグレードが良いので、その点も考慮したほうがよいと書いてきましたが、金銭的なことばかり目がいくFPでも持家派が多いのには理由があります。
目次[閉じる]
FPが重視するのは「老後のキャッシュフロー」

FPソフトが前提にしている考え方
ライフプランはFP相談の中心となる部分ですが、ライフプランではFPソフトが一般的に使われています。
FPソフトでは数値を入力して将来を予測するので、良い悪いが数値でしか判断できません。
FPソフトによっては年金が本来の額より高額になるものもあります(多い)。
また、予測するインフレ率や利回りによって将来まったく違うものになります。定期的な見直しが必要なのは、将来の予測が難しいからです。
FPソフトでは現在の状況を前提に将来を予測するので、今の家賃が死ぬまで続く設定では基本的に持家が有利になります(修正はできる)。
キャッシュフロー構造の限界
- 数値で判断しがち
- 住み心地や価値観を数値化しにくい
- 将来のインフレ率の予測が難しい
こういった理由から、FPが持家の思想ではなく、キャッシュフローの構造を冷静に見た結果といえます。
高齢者は賃貸住宅を借りにくい現実
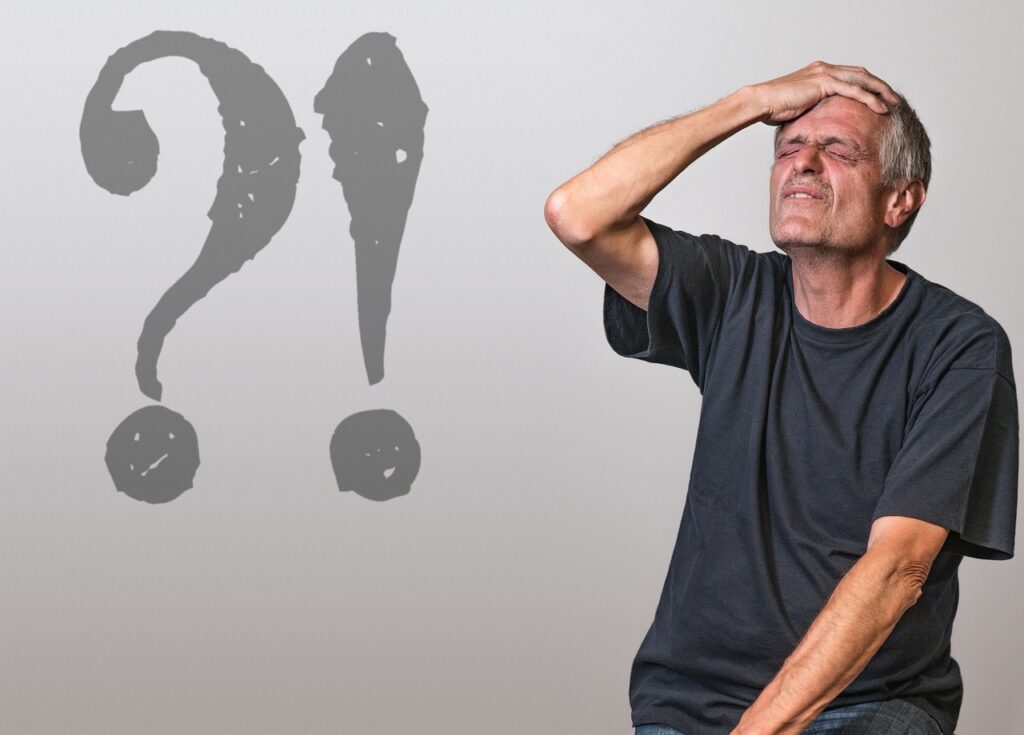
賃貸のメリットは、いつでも自由に住む場所を変えられるという点です。
賃貸であれば、隣人とトラブルがあっても直ぐに引越すことができますし、田舎に引っ越して老後を過ごすこともできます。
賃貸のデメリットとしてよく知られてるのは、一生家賃を支払い続けなければならず、また、いくら住み続けても自分の資産にならない点です。
実際に家賃に住んでる人に聞くと、家賃を支払い続けるということは自分が思っていたよりも大きな負担だとみんないいます。
高齢になると賃貸で不利になる理由
高齢者は部屋を借りにくいという点もあります。
高齢者は収入が少なかったり、孤独死を忌避されて断られることが多いからです。
また、親族がいないと何かあった時に管理会社や賃貸人は連絡できません。
孤独死は事故物件として扱わなくてもよいとされてますが、長く放置された場合は事故物件として扱わなければいけないこともあります。
●高齢になると部屋が借りにくい理由
- 収入が少ない
- 孤独死を嫌がられる
- 親族がいないと連絡先がない
これらの理由から高齢者は部屋を断られがちです。
インフレ時代は借りる側が不利
物価が上がれば家賃も値上がりする可能性があります。
不動産はインフレに強いといわれてますが、これは所有者側には有利ですが、借りる側には不利になります。
老後視点で見た賃貸のデメリット
- インフレで家賃が上がる
- 一生家賃を支払い続ける
- 高齢者は借りにくい
持家のほうが住宅の質が高くなりやすい

賃貸は事業、持家は自己利用
不動産投資は事業として行うので利益が重視されます。
投資家としては、収入は多く費用は少なくが理想なので、部屋に費用をかけ過ぎると損をします。
このような理由を一因として持家の方が通常は家の質が良いとされています。
酷いアパートの中には、壁がベニヤかと疑うような音漏れもあります。
隣の部屋の音が丸聞こえという話は珍しくありません。先日見たテレビでは、隣が空室なのに二つ隣の部屋に住む人のおならもよく聞こえると放送されてましたが、そういうのも割と聞く話です。
-
賃貸=利回り重視 → コストカット
-
持家=住み心地・断熱・遮音重視
低金利時代の住宅効果
昔は金利が高かったため、家を買えるのは収入が高い人だけでした。
しかし、今は住宅ローンが低金利時代なので、賃貸より品質の良い住宅が安く手に入ります。
現在、1,780万円で売りに出てるマンションが12万円で貸し出されてます(空室)が、これを金利0.518%で購入すれば返済額は4万6347円です(35年ローン)。
貸し出さずに自分で住んだ場合、これに管理費と修繕積立金、固定資産税がかかりますが、それでも8万円程度です。
賃貸12万円 > 持家(8万円)
注:あくまでも一例です
持家であっても住宅にお金はかかりますが、死ぬまで住み続けられる家を確保できると思えば安心を得られます。
◎持ち家の特徴
- 持ち家の方が質が良い
- 金利が低い場合→安く買える
- 修繕費・固定資産税を考慮しても安い
- 一方でインフラの問題や資産価値の下落も
持家は住む資産として活用できる

家は保有してる限り費用がかかるので、田舎にある家だとただでいいから引き取ってもらいたいという人がいます。
田舎への移住を考えてる人ならこういう話に乗ってもいいかもしれません(ほとんどは価値がない)。
しかし、田舎が不便で都心に戻る人は多く、また田舎になじめず戻る人も知っています。
売却・賃貸・資金化という選択肢
都心に持家があれば、それを売って田舎へ移住する時の資金にすることができます。
また、自宅を売って住み続けるリースバックというサービスもあります。リースバックは、所有権を売りますが、そのまま家賃を支払って住み続ける方法です。
また、自宅を担保に借入れるリバースモーゲージというサービスもあります。リバースモーゲージはその人が亡くなった時に自宅を売却して借入金の返済に充てる方法です。
もし、保有している自宅が不要になれば、貸せるのであれば賃貸に出してもいいですし、売却して処分することもできます。
-
売却して住み替え
-
賃貸に出す
-
リースバック
-
リバースモーゲージ
税制優遇がある
忘れてはならないのが、住宅ローンがある人や売却した場合は、様々な税制を利用できるメリットもあります。
- 持家→様々な税制がある(譲渡所得の特例、固定資産税の軽減措置、相続税の特例、住宅ローン控除など)
老後資金・介護資金として
自宅を売却して老後資金にしたり、老人ホームの資金に充てることもできます。
ただ、老人ホームに入居しようと思っても最近は倍率が高く、費用も高くてできない人が増えています。介護関係の副業をしたことがありますが、希望しても簡単には入居できないようでした。
- 持ち家を売却して老後資金・介護資金に
- 持家がある→住む家を確保
持家の注意点|ローンと相続は早めに考える

住宅ローンは以下の点にも注意が必要です。
-
完済年齢の制限
-
返済期間の違いによる負担差
- 不動産特有のトラブル
年金生活でローンの返済は大変
賃貸にするか持家にするかはその人のライフプランや働き方にもよるので正解が一人一人違います。しかし、持家の場合はあまり先延ばしできない問題があります。
それは住宅ローンの返済がいつ終わるかの問題です。ちなみに住宅ローンは多くの金融機関で70歳以下、かつ完済時年齢80歳未満と設定されています。
借入れ期間が短ければ毎月の返済額は高額になりますし、審査も厳しくなります。
何より年金で住宅ローンを返済するのは大変です。
住宅ローンを2,000万円借りた場合の毎月の返済額
◎金利0.6%、返済期間20年と35年とを比較
- 返済期間20年の場合:88,454円(総額21,228,987円)
- 返済期間35年の場合:52,805円(総額22,178,427円)
毎月の返済額の差は35,649円なので、短い返済期間では大きな負担になります。
金利がもっと高ければ差も大きくなるでしょう。
相続トラブルの火種になりやすい
持ち家があるデメリットには、相続で不動産があるともめることが多いです。
認知症になると法律行為ができない(不動産を処分できない)ので、認知症になる前の対策も重要です。
まとめ|持家か賃貸かの正解は一つではない
◎ファイナンシャルプランナーに持家派が多い理由
- キャッシュフローが安定する
- 高齢者は部屋を借りにくい
- 持家の方が家の質が高い
- 低金利時代は住宅コストを抑えやすい
- 持家が資産になる
- 有利な税制を利用できる
重要なのは持家か賃貸ではなく、老後まで見据えた住まいの設計をしているかどうかです。
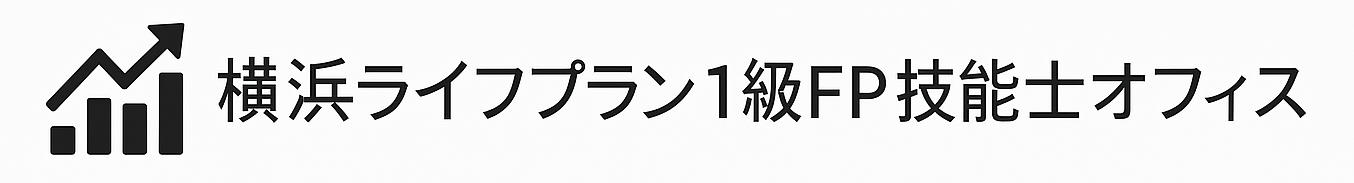




コメント Comments
コメント一覧
コメントはありません。
トラックバックURL
https://yokohama-lifeplan.com/money/why-owning-a-home-is-advantageous/trackback/