人生100年時代が到来といわれるようになりました。とはいえ、お金の備えを「いつか」「そのうち」と先送りにしていませんか?
「住宅ローンの返済が終わったら考えよう」
「子供が社会人になってからでいい」
このように先送りにしていると、安心できない未来を招いて後悔するかもしれません。
人生100年時代といわれる時代にはライフプランを考えることが必要です。平均寿命が延びれば長く働くことが必要になってきます。
現在の社会保険制度は平均寿命が70歳よりも短いときに設計されたものなので、平均寿命が80歳を超えた現在では想定以上の長寿に追いついていません。
寿命が延びることはかつては目出度いことでしたが、現在はリスクと見られるようになりつつあります。
一般的に老後は年金収入でやりくりしていくことになりますが、退職金が3,000万円以上あっても生きている間に資産が無くなってしまう人もいます。
将来、資産が底をつく可能性が分かれば、早めに対策を立てることができます。
対策を立てる上で役に立つのがライフプランとキャッシュフロー表です。
資産形成も若いうちから行えば、少額でも複利が活きてきます。 毎月2万円でも25歳から積立投資をすれば、60歳の時には1480万円(3%)になります。しかし、45歳からでは毎月4万円を積立投資しても、60歳の時に900万円(3%)にしかなってません。
ライフプランを考えることは単にお金の表を作るだけではありません。自分のキャッシュフローを見て、NISAやiDeCoの利用を始めた人もいます。
自分のライフプランと向き合うことは、様々な制度に触れる機会が増え、セカンドライフの働き方の選択肢を増やすことにもなります。
目次[閉じる]
ライフプランとキャッシュフロー表の作り方

ライフプランとは人生設計のことをいいます。
人生の節目や目標を達成するために資金計画を立て、将来の安心を確保したり、改善するための設計図のようなものです。
ライフプランをもとに10年、20年の長期的な視点に立って家計の収支を予測するのがキャッシュフロー表です。
30年、40年といった長期のキャッシュフローを立てることもできますが、あくまでも予測なので定期的な見直しが必要です。
キャッシュフロー表はエクセルやスプレッドシートがあれば、基本的に誰でも作ることができます。
ファイナンシャルプランナー(以下FP)が作るライフプラン・キャッシュフロー表だと少し複雑なものになりますが、簡単なものなら誰でも作れます。
FPに相談した場合との違いは改善策や制度についての回答あるかどうかです。様々な制度について知らなければ、改善策の選択肢も少なくなるからです。
- 将来の不安→保険・貯金しか知らない→どちらか
- 様々な制度を知っている人→自分に合った対策を選べる
①ライフイベントと必要資金を洗い出す
ライフイベントの把握や将来の収入、支出、現在の貯蓄が分かれば、キャッシュフロー表が作成できます。
ライフイベントとは、ライフプランで起きるイベントをいい、結婚や住宅購入、子供の進学などがイベントに該当します。
ライフプランでは将来の収支を予測する必要があるので、まず、今後の人生で発生する大きなライフイベントを整理します。
注目するのはお金(キャッシュ)がかかるライフイベントということです。
◎ライフイベントの例
- 車の購入(買い替え)
- 結婚
- 出産
- 住宅の購入
- 子供の進学(教育資金)
- 老後資金の準備(貯蓄・投資)
- リタイアメントプラン(リタイア後の生活設計)
上記の例は大きな資金が必要なイベントですが、毎月の収支では他にも旅行や趣味、習い事も書き出します。
既に支出することが分かっているものだけでなく、将来の目標や計画(何歳までにいくら必要)も大まかに書き出します。
②収入・支出・年金を整理する
現在の収入と支出を整理します。
会社員なら源泉徴収票、個人事業主なら確定申告から収入が分かりますが、収入は税金と社会保険料を控除した可処分所得を使います。
支出が分かれば何でもいいですが、家計簿をつけると把握しやすいです。
賃金の上昇率や物価のインフレも予測すると今後のシミュレーションに役立ちますが、複雑になるなら最初は気にしなくてもよいです。エクセルやスプレッドシートなら後から物価上昇や運用利回りも修正できるので。
多くの人が苦手としてるのが年金ですが、実績に基づく年金額はねんきん定期便やネットで知ることができます。
分かりにくいのが将来受け取れる予測ですが、これも現在の収入をもとに大まかに目安を予測できます。

老齢厚生年金はいくらもらえる?計算方法と平均受給額の目安を解説
前回は老齢基礎年金だったので、今回は老齢厚生年金の受給額の目安についてまとめました。 [synx_toc title="目次" depth="3"]老・・・
横浜ライフプラン1級FP技能士事務所
退職金は会社によって違うので、人事や総務の人に聞くのがいいかもしれません。将来、退職金がどうなるか分からないのであれば、出る場合と出ない場合をシミュレーションしてみることもできるので、あまり考え過ぎないでも大丈夫です(向き合うことが大事)。
支出はまとめてでもできますが、ある程度分けると見直しの時に把握しやすいかもしれません。
生活費とひとまとめにするのでなく、基本生活費、住居費、教育費、保険料、車両費などと細かく分類するようにです。
| 収入 | 支出 |
| 給与、賞与、副業収入、年金、一時収入、その他 | 基本生活費、住居費、教育費、保険料、車両費、娯楽費、その他 |
③必要資金と資産運用を計画する
ライフイベントに必要な資金を見積もり、それに向けた貯蓄および投資を計画します。
必要な資金を貯めるためにファイナンシャルプランニングを立てて効率的な方法を考えます。
目標までに期間があれば、株式や投資信託など、ある程度リスクを取った方法もあります。
- 非常用の資金:(緊急用のため、普通預金やMRFなど)
- 生活資金:1年以内に使う予定がある資金(定期預金・普通預金)
- 使用予定資金:10年以内に使う予定がある資金(個人向け国債・社債)
- 余裕資金:10年以上使う予定がない資金(株式・投資信託)
必要な貯蓄額の例
| 住宅資金 | 頭金500万円および諸費用350万円 |
| 教育資金 | 長男大学費用400万円+次男大学費用400万円 |
| 老後資金 | 1億円ー(公的年金+退職金+老後収入)=退職までに準備する額(?万円) |
老後資金のように長い期間が取れるものは、株式や投資信託、NISAやiDeCoを活用すると効率的に増やせます。
④キャッシュフロー表を作成する
キャッシュフロー表にインフレや昇給率などを入れると複雑になるので、まずは分かっている収支を書き出してみることです。
あわせて病気や失業などの想定外の出費に備えて余裕を持つといいかもしれません。

このキャッシュフロー表はスプレッドシートで作ったものですが、インフレや昇給は考慮してません。
本来はインフレや昇給を考慮するのが良いのですが、それらは後からでも設定できますし、予測も難しいので、最初はそこまで気にせず作ってみることです。
キャッシュフロー表を作成したら、定期的に見直しすることも大切です。分かってきたらインフレや昇給も考慮してシミュレーションすれば、様々な角度から考察できます。
⑤支出・制度を見直して改善する
収入の合計から支出の合計を控除した金額が年間の収支になります。
年間収支がマイナスになる年は、支出の見直しが必要かもしれません。
収支のマイナスがある年はそれまでに貯蓄した資産から補うことになりますが、マイナスが一時的ならそれほど問題ないこともあります。
たとえば、子供が進学した時は大きな金額が必要になりますが、他でプラスになって貯蓄が底をつかなければとりあえずは安心といえます。
収入から支出を引いたものの中に何に使ったのかわからない金額を使途不明金といいます。
使途不明金があまり高額になると見直しが必要かもしれません。
家計にプラスになる制度
- 住宅購入:住宅ローン控除
- 出産:出産育児金・出産手当金
- 資産形成:NISA・積立投資
- 病気や死亡のリスク:生命保険・医療保険・健康保険
- 老後資金:iDeCo・公的年金・企業年金
- お得な制度:ふるさと納税
生命保険に加入する時は、社会保険制度の補完として利用を考えると保険料の過大な支払いを回避できます。
キャッシュフロー表の直接的な改善ではありませんが、保険は定期的に見直すことも大切です。
まとめ
◎ライフプランを立てる流れ
- ライフイベントと必要な資金を知る
- 現在の収入・支出・貯蓄残高を把握する
- 必要な資金を計画する
- キャッシュフロー表で将来の資金不足を確認する
- 不足する部分は投資、副業、節税などを考える
ライフプランは、一度作ったら終わりではなく、定期的に見直しをすることが大切です。なぜなら、ライフプランを立てても計画通りにいくことが少ないからです。
計画通りにいかないなら無駄かというとそうではなく、ライフプランを立てることで様々なリスクの顕在化ができます。
リスクが分かれば後は対策を立てることができます。
国の政策によってもキャッシュフローの結果は変わるので、何度でも見直しすることをおすすめします。政治に対する興味も持てるはずです。
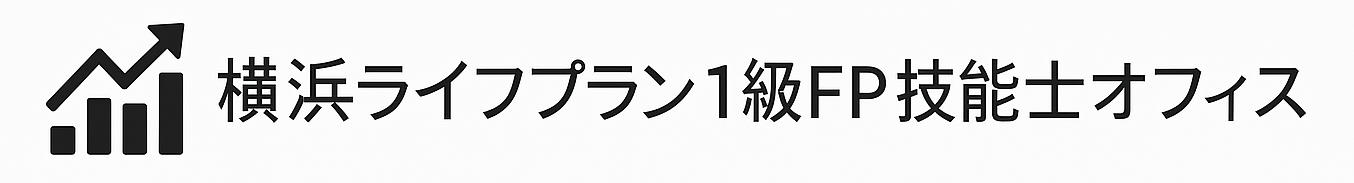



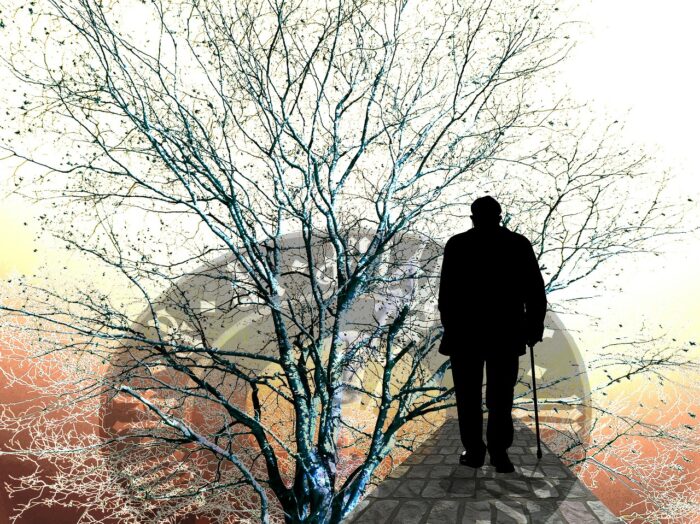
コメント Comments
コメント一覧
コメントはありません。
トラックバックURL
https://yokohama-lifeplan.com/money/how-to-make-a-life-plan/trackback/