年金には公的年金と私的年金がある
何かと話題の年金ですが、年金には公的な年金と私的な年金があります。
公的年金には、日本の20歳から60歳までならすべての人が加入する国民年金と、会社員や公務員が加入する厚生年金保険(以下厚生年金)があります。
公的年金は要件に該当したら原則として加入することになります。
一方、私的年金は公的年金以外の年金をいい、これには企業が福利厚生として行う企業年金や、生命保険会社が販売している個人年金などがあります。
- 公的年金→国民年金と厚生年金
- 私的年金→生命保険の個人年金・企業年金など
また、公的年金が強制なのに対して、私的年金は個人・企業が任意に加入します。
国民皆年金とは?日本の年金制度の基本

日本の公的年金は国民皆年金の制度をとっています。
国民皆年金の仕組み
国民年金が日本に住む20歳から60歳未満のすべての人を対象としてるので、国民は原則として年金に加入することになります。
そして、加入した期間と保険料に応じて将来年金が支払われることになります。
年金額は人によって違う理由
誤解されてる人が多いですが、受け取れる年金額は一人一人違います。
未納の期間があれば、それだけ将来受け取る年金も少なくなります。
◎年金額は人によって違う理由
-
未納・免除
-
被保険者区分
-
報酬額の違い
- 受け取れる年金は一人一人違う → 将来のために年金とライフプランの確認が重要
公的年金は「3階建て」で考えると分かりやすい
公的年金では、基礎になる年金が国民年金、厚生年金は国民年金の上乗せといった位置づけです。
1階が国民年金なら厚生年金は2階部分、iDeCoや個人年金は3階部分といったところです。
| 3階 | 個人年金、iDeCo、企業年金 |
| 2階 | 厚生年金(老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金) |
| 1階 | 国民年金(老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金) |
国民皆年金なので、無職やアルバイトの人も国民年金の第1号被保険者になります。
ただし、前年の所得によっては免除制度の対象になるかもしれません。反対に前年の所得が大きければ、今は無職でも高額の保険料を負担する可能性があります。
国民年金の被保険者は3種類ある

国民年金に加入した場合の被保険者には、第1号被保険者から第3号被保険者までの3つのタイプがあります。
第1号被保険者(自営業・無職・学生)
日本に住んでる20歳以上60歳未満の自営業者やその配偶者、学生、アルバイト、無職などが対象です。
第2号被保険者(会社員・公務員)
厚生年金保険の適用事業所で働く人が対象です。例えば、企業に勤める会社員や公務員の人です。
第2号被保険者は厚生年金の被保険者だけでなく、国民年金の被保険者でもあります。つまり会社員として働いた期間の分として国民年金と厚生年金を将来年金として受け取ることになります。
第3号被保険者(扶養配偶者)
第3号被保険者 第2号被保険者に生計を維持されている20歳以上60歳未満の配偶者です。
第2号被保険者の収入によって生計を維持されているとは、年収が130万円未満のことを指します。
「働き過ぎると扶養から外れる」と言われるのは、130万円以上になると生計を維持されてるとは見られなくなる(自分で保険料を納める)からです。
第3号被保険者は国民年金の加入者ですが、保険料の負担はありません。保険料の負担はありませんが、国民年金の被保険者として年金額に反映されます。
個人事業主が法人化したら
自営業の人は第1号被保険者ですが、その後事業が拡大して法人成りしたら、会社の厚生年金に加入するので第2号被保険者となります。
- 個人(第1号被保険者)→法人化 → 会社の代表取締役(第2号被保険者)
なぜ公的年金だけでは老後が厳しいのか

よく言われる老後2000万円問題(今は3000万円?)は公的年金だけでは老後生活が立ち行かないことを意味してます。
老後2000万円問題
厚生労働省のデータによれば、老後世帯の平均で毎月4、5万円が赤字といわれています。
退職後30~40年生きたとしたら1800~2400万円が不足することになります。
インフレでさらに厳しくなる理由
今までの日本はデフレでしたが、今後はインフレが予測されてるので、2000万円では心許ありません。
しかも、受け取れる年金額は納めた保険料と被保険者の期間によって変わるので、自営業の期間が長い人ほど引退できない可能性があります。
老齢厚生年金も報酬額によって受け取る年金額が違う(報酬が高い人は年金も高い)ので、将来自分が受け取れる年金を知り、早めにライフプランを立てることが大切です。
老後資金は年金+自助努力で考える

若い人であればiDeCoとNISAを活用した積立投資が有効です。
iDeCoの役割(老後専用)
iDeCoは老後資金目的にしか使えませんが、掛け金を拠出した時、運用時、受取時の3つのポイントで税制優遇があります。
NISAの役割(自由度)
NISAは税制優遇が運用時だけですが、目的が限定されてないことに利点があります。
iDeCoとNISAは競合ではなく役割分担
iDeCoとNISAのそれぞれのメリットを利用して使い分けるのが良さそうです。
また、老後資金を取り崩しながら生活する場合もただ取り崩すのではなく、運用しながら取り崩す方が資金が底をつく時期を伸ばせます。
年金の今と未来を確認!ねんきん定期便で分かること・確認すべきポイントとは
まとめ
- 日本は国民皆年金ですべての人が年金制度に加入するが、それだけで老後の生活を賄えるわけではない
- 日本は国民皆年金 ・公的年金には国民年金と厚生年金保険がある
- 全ての日本人が対象になるのは国民年金
- 厚生年金は国民年金の上乗せ
- 国民年金には第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の3種類ある
- 公的年金は一人一人受け取れる金額が異なる
- 自営業者は会社員より年金がかなり少ない
- 年金は土台、上乗せをどれだけできるかが大切
- 公的年金の状況を把握して将来に備えることが大事
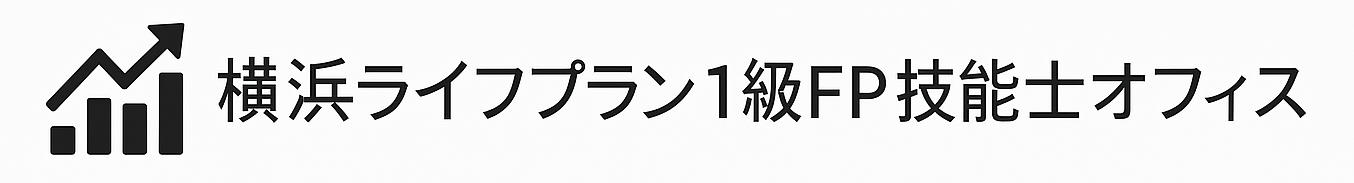



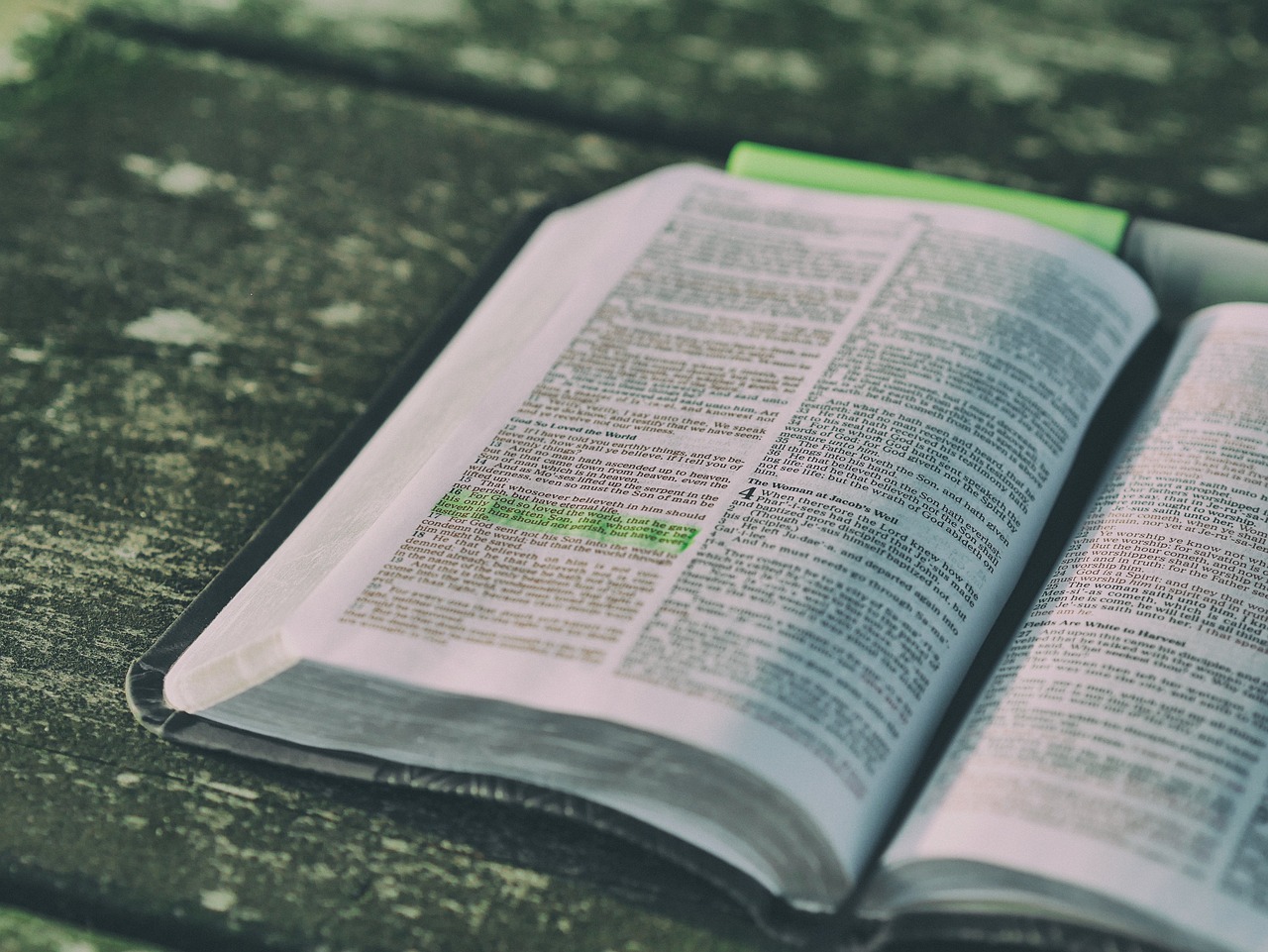
コメント Comments
コメント一覧
コメントはありません。
トラックバックURL
https://yokohama-lifeplan.com/money/universal-pension/trackback/