「デフレからインフレになるっていうけど、このまま銀行預金でいいんだろうか?」
このような疑問をお持ちの方は多いと思います。
30年以上続いたデフレでは、現金を持っているだけで特別なことをしなくても資産価値が維持されてました。
しかし、物価が上がり続けるインフレ時代では、預金だと毎年お金の力が削られていきます。
資産運用のルールでは、デフレ下とインフレ下とでは真逆になるので、両者の違いと基本を知っておくことは資産を守るうえで重要です。
目次[閉じる]
日本はデフレだったから資産運用をあまり考えなくてもよかった
現金預金はインフレやデフレで価値が変化します。
日本の失われた30年では、ずっとデフレが続きましたが、これから予測されてるように日本がインフレになれば、資産運用もそれに合わせなければいけません。
これから訪れるインフレ時代に、失われた30年と同じような運用のやり方では、お金の価値がどんどん失われていくからです。
お金の見た目と実質の違い
1万円札は今も5年後も同じ1万円に見えますが、実際はお金の価値が下がるので、今1万円で買えたものが5年後にはさらに5百円、千円を足さないと買えなくなってるかもしれないのです。
失われた30年では現金預金で保有してもあまり影響はありませんでしたが、インフレ時代で一番怖いのは現金預金で保有することで失う資産の目減りです。
お金の価値を維持するためにも、それぞれの特徴と対策を知っておく必要があります。
●年2%のインフレ
- 現金→100万円→20年後→100万円
- 実際の価値→20年後→67万円(価値が下がる)
- 毎年2%のインフレ→2%分を増やす必要がある
●デフレ時代
- 現金100万円→価値が変わらない、または価値が上がる
- 物価が下がる→多くのものを買えるようになる
インフレとデフレで変わるお金の価値

ニュースでもよく取り上げられてるので、インフレとデフレという言葉はご存じだと思います。
お金の価値は一見すると変わらないように見えますが、これを商品に目を向けると常に変化してることが分かります。
デフレとは何か
デフレの時代の牛丼は一皿400円からどんどん値下げしていった結果、牛丼一杯290円という時代がありました。
これはデフレの影響で物が売れなかったため、値段が下がったからです。
こんな感じで相対的にお金の価値は保有してるだけで上がっていきました。
インフレとは何か
一方、インフレの時代は牛丼価格はどんどん上がり、数年前に350円だった牛丼は気づいたら500円になりました。
これはインフレの影響でお金の価値が下がり、350円では牛丼を買えなくなったからです。
コロナ後は特に様々な商品がどんどん値上がりしています。
また、マンションや一戸建てといった不動産価格も値上がりが凄いです。これに関連して管理費や修繕積立金といった不動産に関係する費用も値上がりしています。
インフレ時代に預貯金はリスクになる

インフレが続くと預金の価値はどうなるか
預貯金の金利は0.1%もありませんので、これは無視できる数値です。
しかし、2%のインフレが続くとなると、これは無視できません。欧米のように3%以上ならもっと大きな影響を受けます。
もし仮に2%のインフレが続けば、10年で20%の価値が失われます。
2%・3%インフレ時の資産価値変化
現在10万円で買えてた商品が、12万円以上出さないと買えなくなってしまいます。
これが20年後は3分の1が失われるので、今の10万円は20年後に実質6万8千円になったのと同じです。
さらに30年後は半分近く(44%)が失われ、今の10万円は5万6千円と同じ価値です。
2%でこうなのですから、3%は言わずもがなです。
3%のインフレによる現金価値の変化
- 10万円
- →10年後の価値:7万4千円
- →20年後の価値:5万5千円
- →30年後の価値:4万1千円
タンス預金ではインフレに対処できないので、このようにインフレ時代にタンス預金はリスクしかありません。
デフレ時代の運用方針

デフレ時代は守りの運用が有効
デフレ時代はお金を保有してるだけで価値が上がるので、あえてリスクを取って株式や不動産で運用する必要がありません。
安定資産の生命保険や債券といったものでも十分といえます。
デフレの時代は金利が下落し、株価も下落するので、日本は対ドルで円高に進みます。
住宅ローンを組んだ人は、デフレだと相対的に借金の負担も増すことになります。また、不動産の価値も下がるので無理して住宅ローンを組んでまで買う必要性もありませんでした。
デフレ時代の運用の考え方
- デフレ時代は物価が下落し、現金の価値が相対的に高まる
- 銀行預金や国債の比率を高める(守りの運用)
- 企業収益は落ち込み株価が低迷→株式投資は慎重に
- 優良株や高配当株が割安で買えるチャンス
- 過度なリスクを取らず、流動性を確保する
インフレ時代の運用方針

インフレ時代は現金だけでは不十分
インフレ時代はデフレと逆なので、お金を保有してるだけでは価値が失われていきます。
株式や不動産である程度のリスクを取らないとお金の価値が目減りしていきます。
インフレに強い資産とは何か
安定資産の生命保険や債券ではインフレに負ける可能性があるため、お金を株式や不動産、コモディティなどで分散投資する必要があります。
インフレの時代は金利が上昇し、株価も上昇するので、日本は対ドルで円安に進みます。
住宅ローンを組んだ人は、インフレで相対的に借金の負担が減ることになります。
無理をしてまで住宅ローンを組む必要はありませんが、不動産の価値も上がるので住宅ローンを組むには有利な状況です。
むしろ様子を見ているうちに金利が上昇して機会を失うかもしれません。
インフレ時代の運用の考え方
- インフレ時代は物価が上昇する→現金だと目減りする
- 株式・不動産・コモディティなどインフレに強い資産(攻めの運用)へ
- インデックス投資や国際投資で分散投資
- 債権は金利上昇で価格下落のリスク
- 成長資産に長期的に分散投資してインフレをカバーする
インフレに負けない運用をするための考え方

インフレ率を上回る利回りを意識する
インフレが2%であれば、最低でも2%を超える運用をすればいいことになります。
ただし、利益や商品には税金がかかるのでその分も考慮しなければいけません。
一極集中を避ける重要性
投資信託の中には平均リターンが10%以上のものもありますが、資産のすべてをその商品に一括して投資するとリスクが高くなります。
全ての資産を同じ商品で運用せず、投資先を分散してリスクに備えることも大切です。
個別株であれば、一つの銘柄だけに集中投資せず、複数の銘柄を保有することで分散投資になります。
期待リターンと分散投資の考え方
期待リターンは資産の収益率の平均で表せられます。
例えば、1000万円の3分の1をそれぞれ期待リターン9%、期待リターン1%、期待リターン3%で保有してれば以下のようになります。
投資収益率=(9+1+3)÷3=4.3…と約4.3%です。
500万円を9%、250万円を1%、250万円を3%なら、利益は45万+2.5万+7.5万=55万円となり、5.5%の利回りです。
5.5%の利回りで運用できれば、現在のインフレ率ならお金の価値を維持するには十分です。
まとめ|インフレ時代は資産運用の考え方を変える
- インフレ時代とデフレ時代とでは運用方針を変える必要がある
- インフレはお金の価値が下がり、デフレはお金の価値が上がる
- インフレ時代ではお金の価値が目減りしていく
- 金利や株価もインフレで上昇し、デフレで下がる
- インフレ下では、インフレ率を超える運用利回りを目指す
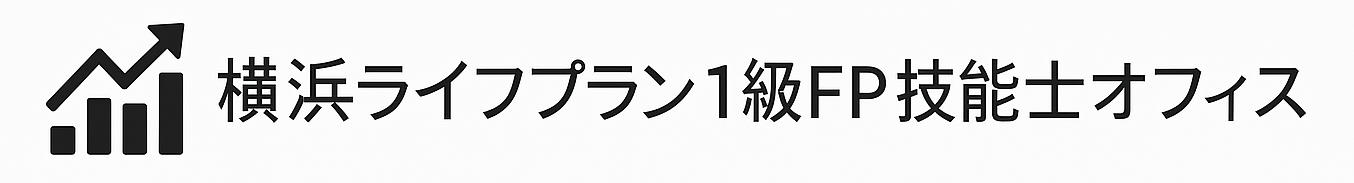




コメント Comments
コメント一覧
コメントはありません。
トラックバックURL
https://yokohama-lifeplan.com/money/asset-management-in-times-of-inflation-and-deflation/trackback/