「投資を始めたものの、気がつけば生活費が足りない……。」
「NISAやiDeCoにお金を回しすぎて毎月のやりくりが大変だ。」
このような悩みを耳にすることが増えました。
せっかく未来のために投資をしたのに、日常生活が圧迫されては本末転倒です。
その原因の多くは、資金を一つの財布として考えてしまうことにあります。
せっかくNISAやiDeCoを始めたのですから、投資を無理なく続けるためにも、まずは手元のお金を目的ごとに分けることが必要です。
目次[閉じる]
増えるNISA貧乏とiDeCo貧乏
老後2000万円問題をきっかけに投資を始める人が増えました。
老後2,000万円問題と投資ブームの背景
この老後2,000万円問題とは、平均的な生活をする人であれば、年金とは別に2,000万円の老後資金が必要とされることに由来します。
2,000万円不足する人もモデルは持家のケースなので、賃貸の人だと5,000万円は必要でないかということでも話題になりました。
老後2,000万・5,000万円問題を背景に、2024年から新NISAが始まり、若い人からお年寄りまで投資に興味を持ち始めています。
NISA貧乏・iDeCo貧乏とは何か
ところがNISAが始まってから、NISA貧乏やiDeCo貧乏が話題になってます。
NISA貧乏、iDeCo貧乏とは、老後のために毎月数万円をNISAやiDeCoに投資したことで、余裕のない生活が更にカツカツになり、貧乏生活に陥ってしまうことです。
NISAとiDeCoの違い
特にiDeCoは引き出せるのが60歳以降なので、無理してiDeCo口座に資金を回す必要はありません。
- NISA→いつでも現金化できる
- iDeCo→原則60歳以降
- 目的に使い分ける
若い人は複利を活かせる
日本人の寿命は年々伸びており、この結果老後に必要な資金が増えてることから、将来に不安を感じて少しでも投資に回そうと思うのは分かりますが、貧乏生活に陥っては本末転倒です。
確かに投資に回せる資金が少額だと、殖やせる金額もそれに見合って少額なので分からなくもありません。
老後にどのような生活をしたいかにもよりますが、若い人は少額であっても複利を活かせられるので、無理のない範囲で運用を考えることが大切です。
何より続けられずに1年、2年で解約しては意味がないので、どうすれば投資を続けていけるかも重要です。
- 投資は継続が重要
- 長期投資→複利を活かせる
投資の基本は長期、分散、積立

初心者は投資信託から始める理由
投資初心者がいきなり個別株を始めるのはリスクが高いので、まず最初は投資信託で投資に慣れることが大切です。
確かに個別株を複数保有すれば分散投資になりますが、個別株は比較的資金が必要なので、初心者が始めるにはハードルが高いです。
投資信託であれば分散の効果が期待でき、数百円といった少額から始められ、何より投資の知識があまり必要ありません。
長期投資と複利の効果
証券会社に毎月の投資額を設定しておけば、毎月決まった額が引き落とされ、気づいたら数百万円になってることもあります。
◎毎月3万円の積立投資を5%の金融商品で30年続けると
- 投資した金額:1,080万円
- 投資利益:1,360万円
- 元利合計:2,440万円
投資信託は選び方と継続が重要
ポイントは価格が上がっても下がっても一喜一憂せず、ひたすら続けることです。
ただし、最初の商品選びでろくでもない商品(コストが高いなど)を選んでしまうと成果も期待できません。
- 期待リターンは商品によって違う
- 投資信託は初心者向き
- 投資信託は保有してるだけでコストがかかる
投資を続けるために手元資金を分ける

投資資金は多いほど有利
同じ商品なら投資のリターン率は同じなので、投資においては資金は多いほうが有利です。
1万円の10%は千円ですが、100万円の10%は10万円となるように、当然、投資資金が多い方が利益の額も大きくなります。
だからといってボロボロの服をまとうような貧乏生活では元も子もないので、投資を続けていける範囲で積み立てていくことが重要です。
生活を圧迫しないための資金の考え方
そのためには手元にある資金を分けて、当分使う予定がない資金を投資に回す必要があります。
手元にある資金には、日常生活に必要なもの、近いうちに使うもの、当分使う予定がないものがあると思います。
食費や水道光熱費、家賃(住宅ローン)といった毎月かかる資金は日常生活に必要な資金です。
子供の教育資金として数年以内に必要な資金や自動車の買い替えを考えてる資金などは、近いうちに使う資金として区別します。
投資に回せるのは残った当分使う予定がない余裕資金です。
また、リストラや震災等、何かあった時に備えて半年から1年分の生活費を別にしておくことも重要です。
数年は使う予定がない余裕資金が投資に回せる資金ですが、近いうちに使う資金であっても少しのリスクなら取れるケースもあります。投資商品の中には国債のような安全性の高いものもあるからです。 そして、老後資金作りの運用の中心になるのは余裕資金です。
4つの資金の分類(財布を分ける)
- 日常生活の資金
- 近いうち使う予定の資金(数年、10年以内)
- 余裕資金(10年以上予定がない)
- 緊急用資金(生活費半年〜1年分)
余裕資金を増やすためにできること
余裕資金を増やすために生活費の見直しも大事かもしれません。
固定費を見直す効果
有効と言われるのは住宅ローンや保険、サブスクリプションや携帯料金といった毎月かかる固定費の見直しです。
私も動画配信サービスやネットゲーム、資格講座などのサブスクリプションを利用してるため、どこか削れないか見直したところ、ネットゲームの解約と2台あるうちの1台の携帯料金を格安会社にしました。
この2つだけでも月1万円の節約になりました。そして、浮いた1万円をchatGPT、Gemini、Copilotに課金したことで、効率よく業務を進められるようになりました。
もしも、この浮いた1万円を毎月積立投資(7%)をしたら、25年後には783万円になります。このように小さな金額でも積み重ねると大きな金額になるからバカにできません。
リスクとリターンの関係を理解する

リスクとリターンは比例する
投資をする際に覚えておくと良いことはたくさんありますが、その一つが現代ポートフォリオ理論ではリスクとリターンは比例するということです。
将来資金を増やしたいと思うのであれば、ある程度のリスクは取る必要がありますが、心配性の人はリターンが少額であってもリスクを取らない方がいいこともあります。
ただし、投資に慣れてきたり、状況の変化でリスクを取れるようになることもあります。
老後までの期間が長い人の考え方
iDeCoで何年か前に話題になったのが、リスクを取らず安全性の高い資産ばかりで運用してる人が多いことです。
そういった人は資産が減らない一方で将来の年金もほとんど増えない点が問題視されました。
- ハイリターン=ハイリスク
- ノーリスク→資産が増えない
- 老後まで期間がある人はリスクを取ることも検討
オールカントリーと全米株式が人気
ニュースやネットではオールカントリーといわれる投資信託が人気です。
オールカントリーの特徴
オールカントリーは、その投資信託だけで世界の株に分散投資できる投資信託です。
日本の経済市場はいまいちですが、世界に目を向けると好調です。
オールカントリーは世界の成長を取り組むことができることから人気です。
ただし、新興国も含まれるのでリスクも高く、経済がうまくいってない国も含まれます。
全米株式の特徴
オールカントリーよりアメリカ市場に連動した投資信託だけで良いという人もいます。
理由は世界の経済市場の6割以上がアメリカなので、いずれにしてもアメリカの影響が大きいからです。
オールカントリーがいいか全米株式の投資信託がいいかは、これは個人の価値観や将来予測によります。
最近では、アメリカを代表する企業(アップル・エヌビディア・アルファベットなど)に特化した投資信託も人気です。
- オールカントリー→世界
- 全米株式→アメリカ
一番怖いのはインフレによる資産の目減り

インフレ時代に投資しないリスク
その時々の物価によって貨幣価値は変わります。
日本は長らくデフレだったので、運用しなくても現金で保有してれば問題ありませんでした。しかし、これから予測されてるようにインフレ時代になれば、現金預金だけでは資産の価値が目減りしていってしまいます。

インフレ時代とデフレ時代の運用は真逆?デフレ時代との資産運用ルールの違い
「デフレからインフレになるっていうけど、このまま銀行預金でいいんだろうか?」 このような疑問をお持ちの方は多いと思います。30年以上続いたデフレでは、現金を持っ・・・
横浜ライフプラン1級FP技能士事務所
2%のインフレが続けば、100万円を現金で保有してる人は20年で68万円に目減りしてしまいます。
インフレ時代の日本では投資をやらないことがリスクになるということです。
インフレに強い代表的な資産
インフレ時代とデフレ時代とでは、運用方法も変えなければいけません。
インフレに強いといわれる代表的な資産は不動産や株式です。 投資信託、不動産投資信託、ETFといった商品なら比較的少額から始められます。NISA貧乏やiDeCo貧乏にならない範囲で投資を継続することが大切です。
- デフレ→現金でも問題ない
- インフレ→現金だと目減りする
- インフレに強い資産→株式・不動産・コモディティなど
まとめ|投資は生活を守りながら続ける
- 投資の基本は長期、積立、分散投資(続けなければ意味がない)
- 手元資金を分ければNISA貧乏、iDeCo貧乏を避けられる
- 投資は当分使わない余裕資金でやる
- インフレ時代は何もしないことがリスク
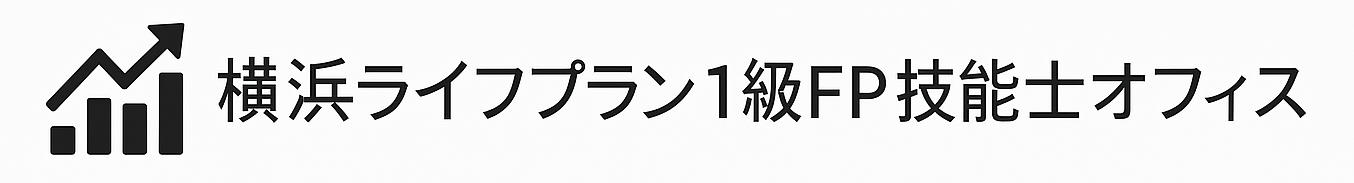




コメント Comments
コメント一覧
コメントはありません。
トラックバックURL
https://yokohama-lifeplan.com/money/divide-available-funds-into-categories/trackback/