目次[閉じる]
リタイアメントプランニングとは何か
老後に向けたお金の計画をリタイアメントプランニングといいます。
老後2000万円問題といわれるように、定年後は現役時代よりも収入が減るため、一般的には年金を受け取りつつ、それまでに蓄えた老後資金を取り崩して生活していくことになります。
少し前に2007年に生まれた子の半分が107歳まで生きるといった話が話題になりましたが、人生100年時代では早めのリタイアメントプランニングが重要とされています。
◎人生100年時代で重要性が高まる理由
-
長寿化
-
定年後の収入減
-
インフレ
老後資金は人生の三大支出の一つ

教育資金、住宅資金、老後資金はいずれも多額の資金を必要とすることから、人生の三大支出といわれています。
老後資金が他の支出と違う理由
人生の三大支出(三大費用)→教育資金・住宅資金・老後資金 特に老後資金は老後までに貯めた資金を取り崩しながら生活していくことから、取り崩し方まで考えなければいけません。
予想外のインフレがあれば必要な資金は増えますし、老後資金を取り崩すのも運用するかしないかで資金の減り方も変わってきます。
- 老後資金→運用をしながらが望ましい
- 運用知識・スキル→必須の時代へ
老後に必要な金額は人によって違う
老後資金をややこしくしてる原因の一つが、必要な老後資金が一人一人異なることです。
ライフデザインが変われば、一人一人に必要な老後資金は違います。
例えば、定年後も自動車が必要な人は買い替えの費用も必要ですし、旅行が趣味の人はその費用も考慮しないといけません。
まずは不足額を知ることが重要
できるだけ現状で把握できることは把握し、大雑把でいいので不足額を知ることが大切です。
不足額を知ることができれば、データや資料をもとにリタイアメントプランニングを立てることができます。
必要な額が分かればあとは目標に向かって行動がとることができ、定期的に修正もできます。
把握しやすいもの・把握しにくいもの
◎把握しやすいもの(データや資料から分かる)
- 年金、生活費の平均費、葬儀費用の相場、住宅のリフォーム平均費用、自動車の買い替え費用、期待利回り
◎把握しにくいもの
- 将来のインフレ、再就職、再就職後の収入、将来の病気(医療費)、実際の利回り、将来の税金・社会保険料
老後に1億円必要は本当か?

若い世帯を中心に年金不要論が叫ばれています。しかし、年金不要論を叫んでいる人が老後の準備をできているかというと、そうでない人の方が圧倒的に多い気がします。
話を聞くと、年金不要論を叫ぶ人に限って老後に向けた準備ができておらず、貯金もないことが大半です。
年金がなかった場合の試算
もし仮に年金制度がなかったとしてら、退職後の20年で1億円が必要です。
生命保険文化センターによると、ゆとりある老後のためには毎月38万円(2016年)が必要とされています。
ゆとりある老後を暮らそうと思うのであれば、20年だけで38万円×240か月=9,120万円になります。
もしもの時のための備えとして1割の912万円をプラスすれば、約1億円が必要です。
年金不要論は危険
もっとも年金不要論を唱える人の多くがゆとりある生活をできるとは思ってないはずです。自身の状況が良くないから自暴自棄になって年金不要論を唱えてる可能性もあります。
- 諦め・失望・勉強不足→年金不要論
日本の年金制度は賦課制度なので、現役世代が納めた保険料で今の年金受給者を養っています。
現役世代が少なく、年金受給者が多ければ、当然現役世代の負担が重くなっていきます。
年金を受給してる世代は保険料をあまり納めてませんが、今の現役世代は負担した保険料を下回る年金しか受け取れないと予想されてます。
こういったことも年金不要論が出てる一因です。
平均的な老後世帯の支出については、毎月27万円程度かかるといわれています。
27万円×12カ月×20年=6,480万円 その場合は6,480万円を自分で用意しなければならないことになります。
自分でこれだけの金額を用意できる人は、そう多くはありません。 制度としては欠陥が多い年金ですが、老後を生きる日本人には必要な制度といえます。
- 現在の年金制度→現役世代が年金受給者の年金を稼ぐ
- 現役世代の保険料→年金受給者の年金へ
- 今の現役世代→負担した保険料を下回る年金
- 人口減少時代→現役世代が損する
- 年金ある→老後資金が少なくてよい
老後を支える収入と支出の考え方

定年を迎えて再就職した場合、一般的に収入は減るといわれています。
収入だけでは不足するマイナス分は、それまでに貯めた老後資金で補うことになります。
ちなみに社会保険料の金額と納めた期間は一人一人違うので、受け取る年金額も一人一人違います。年金の受給権があるからといって安心できません。
老後の主な収入
将来の年金はある程度の年齢に達してれば、年金定期便やねんきんネットから分かります。
老後に不足する金額は、老後の収入からかかる費用を控除して、それに定年後の余命を考慮して求めます。
- (老後の収入-老後の支出)×余命(年数)=老後に必要な資金
必要な老後資金は一人一人違うので、ここでは平均値を使って説明します。
老後の収入の柱となるのは国民年金、厚生年金といった公的年金です。それに加えて企業年金や個人年金があればそれも収入です。老後も再就職して働く場合は、それも老後の収入になります。
◎老後の収入
- 公的年金(国民年金、厚生年金)
- 企業年金(確定給付企業年金、厚生年金基金、確定拠出年金、退職等年金給付など)
- 個人年金(iDeCo、付加年金、国民年金基金、個人年金保険など)
- 再就職後の収入
- その他の収入(運用収入、副業収入など)
老後の主な支出

総務省が公表してる有名なデータに無職の高齢者夫婦世帯の平均があります。
これを見ると高齢者夫婦世帯の支出の平均は約26万円となっています。生命保険文化センターの調査では最低日常生活費は20~25万円必要という結果です。
まあ、平均的な老後世帯では25万円くらいは必要ということでしょう。さらに、ゆとりある生活をしたいなら約37万円が毎月必要とされています。
上記の数値は生活費だけなので、自動車の買い替えや旅行費、家のリフォームは別途必要です。賃貸の人は毎月の賃料も必要になります。
ライフイベントの費用
- 家のリフォーム 100万~1000万円
- 旅行 数万~20万円(海外旅行30万~100万円?)
- 車の買い替え 100~500万円(中古車、新車にもよる)
- 葬儀費用(100万~200万円)
老後の支出
- 生活費(食費、水道光熱費、衣服費、交通費、交際費、娯楽費、通信費など)
- 家の費用(管理費、修繕積立金、月あたり固定資産税など)
- 自動車の維持費(ガソリン代、駐車場代、保険、税金)
- 社会保険料(国民年金、国民健康保険、介護保険など)
- 保険料(医療保険、生命保険、損害保険など)
- 税金(所得税、住民税)
- その他の支出
老後資金の簡易計算式
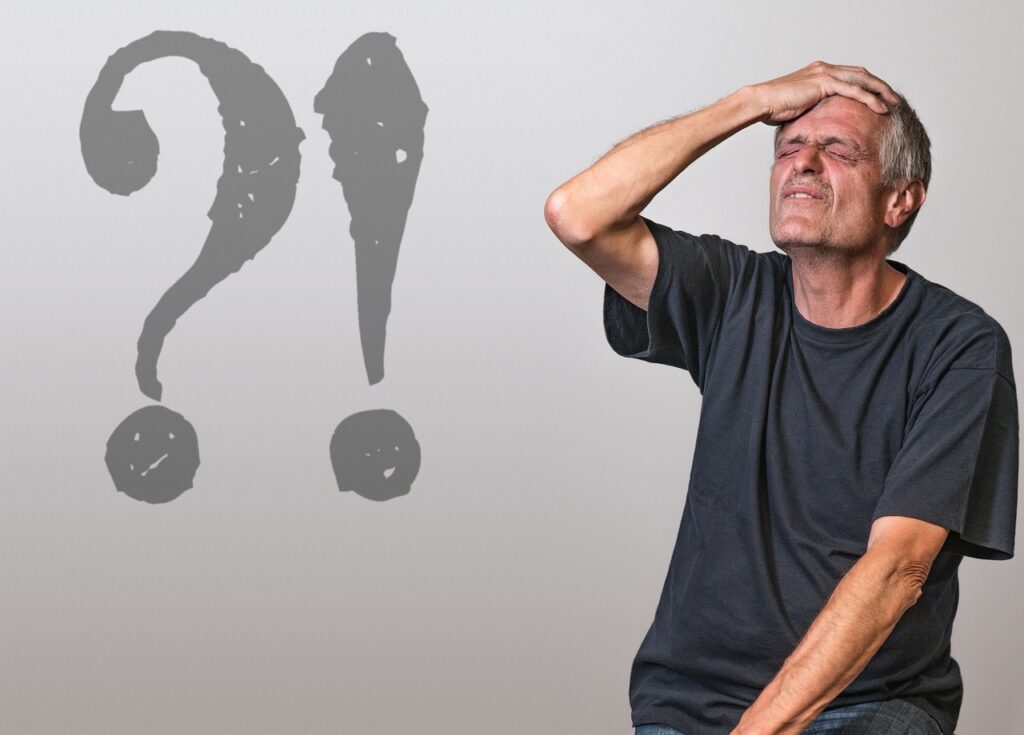
基本式
- (老後の収入 − 老後の支出)× 余命
平均余命というのは、現在〇歳の人があと何年生きるかの平均をいいます。
簡易生命表には65歳からの平均余命は男性で約20年、女性で約25年なので、長生きに備えてプラス5年の95歳までとします。
つまり95歳から定年の65歳を引いた30年分は最低でも老後に不足する老後資金として用意したほうがいいでしょう。人生100年時代なので40年で見ておく方がいいかもしれません。
平均ケースでの試算
65歳以上夫婦世帯の平均の年金収入が約22万円、平均の支出が26万円なので、毎月4万円が不足することになります。
- (22万円-26万円)×12カ月×30年=△1440万円
インフレ等で物価が上昇した場合や年齢を重ねるごとにかかる医療費を考える必要もあります。
加えて増税、保険料増加、医療負担増加を考えると2000万円はないと心許ないかもしれません。とはいえ考え過ぎたらキリがないので、その都度修正していくしかありません。
老後の生活を考える上では投資知識や投資スキルがあるとかなり有利です。
まとめ|リタイアメントプランニングの本質
- 定年して再就職すると収入が減ることが多い
- 老後に不足する分は、それまでに貯めた老後資金で補う
- 老後資金の積み立ての正解は一人一人違う
- 高齢夫婦無職世帯の平均の年金額は月約22万円(厚生年金受給者平均14万5千円)
- 高齢夫婦無職世帯の平均支出は月約26万円
- 賃貸の人は家賃もかかる
- 投資知識・スキルは必須の時代
- 定年制を廃止する企業も増えている
参考 2023年 統計局 家計調査報告 お葬式に関する全国調査
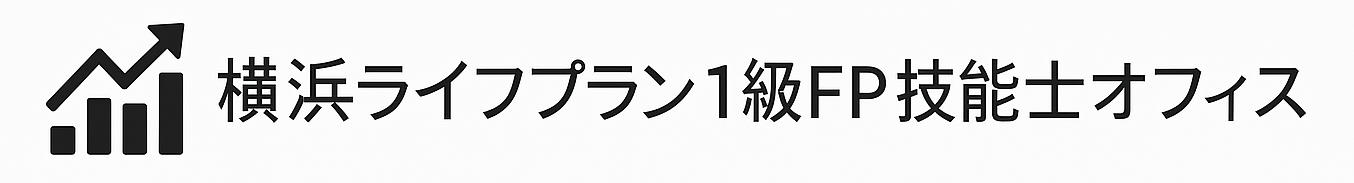

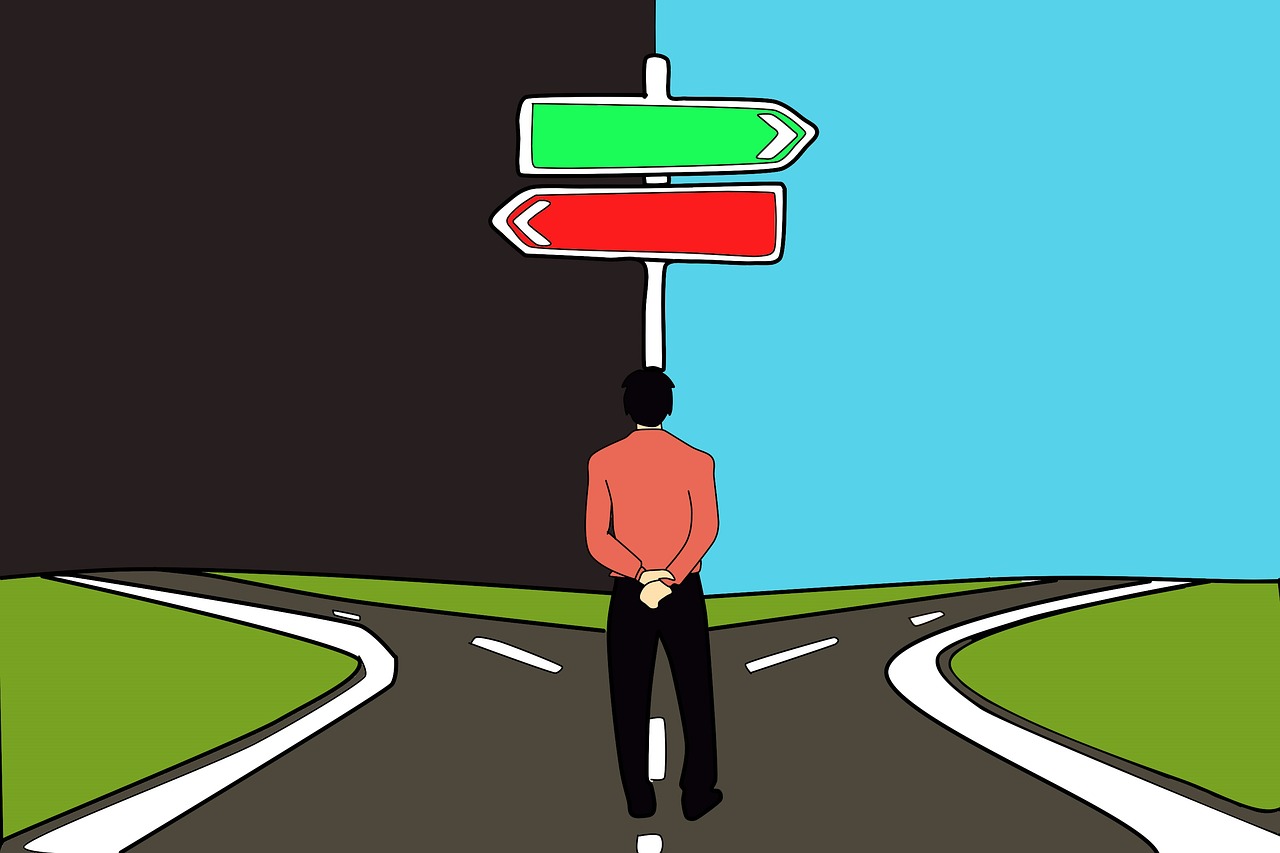


コメント Comments
コメント一覧
コメントはありません。
トラックバックURL
https://yokohama-lifeplan.com/money/money-needed-for-retirement/trackback/