60歳からの継続雇用制度を導入する企業が増え、2015年現在では70歳以上でも働ける企業が2割に達するまでになりました。
日本は将来的に人手不足になることが予想されてるので、それを見越して定年制を撤廃する動きが大手を中心に出ています。
ある歳から何年間生きるかの平均を平均余命といいますが、65歳からの平均余命は現在男性で約19年、女性で約24年となっています。
定年退職した後、働かずに生活していくのであれば、平均余命以上の年数分の生活資金がないと安心できません。
これはあくまでも平均の余命なので、老後のライフプランを考えるうえでは、余裕をもって多めに生きると仮定しておく必要があります。
夫婦二人の老後には毎月30万円の生活費がかかる?

総務省が公表している2014年の家計調査によると、老後夫婦二人世帯の平均生活費は毎月26~27万円かかるそうです。
今は26~27万円ですが、これから先インフレや増税があれば平均生活費はもっとかかる可能性もあります。
仮に必要な生活費が将来も変わらないとしても、30年間で必要な金額は単純計算でも9,360~9,720万円になります。
27万円×30年×12ヶ月=9,720万円
20年間でも6,240万円が必要になります。
となると人生100年時代に65歳で引退するのはリスクを背負うことになります。
といっても日本では国民皆年金制度を採っているので、ほとんどの人は公的年金が受けられます。
しかし、仮に65歳から年金の平均額が受け取れるとしても、2000万円が不足するといわれています。
老後世帯の老後の収入不足額の平均額は6万~7万円といわれており、30年間では2,160~2,520万円が必要になる計算です。
- -7万円×12か月×30年間=マイナス2,520万円
不足する場合は、生活水準を見直すなり下げるなりしなければ、早く老後資金が無くなることになります。
老後資金が不足する場合を回避する簡単な方法は、働き続けることです。
能力や知識を活かして独立する人もいます。
配当所得や不動産所得といった不労所得もあった方が安心できます。
老後を支える年金(国民年金の額)
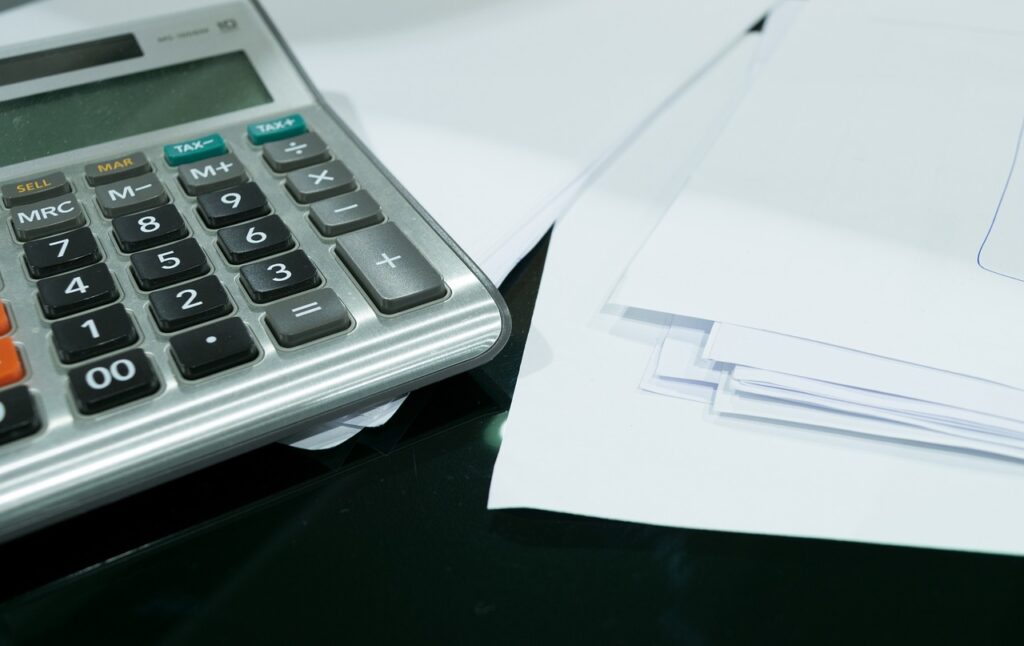
強制加入の公的年金には、国民年金と厚生年金があります。
自営業者も会社員も専業主婦も、基本的にすべての国民が対象となるのが国民年金制度です。
厚生年金は、会社員や公務員が主な対象となり、自営業者の人は被保険者になれません。
自営業者の期間が長ければ長いほど国民年金だけに加入することになりますから、自営業が長い人ほど老後の年金は少ないです。
気になる国民年金の額は、満額で780,100円となります。
この金額は毎年物価変動とか賃金を加味して修正されますが、だいたいこんな感じの金額です。
この金額は年間なので、月々に換算するとだいたい月65,000円といったところです。
未納の期間がある場合は、国民年金の額が1か月あたり1,625円ほど少なくなっていきます。
会社員の期間がある人は、国民年金にプラスして厚生年金の分がプラスされます。
国民年金は、決して大きな金額ではないかもしれませんが、老後の生活を支える重要な収入源です。
老後を支える厚生年金の額
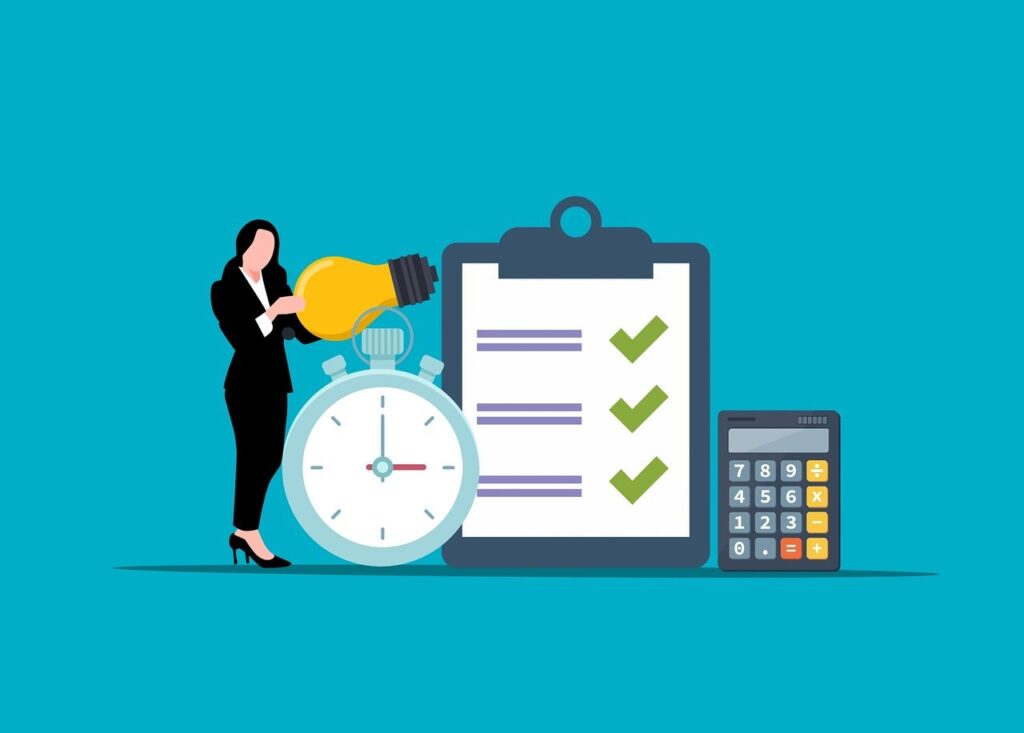
厚生年金では、被保険者の報酬と加入月数によって年金額が異なります。
厚生年金は、平成15年3月までと平成15年4月からとでは計算方法が違います。
平成15年3月までは、年金の計算に賞与は含めませんでしたが、平成15年4月からは賞与を含める総報酬制になっています。
したがって、平成15年3月までと4月からとでは、年金計算で使う乗率も違うので、平成15年3月からと4月からとは分けて計算します。
平成15年4月以降の給与と加入期間を参考にまとめてみました。数値はそれぞれ平均報酬額と厚生年金加入期間。
| 平均報酬 \ 加入期間 | 10年 | 20年 | 30年 | 40年 |
| 20万円 | 13万円 | 26万円 | 39万円 | 53万円 |
| 30万円 | 20万円 | 39万円 | 59万円 | 79万円 |
| 40万円 | 26万円 | 53万円 | 79万円 | 105万円 |
| 50万円 | 33万円 | 66万円 | 99万円 | 131万円 |
| 60万円 | 39万円 | 79万円 | 118万円 | 158万円 |
例えば、20歳から60歳まで会社員として働いた人で、その40年間の報酬の月の平均が40万円だとしたら、厚生年金は105万円ということになり、合わせて国民年金の満額78万円を受け取れます。
60歳後も会社員として働くのであれば、国民年金は増えません(20歳から60歳までが対象)が、厚生年金の年金はさらに上乗せされていくことになります。
マクロ経済スライド

今年からマクロ経済スライドが導入され、一時期は大きくメディアでも取り上げられました。
年金制度では、始めて年金を受け取るような人は手取り賃金の伸びを反映して年金が計算され、その後は物価の伸びによって年金が改定されるようになっています。
マクロ経済スライドの期間は、年金の改定に加えて、さらに年金受給者を支える公的年金の被保険者数や、平均余命の伸びを加味することで、本来の年金額の伸びを抑えます。
マクロ経済スライドでの年金水準の目標とされているのは、現役世代の平均手取り賃金の50%を上回る水準を維持することです。
現役世代の半分しかないので、住宅ローンを支払ってると、旅行をして、おいしいもの食べてといった希望を実現するのは難しくなります。
若い頃に学んでおけばよかったことの1位は資産運用

高齢者を対象にした「若いころに学んでおけばよかったこと」というアンケートが某雑誌で実施されていました。
1位は英語かなと思いながらアンケート結果を見たら、意外にも1位は資産運用でした。
ちなみに、1位と予想した英語は2位でした。
証券会社が実施しているアンケートだったので、こういった情報はあくまでも参考程度にとどめておくのがいいのですが、証券会社主催の資産運用をテーマにしたセミナーは実際盛況のようです。
今現在、年金を受給している人が若かった頃とは経済環境が大きく異なりました。
まず、年金制度が大きく様変わりしており、インフレ経済からデフレ経済へと変わりました。
ところが今度はインフレに変わりつつあるようで、物価の上昇が目立つようになってきました。
確定拠出金やNISA等を政府が奨励しているように、今までのように銀行に預けておけばいいという時代は終わり、運用結果が老後生活を決めることになる可能性が高くなってきました。
10年前は1グラム1,500円から1,700円程度だった金は今では4,000円~5000円になっています。
大学生時代に勧められるまま20万円で購入した金のネックレスは、今売ったら80万円以上になるといわれました。
現役世代は、資産を形成する時代といわれています。
といってもリスクのある物に投資しろといっているわけではありません。
目標を作ってコツコツと実践するだけでも違います
おわりに
65歳に引退して30年生きるなら老後資金として1億円必要かもしれませんが、実際は公的年金があるのでそんなにかかりません。
加えて現役時代から金融や不動産に投資してきた人はもっと少なくなります。といってもその後の生活や働き方でも違ってきます。
老後資金を貯めても使わずに相続税でがっぽりもっていかれる人が多いそうです。
でも、原資は多いほうが同じ利回りでも受け取れる金額は大きくなりますし、仕方ないところもあると思います。



コメント