「突然の入院で医療費が20万円を超えてしまった……。」
こういった経験をすると「こんなに払わなければいけないのか」「やっぱ医療保険はいらないと怖いな」と不安になるかもしれません。
しかし、実は日本には医療費が高額になった場合に自己負担を軽減してくれる高額療養費制度があります。
たとえば年収500万円の人なら、1ヶ月にかかる自己負担は9万円程度です。つまり支払った20万円のうち10万円以上が戻ってくる可能性があるわけです。
知らなければ損をするかもしれない高額療養費制度について解説します。
目次[閉じる]
高額療養費制度とは

健康保険に加入してる人が病院で治療を受けると窓口での負担が一部で済みます。
これは健康保険に加入してるので病院での自己負担が一定額に抑えられるからです。
このように健康保険の被保険者は、病気になった時に備えて健康保険に加入しています。日本は国民皆保険制なので、国内に住む人は何らかの医療保険(健康保険、後期高齢者医療、国民健康保険など)に強制加入していることになります。
健康保険に加入している人が受けられる給付
健康保険では、一つの月に被保険者や被扶養者が払った一部負担金(治療費等)の自己負担が高額になった時は、負担軽減が受けられることがあります。
いわゆる高額療養費制度といわれるものです。
高額療養費制度を知らないと損をする理由
この高額医療費制度を知っておくと無駄な保険に加入しなくて済むことになり、むしろ知らないと損することになります。
健康保険では、同一の月に被保険者や被扶養者の払った治療費等の自己負担額が高額(健康保険法では著しく高額という)になると、一定の自己負担限度額を超えた部分が支給(払い戻される)されます。
自己負担限度額は収入によって決まっており、その額を超えた場合に対象になります。
自己負担の上限を超えた場合に申請をすれば高額療養費として払い戻されるので、一時的に被保険者が負担することになります。
高額療養費の支給要件
法律では療養給付、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、介護療養費、家族訪問看護療養費といった専門用語が並んでますが、病院で支払う医療費のことです。
対象となる医療費の範囲
高額療養費は、被保険者だけでなく、被扶養者(その人に養われてる家族)も対象です。
高額療養費は月単位で計算される
重要なのは医療費は同じ月で自己負担を見るということ(月単位)です。1年を合算するとかではありません。
また、自己負担の上限は被保険者の収入によって異なります。
高額療養費の自己負担限度額はいくらか

現役並み所得者の自己負担限度額
| 年収の目安 | 上限額 |
| 約1,160万円~ | 25万2,600円+(医療費-84万2,000円)×1%(多数回該当14万100円) |
| 約770万円~1160万円 | 16万7,400円+(医療費-55万8,000円)×1%(多数回該当9万3,000円) |
| 約370万円~770万円 | 8万100円+(医療費-26万7,000円)×1%(多数回該当4万4,400円) |
上記の医療費というのは一部負担の額ではなく、10割の額をいいます。例えば、窓口で3割負担で3万円なら医療費は10万円といったようにです。
したがって年収が400万円の人なら、上の表からその月の医療費はだいたい9万円以下で済みます。
多数回該当とは何か
多数回該当とは、療養を受けた月までの1年間で高額療養費の支給を4回以上受けた場合です。
400万円の人なら、その月の医療費は4万4,400円が上限となります。
このように高額療養費では月単位でみます。
一般所得者の自己負担限度額
一般の人とは、年収が約156万円~370万円の人をいいます。
| 年収の目安 | 70歳未満 | 70歳以上(外来・個人ごと) | 70歳以上(世帯全員) |
| 約156万円~370万円 | 5万7,600円(多数回該当4万4,400円) | 1万8,000円(年間上限14万4,000円) | 5万7,600円(多数回該当4万4,400円) |
低所得者(住民税非課税世帯)の自己負担限度額
低所得者とは住民税が非課税の世帯をいいます。
| 年収の目安 | 70歳未満 | 70歳以上(外来・個人ごと) | 70歳以上(世帯全員) |
| 住民税非課税世帯・年金収入80万円以下 | 3万5,400円(多数回該当2万4,600円) | 8,000円 | 住民税非課税世帯2万4,600円 年金収入80万円以下1万5,000円 |
健康保険は強制加入が原則

健康保険は医療費リスクへの土台
健康保険は適用要件に該当したら強制加入が原則です。
それゆえ、これは生命保険を考える際の土台となる制度といえます。つまり、健康保険が強制加入であること及び高額療養費制度があることから、何かあった時の保障を全て健康保険で賄わなくてよいことになります。
高額療養費制度を前提に保険を考える重要性
健康保険制度が強制加入であること及び高額療養費制度があることを知らなければ、無駄な生命保険に加入することになります。
加えて健康保険だけでなく社会保険は原則として申請しなければ給付を受け取れないことを知っておくとよいでしょう。
同じ収入の人が、同じ治療を受けて同じ額の医療費がかかったのに、ある人は数万円の払い戻しが受けられて、別の人は1円も受け取れない、そう考えると恐ろしいですね。
限度額適用認定制度を使えば窓口負担を抑えられる

限度額適用認定制度とは
高額療養費の申請をしても、金額が払い戻されるのは数か月先ですが、限度額適用認定制度を利用することで、医療機関ごとの窓口支払いを高額療養費の自己負担限度額までに抑えることができます。
あらかじめ限度額適用認定証、限度額適用認定・標準負担限度額認定証の交付を受けておくことで、窓口での支払いを自己負担上限額までに抑えることができます。
限度額適用認定・標準負担限度額認定証は、低所得者の方が対象です。
限度額適用認定証の申請方法
窓口で事前に交付を受けた限度額適用認定証を提示することで、自己負担限度額までに抑えられるので高額療養費の申請が不要になります。
◎健康保険限度額適用認定申請書

健康保険以外の医療保険にも高額療養費制度はあります。
申請方法は保険者がどこなのかによって違います。自分がどの医療保険の被保険者になっているかが分かれば、保険者のサイトで確認できます。
まとめ|高額療養費制度を知って医療費の不安を減らす
- 健康保険は強制加入が原則
- 会社員は健康保険組合または健康保険協会、自営業者は国民健康保険に加入する
- 健康保険に加入してるから窓口での負担が一定額に抑えられている
- 1か月の医療費が高額になった場合は高額療養費で払い戻しされる
- 高額療養費は月単位で計算する
- 1か月の医療費の上限は収入によって違う
- 限度額適用認定証があれば窓口での負担を限度額までで済ませられる
- 多数回該当だと上限額が引き下げられる
参考 厚生労働省 高額療養費を利用されるみなさまへ
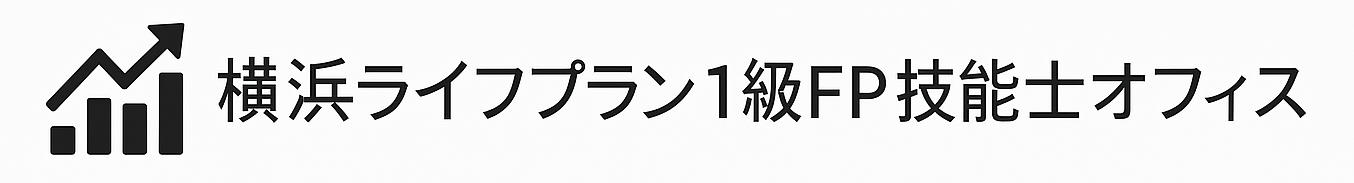



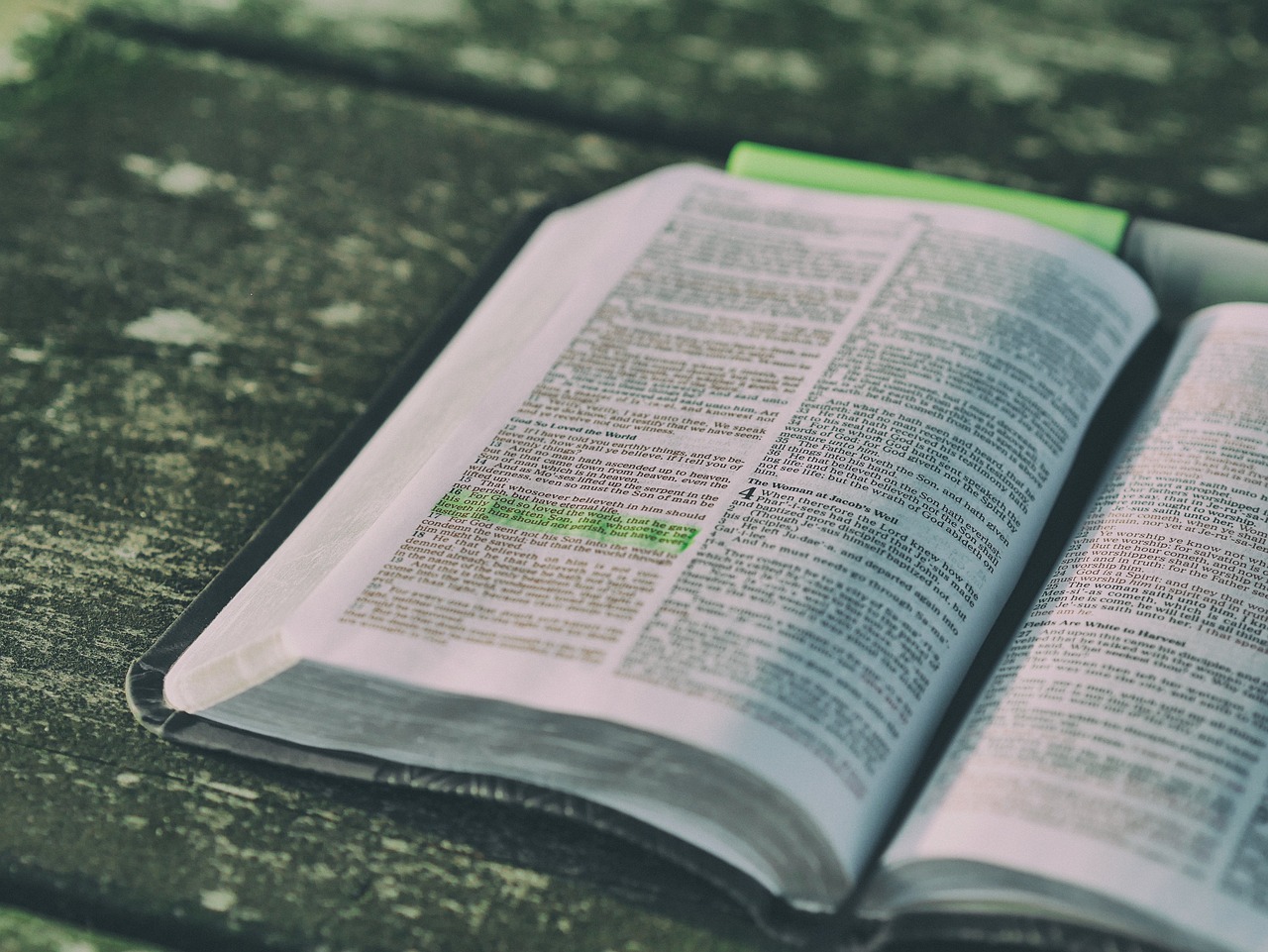
コメント Comments
コメント一覧
コメントはありません。
トラックバックURL
https://yokohama-lifeplan.com/money/kougakuryouyouhi/trackback/