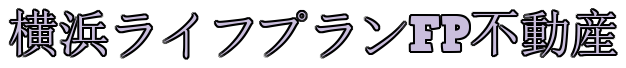仕事柄、不動産協会とファイナンシャルプランナーの勉強会に参加しますが、最近は相続がらみの内容が多いです。
現在の日本は、4人に1人以上が高齢者(65歳以上)といわれており、今後も高齢者の割合は増加していくと予想されています。
国立社会保障・人口問題研究所の研究によると、今から40年後の日本は、高齢者が4割近くにもなると予測されてます。
そのような超高齢社会では、相続の問題は他人ごとではありません。
相続税がかかる相続より、相続税がかからない相続の方がもめる確率が多いのは、何も対策をしなかったからだといわれています。
4つの相続対策

相続対策には今の生活を大きく変えずに、残される人にとって有利な設計となるような対策を立てるポイントがあります。
相続対策には大きく分けて4つあるといわれています。
①遺族がもめないための遺産分割対策、②相続税をどうやって捻出するかの納税対策、③相続税を抑えるための節税対策、④相続対策を考えつつ被相続人の老後が立ちゆくような老後対策の4つです。
今の生活を大きく変えなければいけない相続対策では本末転倒なので、一般的な相続対策では、今の生活のまま資産の組み換えを行います。
相続対策
- 遺産分割対策
- 相続税の納税対策
- 節税対策
- 事業承継対策
遺産分割対策
遺産分割対策では、誰がどの財産を相続するかの対策をします。
相続財産に不動産がある場合、不動産の価格の判断が不透明で誰もが納得できる金額にはなりにくいため、もめる相続になりやすいです。その点、現金であればだれもが納得できます。
遺産分割の観点からは、不動産よりも現金の方がスムーズに進みます。
納税対策
納税対策では、税金をどうすればスムーズに納税できるかを考えます。
相続する財産が不動産や上場していない株式だと、現金化に時間がかかります。
相続財産が不動産や上場していない株式の場合は、相続した後に相続税の支払いをスムーズにできる対策を取っておきます。
節税対策
節税対策は、相続したら納付することになる相続税を、合法的に少なくなるための対策です。
生前から財産を移転したり、財産の組み換えを行って評価額を下げる方法があります。
評価額が低ければ、相続税も低くなるからです。
事業承継対策
事業承継対策では、事業に関する株式や財産を処分できないことを前提に行います。
事業の後継者へ引き継ぐためには、その会社の株式を取得させる必要もあります。
適当な後継者がいない場合は、事業で働く従業員や取引先を考慮して承継させるかどうかの判断も必要になってきます。
法律上の相続人は誰になる?

民法によって決められた、被相続人(死亡した人)の財産を相続することができる人を法定相続人といいます。
法定相続人には、順位があり、血族関係者の構成次第で父母が相続できることがあれば、できないこともあります。
順位があるので、生前仲が良かったといっても必ずしも財産を相続できるとは限らないのです。
配偶者
配偶者とは、婚姻届けをした関係にある夫または妻のことをいいます。
配偶者は、必ず相続人になります。内縁関係だと相続権がありません。
配偶者は必ず相続人となりますが、子、直系尊属、兄弟姉妹のだれが一方の相続人となるかで法律上の相続分が異なります。
相続人の順位
妻は必ず相続人なので、相続人の順位とは、妻を除いた相続人となれる優先順位のことです。
1.子
子がいる場合は、子が第1順位で相続人となります。
子が複数いる場合は、均等に分割されます。
以前は、嫡出子と非嫡出子による差がありましたが、違憲の判決がされ、今は嫡出子も非嫡出子も同じ分割分になりました。
嫡出子とは、婚姻関係にある夫婦の間に生まれた子をいいます。
養子も子と同じ扱いです。ただし、養子に縁組より前に出生した子がいる場合は代襲相続ができないとされています。
2.直系尊属
直系尊属とは、被相続人からさかのぼった血族をいいます。
両親、祖父母、曽祖父母、高祖父母・・・です。
第1順位の相続人である子がいない場合は、被相続人の父母が相続人となります。
父母がいない場合は、祖父母が相続人になります。
3.兄弟姉妹
第1順位の子と第2順位の直系尊属がいない場合は、兄弟姉妹が第3順位者として相続人になります。
つい最近もテレビで「子供のいない夫婦がいて、夫が亡くなったと思ったら、今まで音信不通の夫の兄弟が遺産を請求しにきた」という話が放映されてましたが、それがこのケースです。
たとえ音信不通でも法律上は兄弟姉妹も法定相続人です。
法定相続分とは

配偶者は常に相続人になり、子がいるときは直系尊属と兄弟姉妹は相続分がなく、子がいないで直系尊属がいるときは兄弟姉妹に相続分はありません。
どの順位者が相続人になるかで法定相続分の割合も違います。直系尊属は近い親等が優先します。
1.子の場合
配偶者と子の場合はそれぞれ1/2ずつ相続します。
子が複数いる場合は、1/2をさらに均等で相続します。
配偶者がおらず、子のみの場合は子がすべてを相続します。
2.直系尊属の場合
子がおらず、配偶者と直系尊属とが相続人となる場合は配偶者が2/3、直系尊属が1/3の財産を相続します。
配偶者も子もいない場合は、直系尊属がすべてを相続します。
3.兄弟姉妹の場合
兄弟姉妹は、子と直系尊属がいない場合に相続人となることができます。
配偶者と兄弟姉妹がいる場合の相続割合は、配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4となります。
配偶者、子、直系尊属がいない場合は、兄弟姉妹がすべてを相続します。
ちなみに兄弟姉妹は廃除できませんが、遺留分がありません。このことから遺言が大事ということが分かります。
相続税の基礎控除

以前の相続税の基礎控除は、5,000万円に法定相続人数に1000万円をかけた分でしたが、今は以前の6割になりました。
相続税の基礎控除が引き下げられるまでは、相続税が課税される対象は100人に4人程度といわれていましたが、基礎控除引き下げの導入で課税の対象は100人に8人まであがったそうです。
現在の相続税の基礎控除額は、3000万円と法定相続人数に600万円を乗じたものを足した額になります。
課税価格の合計から控除した金額が課税される遺産の総額になります。
課税価格の合計額 - 基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)= 課税遺産総額
日本の相続税を知った外国人は、「日本ではとてもではないが相続できない」と口をそろえていうそうです。
相続の承認・放棄

相続は承認だけでなく、放棄もあります。
相続はプラスの財産だけでなく、マイナスの財産(借金)も承継しますが放棄できます。
財産の範囲で債務や遺贈を弁済する限定承認というのもあります。
相続の承認、放棄は、相続人が自己のために相続があったことを知った時から3ヶ月以内にしなければなりません。
以下の事由では、単純承認したものとみなされます。
・相続財産の全部または一部を処分した
・3ヶ月以内意思表示をしなかった
・相続人が限定承認・放棄をしたとしても、①相続財産を隠匿した、②ひそかに消費した、③悪意で財産目録に記載しなかった
まとめ
・相続税には基礎控除がある
・相続対策は税金対策のことだけではない
・相続対策には、遺産分割対策、税金対策、老後対策等と様々ある
・相続税がかからなくても相続が原因でトラブルに発展しているケースは多い
・法律上の相続人には優先順位がある。
・法律で相続分が決まっている
・必ずしも法律に従わなければいけないわけではない