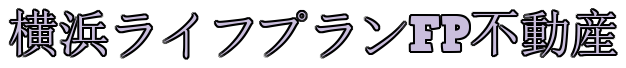将来の夢や希望を思い描き、その夢や希望を達成するための計画をライフプランと言います。
そして、ライフプランを金融・経済知識を使って具体的に実現する計画をファイナンシャルプランニングといいます。
ファイナンシャルプランニングには、金融商品、不動産特有の制度、住宅ローン、年金制度、保険商品、教育資金、相続制度などの幅広い知識が必要ですが、この幅広い知識を持つファイナンシャルプランニングの専門家がファイナンシャルプランナーです。
このライフプランを立てることで住宅ローンのリスクを見える化することができます。
ライフプランとファイナンシャル・プランニング

ライフプランというのは、「30歳までにマイホームを購入する」「子供の大学進学まで教育資金を工面する」「老後は田舎で暮らす」といった将来希望する計画です。
人生設計と同じような意味ですが、ファイナンシャルプランニングを前提とする際にライフプランといわれることが多いようです。
ライフプランを立てても具体的な方法がなければ達成は難しいです。
ライフプランを達成するために、金融・経済知識の知識を駆使して計画したものがファイナンシャル・プランニングです。
ファイナンシャル・プランニングの計画には、金融商品、投資方法、不動産、住宅ローン、税金制度、相続制度、社会保険制度、教育資金などの知識が必要です。
例えば、老後資金の計画を立てる際に目標とする老後資金も、年金制度や年金額が分からなければ、目標の立てようがありません。
そういった場合は、現状を理解したうえで、いつまでにいくら必要かを明確にし、いくつかの選択肢から選んだ方法を実行していきます。
それが積立投資なのかNISAなのか不動産投資なのかは、各個人によって異なります。
ファイナンシャルプランニングの主役は、あくまでも各個人であり、その人の考えを尊重する必要があるからです。
FPは幅ひろい知識で相談に対応!誰に相談すればいいかにもアドバイス
今までは、不動産の購入については不動産会社、住宅ローンの相談は不動産会社や銀行、相続に関する相談は弁護士や税理士、資産運用であれば証券会社、生命保険は保険会社といったように、相談事にそれぞれの専門家に相談することが当たり前でした。
しかし、これらのことは全てお金に関する問題です。
ライフプランを通してキャッシュフローを立ててみることで、その人のお金に関する問題の全体を把握できます。
どれかに偏ってしまうと他の事にお金を回せなくなってしまうので、全体のバランスを見るわけです。
また、ファイナンシャルプランナーは、お金に関する専門家といわれるように、どの専門家に任せればいいのか迷うようなときでも、取りあえずファイナンシャルプランナーへ相談すれば相談内容に合わせて専門家をコーディネートしてくれます。
そのため、ファイナンシャルプランナーは、各種専門家のまとめ役といった側面もあります。
ファイナンシャルプランナーの中には、税理士、社会保険労務士、証券会社社員、保険外務員といった他の専門職と兼業している人も多いです。
ライフプランを立てることがなぜ住宅ローンのリスクを減らすことにつながるのか

住宅ローン、教育資金、老後資金についてそれぞれ独立したものとして捉えてしまうと、住宅ローンに関するリスクが毎月の住宅ローン返済額のみをもって判断してしまうことになります。
同じ年収でも子どもが2人いる家庭とそうでない家庭とでは家計の状況が違うように、無理なく返せる住宅ローンも家庭ごとに違います。
住宅ローンの選択を毎月の返済額のみで判断してしまうと、せっかく購入したマイホームを失うことにもなりかねません。
任意売却ではマイホームを失う人を対象にしますが、破綻する人のほとんどは無理な住宅ローンを組んでいます。
お客様の中には、「年収が少ないから家を買えない」とか「住宅ローンは年収の〇倍までなら安心」といった考えをお持ちの人がいます。
しかし、年収が少なくても家は買えますし、年収の6倍、7倍以下に住宅ローン返済額を抑えても破産する人はいます。
重要なのは年収の多い少ないでも年収の〇倍以下に抑えることでもなく、将来も無理なく返済していける金額であることです。
ライフプランを立てることが、どうして将来のリスクを減らすことにつながるかというと、ライフプランを立てることによって20年、30年後のお金の流れが分かるからです。
例え現在、40万円の収入で家計が賄えていたとしても、子供が成長するにしたがって毎年の教育費は増えます。
退職後の年金は現在の収入よりも下がりますので、現在の年収だけを見ていては将来のリスクに対応できません。
年収が将来どうなるかはハッキリとは分かりませんが、住宅ローンの残り金額と将来の年金額にはルールがあります。
20年、30年後の将来をざっくりとでも知っておくことは、将来のリスクだけでなく、不安の解消にもなります。ライフプランを立てたことがある人は、立てたことがない人よりも不安が少ないというデータもあります。

住宅ローンでライフプランを立てるメリット
- 返済に無理がないか判断できる
- 頭金をいくらにするか判断しやすい
- 借入額をいくらにすると無難か分かる
- 住宅ローン以外のリスクを知る機会になる
- 問題点が分かる→改善に向けて動ける
デメリット
- キャッシュフロー表を作るのが面倒くさい
- 作成に必要な資料集めが面倒くさい
- 考えるのが面倒くさい
これからの住宅購入は将来のリスクも考える

日本は、平成25年に65歳以上が4人に1人以上となり、日本の高齢率は25%を超えました。
現在の国民年金、厚生年金の老齢年金の開始年齢は原則として65歳からとなっています。つまり、3人の現役世代で1人の年金受給者の生活を支えていることになります。
「LIFE SHIFT」の著者によれば、2007年に生まれた子の半数が100歳を超えるまで長生きするそうです。また、著者はこうした人生100年時代では、80歳を超えて働く必要があるとも語ってます。
長生きすることで多くの人が恐れるのが老後資金の枯渇です。これは長く働きつつ、投資に挑戦したり、制度(iDeCo、NISAなど)を活用することで解消できます。
よく持家か賃貸かが雑誌やネットで議論されてますが、それぞれにメリットとデメリットがあるので一概には言えません。
ただ、人生100年時代が到来するとなると、毎月の賃料を年金だけで支払い続けるのは難しいです。
一生賃貸というのであれば、賃料の安い田舎に引っ越すか、交通の便が悪い・4階まで階段の団地などがおすすめです(賃料が安い)。
そうでなければ、持家の人よりも多くの老後資金を準備する必要があります。
持家は購入後の維持費も考慮
持家にする場合に悩むのが、マンションと一戸建てのどちらにするかです。
持家にした場合も、住宅ローンを支払い終わったからといって維持費がゼロになるわけではありません。
持家にした場合は、固定資産税がかかりますし、マンションであれば管理費と修繕積立金もかかります。
一戸建てであっても建物自体は老朽化していくので、自主的に修繕用に積立しておくことが必要です。
あらかじめ金額が分かればライフプランに落とし込むこともできます。
キャッシュフローの作成
キャッシュフロー表を作成すると、可処分所得、支出、年間収支について情報を整理できます。
●家族構成
| 夫 | 36歳 | 会社員 |
| 妻 | 32歳 | パート |
| 長男 | 4歳 | 幼稚園 |
| 長女 | 2歳 | 未就園児 |
●可処分所得
| 夫 | 年収550万円→可処分所得450万円 |
| 妻 | 年収50万円→可処分所得40万円 |
●支出
| 基本生活費 | 220万円 |
| 住居関係 | 200万円 |
| 教育費 | 30万円 |
| 生命保険 | 22万円 |
| 車両費 | 30万円 |
| その他 | 10万円 |
| 一時支出(車) | 6年ごとに250万円 |
●キャッシュフロー表(夫収入2%・基本生活費2%)

年間収支がマイナスが続くので、貯蓄の取り崩しが必要になる→改善が必要
住宅を購入したい(5年後)→シミュレーションを立てる(副業して3万円を積立てる)→リスクが減る(頭金200万円)
おわりに
キャッシュフロー表をFPに作成してもらうメリットは、手間もそうですが、何より解決策や専門家の意見が聞けることです。
実際にFPに相談すると、1時間で5,000円から10,000円の相談料が相場です。そして、キャッシュフロー表を作成してもらうと、3万円から10万円くらいが作成料としてかかります。
占い師や話聞き(愚痴や話を聞くだけの人)に相談しても1時間で5,000円から数万円なのを考えれば、そう高くはないのでは……。
または、手間はかかっても今回のように自分でキャッシュフロー表を作成してみるのがよいでしょう。
住宅ローンを借りる前にキャッシュフロー表を作成することのメリット
・住宅ローンの検討ではキャッシュフロー表を作成するとリスク回避になる
・返済計画に無理がないか分かる
・将来のリスクと向き合える
・問題の顕在化→改善策をうてる