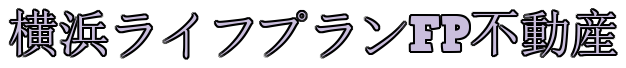「不動産はややこしい」
これは、お客さんからときどき言われる言葉です。
我々の生活には、衣食住は切り離せないものですが、そのうちの一つである住については「ややこしい」とか「難しい」と感じている人は少なくないようです。
特に不動産に関することについては、関連する法律も多く、専門用語も多いためややこしいと思います。
不動産をややこしくしている原因の一つに、同じ不動産なのに評価方法がいくつかあるということがあります。
ニュースなどで「公示価格が発表されました」とか「路線価が公表されました」といったことを聞いたことがあると思いますがこれです。
少し前に相続税対策に不動産を購入する人が増加といったニュースがありましたが、これは不動産の評価方法がいくつかあることを利用したものです。
一つの土地に五つの評価がされる?
みなさんの中には「一物五価」という言葉を聞いたことがある人がいるかもしれません。
一物とは、一つの物、つまり一つの土地のことです。
そして、五価というのは、五つの評価方法によって付けられる価格をいいます。
普段の生活で、スーパーに大根を買いに行ったとします。大根はその年の豊作や凶作、時期などによって価格が変化します。
高いと思ったら購入しないかもしれませんが、「このくらいなら……まあ、いいか」と思って購入した場合、それを「時価」といいます。
時価という時点でややこしく感じるかもしれませんが、時価というのは取引が成立した場合の価格をいいます。
値段交渉をして少し値引きしてもらった場合は、値引きしてもらった価格が時価になります。
まあ、その時の価格です。
不動産であれば、チラシでは5000万円の土地が売りに出されていても、値引き交渉の結果、取引成立額が4500万円なら、時価は4500万円ということになります。
そして、五価のうちの時価以外には、公示価格、相続税路線価、基準値標準価格、固定資産税評価額の四価があります。
公示価格
公示価格とは、国土交通省の土地鑑定委員会が、毎年1月1日の基準時点で日本各地の標準値を評価したものです。
評価したものは3月に公示されます。
公示価格は、一般の土地取引価格の指標や、公共事業用地の取得価格の算定指標として扱われます。
とはいえ、実際の不動産取引では、時価と公示価格が乖離することがよくあります。
特にバブル期では、少し前の価格を参考に評価した公示価格は、時価よりも低く評価されていることもしばしば見られます。
路線価
路線価というと、一般的には相続税路線価をいいます。
相続税路線価は、相続税法に基づいて毎年1月1日を基準日として土地を評価しています。
1月に評価された価格は7月に国税庁から発表されます。
相続税路線価は、相続税と贈与税の算定基準となる価格で、公示価格の80%を目安に設定されているといわれています。
固定資産税にも路線価があり、固定資産税の路線価も公開されています。
基準値標準価格
基準値標準価格は、毎年7月1日を基準日として、国土交通省が9月に発表します。
基準値標準価格は、価格の評価方法や目的は公示価格と同様ですが、公示価格を補完する役割があります。
公示価格は1月1日を基準日としていますが、基準値標準価格は7月1日を基準日としています。
公示価格や基準値標準価格は、不動産鑑定士という専門家が計算したものを調整して国土交通省や都道府県知事が公表します。時価とは乖離することが多いですが、土地の価格の参考になります。
固定資産税評価額
固定資産税評価額は、市町村(東京23区は都)が3年に1度評価替えを行う固定資産税の基準となる価格です。
原則として3年に1度の基準年度の前年の1月1日を価格時点として評価します。
土地の固定資産税評価額は、公示価格の70%程度が目安とされています。
公示価格の70%程度となっているように、現金で持つよりも土地で保有したほうが資産の評価額が下がります。
評価額が下がるということは、納める税金も下がるということです。
節税対策に不動産が活用されているのは、こういった理由も一つに挙げられます。
まとめ
・土地の評価方法には、時価、公示価格、路線価、基準値標準価格、固定資産税評価額など五つある。
・時価は、不動産の取引成立価格をいう。
・公示価格と基準値標準価格は、国土交通省や都道府県が公表してる土地価格の目安。
・公示価格と時価は乖離しやすい(公示価格が安い)。
・路線価は、相続税や贈与税の算定基準となる価格をいう。
・固定資産税評価額は、固定資産税の算定基準となる価格をいう。
土地の公的な価格情報については、国土交通省が運営してる不動産情報ライブラリというものもあります。
不動産情報ライブラリ https://www.reinfolib.mlit.go.jp/