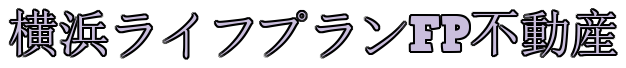住宅ローンの毎月の返済額は、借入額、金利、返済期間、返済方式によって決まります。
金利は借りる側が自由に決めることはできませんが、借入額、返済期間、返済方式は借りる側が決められます。
借入額は、購入する物件、自己資金等によって変わります。
返済期間は、10年以上にすれば住宅ローン減税の対象となります。
返済方式には、元利均等返済と元金均等返済がありますが、返済計画が立てやすい元利均等返済が多く選ばれています。
返済期間については、35年までというのが一般的ですが、最も多く設定されているのは25年~30年といわれています。
返済期間が違うことで毎月の住宅ローン返済額はどのように変わるのでしょうか。
住宅ローンの返済期間の平均は26.4年?

まず、住宅ローンの返済期間について、利用者がどれくらいに設定しているのかを見ていきます。
住宅ローンのフラット35を扱う住宅金融支援機構では、民間住宅ローンの貸出動向調査について公表しています。
「2018年 民間住宅ローンの貸出動向調査」の住宅ローンの貸出期間を見ると、2017年度の住宅ローン貸出期間の平均は26.4年でした。
住宅ローン利用者が選択した返済期間について割合でみると、30年超35年以下を選択したのは20.8%、25年超30年以下を選択したのは41.9%、20年超25年以下を選択したのは21.2%、15年超20年以下の借入期間は11.9%、10年超15年以下は3.8%でした。
2017年度は、借入期間25年超を選ぶ人が前回の調査より増加しました。
35年超と10年以下の期間が少ないのは、35年超を選ぶには長期優良住宅の認定を受けなければいけないこと、10年以下だと住宅ローン控除が使えないことが原因と思われます。
借り換えもあるので純粋に返済期間の平均とはいえませんが、繰り上げ返済や借り換えをうまく活用してる人が多いことが分かります。

フラット35 2018年 民間住宅ローンの貸出動向調査
追記
2019年の消費税増税に伴って住宅ローン控除の期間が3年延長されました。
2019年の住宅ローン控除の見直しでは、最初の10年については同じですが、11年目から13年目までは、①ローンの年末残高(4,000万円上限)の1%と、②住宅価額の2%を3年で割った額のうちの、少ない金額を所得税・住民税から控除します。
-

-
2019年度の不動産に関連する主な税改正
2019年度の税制改正が公表されましたが、今年は消費税の引き上げが予定されています。 消費税の引き下げに伴う需要変動に向けて、住宅ローン控除の拡充が図られます。 Contents 住宅ロ ...
住宅ローンの返済期間による返済額の違い

住宅ローンは原則最大で35年までです。
長期優良住宅の基準をクリアして認定された場合は50年までも可能ですが、長期優良住宅は少ないです。
一般的に住宅ローンは35年と思っておけばいいと思います。
住宅ローンは同じ金利、同じ借入金額であれば、返済期間で金額が異なります。
返済期間を短くすれば毎月の返済額は上がり、長くすれば毎月の返済額は下がります。
また、短くするほど利息の負担は減り、長いほど利息の負担は増えます。
ただし、利息を抑えるあまり返済期間を短くし過ぎて、毎月の返済が厳しくなったら意味ありません。
ここからは返済期間による金額の違いを比較してみます。
金利1%
借入額/返済期間
| 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
| 3000万円 | 137,968円 | 113,061円 | 96,491円 | 84,685円 |
| 4000万円 | 183,957円 | 150,748円 | 128,655円 | 112,914円 |
| 5000万円 | 229,947円 | 188,436円 | 160,819円 | 141,142円 |
金利2%
| 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
| 3000万円 | 151,765円 | 127,156円 | 110,885円 | 99,378円 |
| 4000万円 | 202,353円 | 169,541円 | 147,847円 | 132,505円 |
| 5000万円 | 252,941円 | 211,927円 | 184,809円 | 165,631円 |
住宅ローンの返済期間が毎月の返済額に与える影響の結果を踏まえて

以上の結果から返済期間が変わると随分と違うことが分かります。
余裕がある人であれば、返済期間を短くして早めに返済を終えさせることもできます。
反対に将来出費の予定があるとか、子供が小さいためこれから多くの出費がかかる人は、返済期間を35年、または長めにとり、無理なく返済できる計画にするのがいいと思います。
無理なく返済できる金額にして、余裕が出たときに繰り上げ返済をすることでも利息の費用は削減できます。
また、繰り上げ返済には期間短縮型と返済額軽減型とがありますが、期間短縮型の繰り上げ返済を併用してローンの返済期間を短縮させることもできます。
現在は金利が最低水準なので、多めに借りて住宅ローン控除の適用期間が終わった後、一括で返済するといったことも可能です。
住宅ローンの資金計画では、小さい子供がいる家庭では、これから先の教育費のことも合わせて一番お金が掛かる時期を乗り越えられるかがポイントとなります。
最初は長い期間の住宅ローン返済期間を設定して、余裕が出てきたら繰り上げ返済をするといった方法が一番リスクが少ないです。
どのようなプランが最適なのかは、子供が小さいとか、退職までに完済したいのか、資産がどれだけあるか等によっても違ってきます。
つまり住宅ローンの資金計画は、家庭の状況に応じたオーダーメイドで立てる必要があります。
住宅ローン控除について

住宅ローンを借りる人は、住宅ローン控除も利用すると思います。
住宅ローン控除は所得税の税額控除で、配偶者控除のような所得控除とは効果が違います。
税額控除は納めた税金に直接関わるので効果が大きいです。
住宅ローン控除を使うためには、住宅ローンの返済期間が10年以上という要件を満たさなければなりません。
10年以内の返済期間だと要件を満たさないので利用できません。
また、最初は要件を満たしていても、住宅ローンの繰り上げ返済で期間が短くなり、当初からの借入期間が10年以内になってしまうと、その後は適用されなくなってしまいます。
住宅ローン控除の適用を受けるには、控除を受ける最初の年に、確定申告に必要書類(建物のみ・土地建物が一緒かで違う)を添付して税務署に提出する必要があります。
2年目以降は、住宅借入金等特別控除額の計算明細書、住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書を提出することで済みます。
国税庁 「住宅を新築又は新築住宅を購入した場合(住宅借入金等特別控除)」
おわりに
最初から短い期間で借り入れなくても、繰り上げ返済をその都度行うことで、将来支払う利息の節約ができます。
繰り上げ返済の効果は、残り返済期間が長いほど効果が大きく、また、金利が高いほど効果が大きくなります。
現在は過去最低レベルの低金利なので、住宅ローン利用がしやすい反面、繰り上げ返済の効果も低いといった特徴がみられます。
今のような低金利では、あえて繰り上げ返済をしないという人もいます。