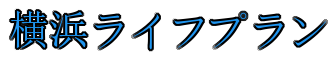今や横浜を代表する観光スポットになった「横浜赤レンガ倉庫」ですが、自分が子供の頃はオープンしてませんでした。
元々は、明治政府によって建設された横浜の保税倉庫でしたが、やがて活躍の場が減少していくと1989年頃には放置されるようになったようです。
その後、横浜市が買い取って修復し、2002年にリニューアルオープンすると、横浜を代表する観光名所へと変貌しました。
横浜赤レンガ倉庫では、定期的にイベントが開催され、建物の中には店舗や展示ギャラリーなどがあり、ショッピングと食事も楽しめます。
みなとみらいや象の鼻パーク、大さん橋や山下公園といった横浜を代表する人気スポットも近いです。少し歩きますが中華街も徒歩で行けます。
自転車で周辺の観光スポットを回るのもおすすめです。
横浜赤レンガ倉庫の歴史
明治になって諸外国との交易が盛んになり、日本にも近代的な港湾の建築が急務となります。
1889年頃から横浜の築港工事が始まると、横浜赤レンガ倉庫も明治の終わりから大正にかけて建築されました。
赤レンガ倉庫の設計は、建築家として当時有名だった妻木頼黄が行いました。
妻木は、官庁営繕建築を手がけ、横浜港では大蔵省臨時建築部長として税関監視部庁舎、新港ふ頭赤レンガ倉庫など数多くの税関関連建築を手がけています。
-

-
横浜港発祥の地「象の鼻パーク」
横浜の開港広場から、大さん橋へと向かう途中に横浜港発祥の地といわれる「象の鼻波止場」があります。 明治の時代に入り、欧州文明を見学するため日本を旅だった岩倉使節団は、この象の鼻波止場から船に乗って出発 ...
1911年に2号倉庫が完成すると、1913年には1号倉庫も完成しました。
しかし、第二次世界大戦後に接収されます。
戦後しばらくして接収が解除されましたが、海上貨物のコンテナ化が進むと次第に取り扱う量が減少し、1989年頃には廃止されるようになりました。
その後横浜市が、放置されてあった赤レンガ倉庫を国から買い取り、2002年4月に商業・文化施設として新しくオープンしました。
2013年には、オープンから通算来場者数が6000万人を突破するなど、赤レンガ倉庫は横浜の名所となりました。

赤レンガ倉庫は、明治末期から大正初期に国の模範倉庫として建設されたレンガ造りの歴史的建造物です。創建当時から横浜港の物流拠点として活躍してきましたが、新港ふ頭が物流機能を他のふ頭に譲っていく中、赤レンガ倉庫も倉庫として利用されなくなり、地区のシンボルとして静かに佇んでいました。
横浜市では、『ハマの赤レンガ』と呼ばれ多くの市民に親しまれてきたこの赤レンガ倉庫を、貴重な歴史的資産として保存し、また市民の身近な賑わい施設として活用するため、平成4年3月に国から取得しました。
取得後、建物補強のための工事を行うとともに、活用の方法について検討を進めてきた結果、「港の賑わいと文化を創造する空間」を事業コンセプトとして、横浜らしい文化を創出し、市民が憩い・賑わう空間として位置付けた赤レンガ倉庫の活用計画がまとまりました。横浜市及び民間事業者(2号倉庫)は、その活用計画に基づき内部改修工事を実施し、2002年(平成14年)4月12日に新たに施設がオープンしました。引用 横浜市ホームページ http://www.city.yokohama.lg.jp/kowan/m-sight/akarenga/
赤レンガ倉庫の建物
赤レンガ倉庫では、定期的にイベントが行われてます。

ちなみに横浜赤レンガ倉庫に入場料はありません。

象の鼻パークから見た赤レンガ倉庫です。

左の建物が2号館で、右の建物が1号館になります。イベントがない日は閑散としてます。イベントがなくても中に入れます。

こちらが赤レンガ倉庫1号館です。

こちらは赤レンガ倉庫2号館です。
赤レンガ倉庫の桜
赤レンガ倉庫の大さん橋側の空き地には桜が植えてあるので、ちょっとした桜の名所になってます。

桜の開花時期になると観光客がたくさん訪れます。

目の前は海に面してるので、行き交う船と桜を眺めながら、芝生にシートを敷いてのんびりと過ごす人もいます。
赤レンガ倉庫の夜景
横浜赤レンガ倉庫は、夜になると建物が美しくライトアップされ、多くのカップルが夜景を見に訪れます。

ライトアップされた2号館です。

広場の奥からは、横浜の港や大さん橋、横浜ベイブリッジを眺めることができます。

1号館と2号館とでは営業時間が異なります。カフェ・レストランの営業時間も店舗によります。
1号館 10:00~19:00、2号館 11:00~20:00

「横浜開港記念館」も近いです。
アクセスデータ
住所
交通 みなとみらい線「日本大通り駅」または「馬車路駅」から徒歩6分、JR根岸線「桜木町駅」または「関内駅」から徒歩15分
駐車場 有料駐車場有り
営業時間 1号館 10:00~19:00、2号館 11:00~20:00
公式サイト https://www.yokohama-akarenga.jp/

横浜赤レンガ倉庫には無料の駐輪場があります。県外ナンバーも多いです。
まとめ
・横浜赤レンガ倉庫は国の保税倉庫だった
・倉庫内にはショップやレストランが入ってる
・倉庫前の広場でよくイベントが行われている
・おすすめのロケーションは海、夜景、桜、ベイブリッジ
・横浜赤レンガ倉庫の周辺には山下公園、大さん橋、中華街といった観光名所がある