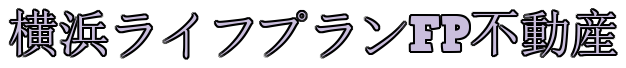不動産取引では多くの金額が動くことから、不動産をめぐるトラブルは多いです。
昔は競売の資料を見に裁判所に行ってたので、暇なときに裁判を傍聴したりもしてましたが、不動産屋はよく訴えられてます。
ちょっとしたことがきっかけで相手の感情を傷つることもありますし、法律を無視して自分の言い分しか認めない人もいるので、不動産のトラブルを完全に排除することは難しいです。
しかし最低限の知識を持って行動したり、注意を心がけることで、無用のトラブルを減らすことはできます。
不動産売買における三大トラブル
賃貸と売買を含めて不動産のトラブルは数多くあります。
・重要事項説明に関するトラブル
・契約の解除に関するトラブル
・瑕疵担保責任に関するトラブル(契約不適合責任)
・分譲マンションに関するトラブル
・賃貸の入居に関するトラブル
・原状回復義務に関するトラブル
・預り金・申込金に関するトラブル
・家賃・更新に関するトラブル
・家賃保証に関するトラブル
中でも不動産の売買は、多額の金銭が動くのでトラブルになりやすいといわれています。
不動産売買において特に多いといわれるトラブルが
・重要事項に関するトラブル
・契約の成立・解除に関するトラブル
・瑕疵担保責任に関するトラブル(契約不適合責任)
です。
重要事項に関するトラブル
不動産の取引では、契約前に「重要事項説明」が行われます。
一般の人は、不動産業者に比べると不動産取引に関する知識が不足してるのが普通です。
そこで宅地建物取引業法では、専門的な知識が不足する買主に対して、事前に重要な事項について調査を行い、調査した内容について重要事項説明書を作成して交付したうえで、宅地建物取引士に説明させることを義務付けています。
法律で重要事項説明書に記載しなければいけないとされている事項
・対象となる宅地または建物に直接関係する事項
・取引条件に関する事項
・一棟の建物またはその敷地に関する権利およびこれらの管理・使用に関する事項(マンション)
契約の前に宅地建物取引士から重要事項の説明がありますが、専門用語や普段聞き慣れ内容も多いため、契約後に言った言わないといったトラブルに発展することは多いです。
トラブルを回避するためには、重要事項説明の署名捺印をする前に宅地建物取引士に質問して不明点を明らかにすることが大事です。
契約の成立・解除に関するトラブル
契約の成立・解除に関するトラブルも多いです。
特に契約の解除に関するトラブルが多く、契約した後に不安になって解除したいと申し出る人はいます。
売買契約では、売主と買主との間に手付金の授受があり、手付金を放棄して契約を解除することができますが、手付金は何百万円にもなったりするので、トラブルに発展することが多いです。
ローン特約が付いている契約では、住宅ローンの承認が受けられない場合に契約を解除することができます。
このローン特約をめぐってトラブルになることも多いです。
民法には、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主は手付を放棄(売主は倍額を渡す)して、契約を解除することができるとされています。
履行の着手とは聞きなれない言葉ですが、「客観的に外部から認識しうるような形で履行行為の一部をなし又は履行の提供をするために欠くことのできない前提行為をした場合をいう(最判昭和40.11.24)。」とされています。つまり、相手側が契約に基づいて行動を起こすことです。
といっても、契約の準備段階は履行の着手にあたらないとされていて、住宅ローンの申し込みは一般的には準備段階と解されています(つまり履行の着手にあたらない)。
ローンが利用できることと、不動産の売買契約とは別なので、ローン特約が適用されるかは確認する必要があります。
また、ローン特約には、解除期日が設けられており、定める解除期日が過ぎた場合は解除することができません。
その場合は、手付金の放棄による解除をすることになります。
瑕疵担保責任に関するトラブル
※民法改正で瑕疵担保責任は契約不適合責任に変わっています。詳しくは次で説明します。
瑕疵とは、キズとか欠陥を表す法律用語です。
瑕疵について売主が知っているのであれば、事前に相手に伝える必要がありますが、必ずしも全てのことを売主が知っているとは限りません。
建物の見えない部分のように、知ることが難しいこともあるからです。
瑕疵担保責任に関するトラブルは、売買契約が成立して引き渡しが終わった後、売主が建物や土地の瑕疵について知らなかった場合に起こるトラブルです。
中古物件の取引などでは、瑕疵担保責任については〇カ月程度を経過したら免責とする、といった特約条項をつけるのが一般的です。
瑕疵担保責任の期間を3カ月にしたのであれば、引き渡し完了後から3カ月までは、売主は隠れた瑕疵について責任を負いますが、3カ月を経過したら責任を負いませんということです。
特約条項の期限内であれば、修理費用などの損害賠償を請求することができます。
また、引き渡しを受けた建物が建て替えが必要な違反建築物であるなど、重大な瑕疵である場合は、契約の目的を達成できないとして解除することもできます。
この瑕疵担保責任をめぐっては、売主と買主の言い分が食い違うことが多く、トラブルに発展することも多いです。
瑕疵担保責任から契約不適合責任へ
2020年4月1日以降の民法改正後は、瑕疵担保責任はなくなり、「契約不適合責任」というものになります。
契約不適合責任では、引き渡しを受けた瑕疵があった場合、契約不適合責任を免責する特約がなければ、、売主の債務不履行責任として契約の解除請求ができます。
ただし、軽微な瑕疵については契約解除できないとされています。
契約不適合責任が施行されれば、売主が瑕疵を知っているか知らないかは関係なく(※)なり、修復や追完、代金減額請求ができることになります。
※瑕疵担保責任制度では、売主が瑕疵について知らなかった場合が要件とされてました。
不動産売買の三大トラブルについてのまとめ
不動産の売買取引で特に多いトラブル
①重要事項説明に関するトラブル
②契約の成立・解除に関するトラブル
③瑕疵担保責任に関するトラブル(契約不適合責任)
①については不明な点は署名捺印の前に明らかにする。
②については解除できるケースを知っておき、ローン特約の解除期日に気を付ける。
③についてはどのような制度なのかを知り、付帯設備表で確認する。
トラブルを完全になくすことはできませんが、ちょっとの心がけで回避できるトラブルもあります。