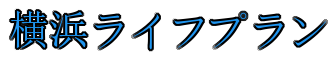2017年からiDeCo、2018年からNISAが始まったことで、投資に興味を持つ人が増えました。
ところが、投資に興味を持って実際に行動に移そうと思っても、始めようとすると分からないことだらけで止めてしまう人も多いです。
確かによく分からないものに何十万、何百円も使うのは当然だと思います。
ただ、投資をしている人としていない人で大きな差がつくのは昔からです。
分からないのであれば勉強すればいいだけです。勉強すれば不安も少なくなります。
読書と実践をすることで、将来大きく変わる可能性を秘めているのが投資です。
ここでは今から投資を始める、始めた人におすすめの本を紹介します。
投資初心者はイラストが多く分かりやすい本がおすすめ
今回紹介する本は、実際に有名な本のうち、自分でも読んだ本の中から役立つと思ったものを挙げています。
投資をこれから始める人には、まず最初はイラストが多い簡単な本がおすすめです。そういった初心者向けの本は必ずといっていいほど投資信託を勧めてます。
有名な本の中には、初心者向けといわれる本でも実際に読んでみると専門用語が多いものがあります。
その時は理解できなかったとしても、投資を続けていると次第に読めるようになってきます。
経験しながら読書をしていると身をもって体感できるので、知識の習得も早いです。
初心者向けの本の多くはデイトレードよりも積立投資を推奨していますが、積立投資なら初心者でも始めやすいからです。
投資を始めたばかりの時は、リスクばかりに目が行きますが、それも最初だけで次第にリスクよりもコストに関心が向くようになります。
リスクとリターンは比例するので、リスクがないのはリターンもないことと同じです。リスクとうまく付き合うことが必要です。
リーマンショックの時は株価が大きく下落して半分くらいに減りましたが、そのまま保有してたら気付いたら株価更新してました。保有していた個別銘柄も倒産せずに済みました。
損が出てるからといって途中で止めず、継続することが大事です。せっかく投資に興味を持ったのに途中で止めてしまうのはもったいないと思えるからです。
投資の初心者におすすめの本
投資初心者が最初に勝ってはいけない本が、専門的な内容の本です。
専門的な本を最初に読んでしまうと、専門用語が難しくて挫折します。
最初に手にするのであれば、「なぜ投資をするのか?」といったことから説明しているものや、本のタイトルに「初心者」「入門」と書いてあるものがいいです。
この本は、どうして投資をするのか、必要なのかということが分かりやすく書いてあります。
何といっても「世界一やさしい」という株の入門書です。
株式、FX、預金、投資信託、不動産投資といった資産運用全般について触れてます。
投資初心者には難しいけどおすすめの本
ここで紹介するのは、投資を始めたばかりの人には難しいですが、いずれは読むことをおすすめする本です。
投資の予備知識がない人が読んだら、難しく感じるかもしれませんが、投資を続けていればいずれ読めるようになります。
投資本のベストセラー「ウォール街のランダム・ウォーカー」
バートンマルキールがの著作「ウォール街のランダム・ウォーカー」は、投資の本では、もっとも有名な本の一つです。
主にインデックス投資のことを中心に学べます。
管理人は、この本を読んだことで殖やすよりも減らさないという考えを学びました。
最もおすすめしたい本の一つです。
敗者のゲーム
チャールズエリス著作の「敗者のゲーム」もインデックス投資を推奨しています。
この本では、市場平均利回りを上回るのはとても難しい事実を上げて、インデックス運用をうまく活用することを説いてます。
いかに市場平均を上回ることが難しいかを過去のアクティブファンドの成績を取り上げて説明しています。
管理人は、この本を読んでからは、維持コストの高いアクティブ投信を止めて、インデックス投信やETFを活用するようになりました。
アクティブ投信の中にも、優秀な成績の商品もありますが、なかなか成果を出すのは大変のようです。
古典的な投資の名著と言われる本
ここで紹介する本は、投資の本では名著として何回も増刷されており、世間的にも知られるている投資の本です。
ただし、財務諸表論の知識が必要であったり、投資の基本的な知識がないと難しく感じると思います。
個別銘柄の選び方が中心ですので、中級者からがおすすめです。
賢明なる投資家 - 割安株の見つけ方とバリュー投資を成功させる方法
作者のベンジャミン・グレアムは、ウォーレン・バフェットの師匠としても有名な人物ですが、本自体もかなり有名です。
バリュー投資というのは、企業の価値に比べて割安な株式に投資する方法のことですが、バリュー投資の古典にあたるのがこの本です。
この著者には、他にも証券分析と財務諸表に関する本がありますが、どちらも専門的すぎて初心者向けではありません。
証券分析と財務諸表と比べれば、この本が一番読みやすいのですが、データが古かったりするので優先順位はそこまで高くありません。
バフェットからの手紙
ウォーレン・バフェットは、伝説的な投資家として世界的に有名な人物です。
バフェットは、世界的な経済危機が起きるとテレビに出演することがあります。
ウォーレン・バフェット自体は、自分で本を出してませんが、この本を読むことでバフェットの投資に対するスタンスが垣間見えて面白いです。
バフェットはグレアムが教鞭をとっていたビジネススクールで投資を学んでいたことから、グレアムの影響を受けた投資スタイルであることが分かります。
この本を読むとバフェットの投資スタイルが、集中投資と長期保有を基本としていることが分かります。
年金だけで老後生活大丈夫?老後資金はリスクと上手に付き合って殖やす
年金だけでは老後生活が大変なのはニュース等で取り上げられているので、ご存知の方が多いと思います。
現在の年金受給世帯の平均の年金額は、月額換算で22万円程度といわれています。
それに対して、毎月の支出の平均額が26~27万円なので、毎月4万~5万円の赤字になる計算です。
さらに、ゆとりある生活のためには毎月35万円程度かかるそうです。いずれにしても年金とは別に自分で老後資金を作る必要があります。
また、今の現役世代は増税、社会保険料増額の影響で、早く手を打たなければ悲惨な老後が待っています。
2017年からiDeCoが始まり、2018年からは積み立てNISAが始まったことで、本屋さんに行くと投資関連の本ばかり置いてあります。
-

-
老後に向けてiDeCo(イデコ)を今すぐにでも始めたほうがいい理由
社会保険制度だけだと老後の生活費が不足してしまうということが知られるようになりました。 また、銀行に預けているだけではいつまで経っても増えないので、投資に興味を持つ人が増えています。 加えて法律の改正 ...
実際に投資を始めて経験してみないと分からないことは多く、リスクについて勉強してから投資を初めても実際に損が出れば普通は慌てます。中には止めてしまう人もいるでしょう。
投資というのは、本に書いてあることを知るだけでは不十分で、経験してみないと分からないことも多いです。
預貯金や生命保険といった元本確定型の資産だと、リスクがあまりありませんが、リスクがないということはリターンもありません。
リスクとリターンは、表裏一体が原則です。
リスクを取れば、資産がマイナスになることは当然あります。
しかし、やり方次第でリスクを軽減させることは可能です。
投資には、株式、投資信託、不動産投資などがありますが、どの資産に投資するにしても、リスクと上手に付き合いつつ資産を殖やすという考えが人生100年時代では必要になってきます。
終わりに
今回紹介した書籍は、投資に関する本ではどれも有名な本です。
投資を始めたばかりの人は、リスクを回避する傾向にありますので、「インデックス投資」に関する本を中心に紹介してみました。
私は忙しい時は積立投資を中心にしてます。積立投資ならほとんど株価を気にせず、下がったらむしろ買い増すだけなので楽です。
NISAでも個別銘柄が買えますが、損益通算を考えると積立投資向きなのかなと思います。