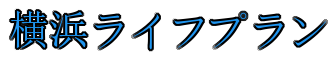北鎌倉にある「東慶寺」といえば、ミシュランガイド三ツ星(わざわざ旅行する価値がある)を獲得した寺院として知られています。
ちなみに鎌倉で三ツ星を獲得したのは、この東慶寺と報国寺のみです。
東慶寺は、女性からは離婚できなかった封建時代に、約600年にわたって女性の駆け込み寺として存在しました。
後醍醐天皇の皇女が護良親王の菩提を弔うために寺に入ったり、豊臣秀頼の娘が20世天秀尼となる等、歴史的にすごい人も入ってます。
境内には、多くの文化人のお墓があることでも知られています。
東慶寺の歴史
東慶寺は、弘安8年(1285)に鎌倉幕府第8代執権北条時宗夫人の覚山志道尼を開山に、北条貞時を開基にして創建されました。
山号を松岡山、寺号を東慶総持禅寺とする臨済宗円覚寺派の寺院です。
鎌倉時代の執権北条時宗の夫人による開山以来、約600年間にわたって縁切寺法を守ってきたそうです。
東慶寺は、女性から離婚できなかった時代に、駆け込めば離縁できる数少ない女性救済の寺として存在しました。
後醍醐天皇の皇女が寺に入り、5世用堂尼(ようどうに)となったことで、東慶寺は松岡御所と称され、寺格の高い尼寺として知られるようになりました。
江戸時代には、豊臣秀吉の孫にあたる天秀尼が20世になり、徳川幕府公認の縁切寺となりました。
ただ、実際は女性から離縁を突きつけることはあったそうです。
明治38年(1905)に元円覚寺派管長の釈宗演が住職となり、荒廃していた東慶寺を再興しました。
宗演の門下には、世界に禅を広めた鈴木大拙がいます。
鈴木大拙は、宗演の遺言に基づき、昭和20年に境内に松ヶ岡文庫を設立すると、禅文化研究の拠点となりました。
室町時代には鎌倉尼五山(東慶寺以外は残ってない)第二位に列せられいます。
東慶寺は梅の名所として知られてますが、その他にもハナショウブ、アジサイ、しだれ桜、夕顔、紅葉といった花が植えられてます。
一年を通して四季の花が楽しめます。
会津騒動
賤ヶ岳の七本槍の一人として勇名を馳せた加藤嘉明が、寛永8年(1631)に病没すると長男の明成が跡を継ぎます。
跡を継いだ明成は、年貢の取り立てを厳しくし、領地の商人から法外な利益を得るなど、領民を虐げたといいます。
筆頭家老の堀主水は明成の行動を諫めましたが、明成は苦言ばかりの主水を疎んじるようになり、次第に二人の仲は険悪になっていきます。
或る日、明成の家臣と主水の家臣が喧嘩をする事件が起こります。
実際は明成の家臣に非がありましたが、事件を聞いた明成は一方的に主水の家臣に非があるとし、主水に対しても蟄居を命じました。
主水が明成の処置に文句をいうと、これに怒った明成は主水の職を罷免します。
呆れた主水は、妻子を東慶寺に預けて、明成のいる城に鉄砲を放って関所を押し破り、自身は高野山へと出奔しました。
高野山は明成の身柄引き渡しを断りましたが、高野山を戦場にするわけにはいかないと主水は山を出ます。
幕府重役による評議の結果、家臣でありながら主君の住む城に鉄砲を放ち、関所を押し破ったことは問題だということになります。
これにより主水の身柄は明成に引き渡され、主水の弟と共に処刑されてしまいました。
主水兄弟の処刑の後、明成は主水の妻子が匿われていた東慶寺に家臣を使わし、妻子を捕らえて処刑してしまいました。
このことを天秀尼が怒り、義母の千姫を通して幕府に訴えた結果、会津藩は取り潰しとなりました。
花の名所
東慶寺の境内は、1年を通して花が咲いてます。訪れたときは山門前に梅が咲いてました。

東慶寺の隣に喫茶店もありました。

境内に入ると路の両側に梅の木が植えてあります。

門に入って左には鐘楼があります。

ミシュランガイド三ツ星だけあって外国人観光客も多いです。

東慶寺の本堂です。

菖蒲畑です。菖蒲の見頃は6月初旬~中旬頃です。

「白蓮舎」

「寒雲亭」

「東慶寺書院」

「さざれ石」
境内の奥には、後醍醐天皇皇女・用堂尼や豊臣秀頼息女・天秀尼の墓があります。

階段を上った先に用堂女王と天秀尼のお墓があります。
他にも、和辻哲郎、鈴木大拙、西田幾多郎、岩波茂雄といった文化人のお墓があります。
主な文化財
境内の松岡宝蔵には、重要文化財の聖観音菩薩立像、東慶寺文書、初音蒔絵火取母、葡萄蒔絵螺鈿聖餅箱をはじめ、多くの文化財を収蔵、展示してあります。

松岡宝蔵の拝観は、9:00~15:30。月曜休館。
拝観料は展示内容によって異なるようです。
本堂の奥の水月堂には、水月観音菩薩半跏像が祀られてます。

水月堂の拝観は、1日2回の9:30 ~(毎月第1日曜日のみ10:00〜)と14:30 ~です。
拝観料は300円です。
松岡山東慶寺のアクセス
所在地 神奈川県鎌倉市山ノ内1367
アクセス JR北鎌倉駅から徒歩で4分
電話 0467-22-1663
拝観時間 8:30〜16:30(10月〜3月は16:00まで)

東慶寺の前は車が渋滞します。自分はいつも自転車かバイクですが、道が狭いので四苦八苦です。
まとめ
・東慶寺は鎌倉時代の執権北条時宗の夫人によって創始された
・後醍醐天皇の皇女、豊臣秀吉の孫が入る由緒ある寺院
・日本に数少ない縁切寺
・江戸時代に日本で二つしかなかった女性の駆け込み寺。もう一つは上野(群馬)の満徳寺。
・梅、桜、菖蒲、アジサイなど花の寺として知られている
・有名人の墓も多い
参考
井上禅定「東慶寺と駆込女」有隣新書