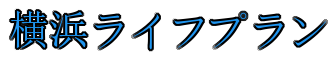横須賀は、2013年に転出数が全国1位を記録するなど、人口減少が問題となっています。
しかし、都心から1時間で行けるということもあって、気軽に行ける観光スポットとして人気のエリアです。
横須賀は、中世は三浦氏の拠点として、江戸時代は浦賀奉行が置かれて栄えました。
明治には横須賀は海軍の軍都として発展し、現在も横須賀には自衛隊関連の施設が多く置かれています。
横須賀市は、東と西に海岸線があるように、海に関する歴史が多数残ってる風光明媚なエリアです。
今回は、「横須賀集客促進実行委員会」が発行しているパンフレットを手に、横須賀市の東側の馬堀海岸沿いを散策してみました。
馬堀海岸から観音崎へ
京浜急行線の「馬堀海岸駅」で下車して、海沿いの道を通って観音崎まで行きます。
途中で寄ったのは、「馬堀海岸よこすか海岸通り(うみかぜの路)」「旧水道トンネル」「馬頭観音」「走水水源地」「破崎緑地」「御所ヶ崎」「走水神社」「横須賀美術館」「県立観音崎公園」です。

今回の散策ルートは、上の画像の赤い線のルートです。
馬堀海岸駅
馬堀海岸駅は、横須賀市にある京浜急行線の駅の一つで、夏は海水浴客でにぎわいます。
メイン通りから1本入った場所に駅があるので、駅の階段を降りたときは寂れた印象を受けましたが、近くにはスーパーやドラッグストアもあります。
飲食店も結構ありますし、車で平成町まで行けば買い物に困ることはほとんどなさそうです。

馬堀海岸駅は、メイン通りから1本入ってるので最初は寂しい印象を受けました。
馬堀海岸よこすか海岸通り
馬堀海岸駅を出て北に進むと東京湾が見えてきます。

海岸沿いには、東京湾を一望できる遊歩道があり、天気が良ければそこから横浜ベイブリッジや房総半島の建物を望むことができます。
パンフレットによれば、「遊歩道に埋めてある大きな石は、住宅地を水害から守るために、国内初の面的防護による高潮対策の護岸となっているから」とあります。
2006年10月に「水辺のユニバーサルデザイン大賞」を受賞しています。
道路沿いにヤシの木が植えてあって雰囲気もよいです。

馬堀海岸は、横須賀よりも房総半島の富津のほうが近いため、房総の建物がよく見えます。

写真だと拡大しないと分かりませんが、天気が良い日はランドマークタワーも見えます。
海を見ながら遊歩道を進んで行けます。

この道路沿いはロードバイクやクロスバイクといった自転車がたくさん走ってます。中には東京から来る人もいます。
旧水道トンネル
旧水道トンネルは、造船所の用水を確保するための水道管を通すために作られたトンネルです。

二つのトンネルが続いてるので、歩いてみるとけっこう長いです。
旧水道トンネルは明治9年に建築され、明治16年に拡張された歴史あるトンネルです。

旧水道トンネルは、横須賀・横浜では有名なフランス人技師ヴェルニーによって作られました。
馬頭観音
馬堀小学校の前の浄林寺の坂の上には、馬堀の名前の由来になったといわれている「馬頭観音堂」があります。
案内板によると、上総(現在の千葉県)から浦賀水道を泳いで渡った荒馬が、蹄で土手を掘ったところ、清水が湧き出したため、そこを「蹄の井」と呼ぶこととし、この地は馬堀と呼ばれるようになったようです。
「平安末期、上総国(千葉)の暴れ馬が村民に追われ浦賀水道を泳ぎ渡り、小原台に着いたという伝承があります。のどが渇いた荒馬は蹄で地を掘ると清水が湧き出し、のどを潤すと駿馬に変わりました。そこを「蹄の井」と呼び、「馬堀」の地名の由来となりました。
馬は美女鹿毛とと呼ばれ、衣笠城主・三浦義澄から源頼朝に献上され生唼と名付けられたといいます。
後に宇治川の合戦で、佐々木信綱は生唼を拝領し梶原景季の磨墨と先陣争いをしたといわれます。
堂には馬の蹄鉄や手綱が奉納され、競馬の騎手が必勝祈願に訪れています。
浄林寺の本堂には馬頭観音が祀られています。」

ここが入口で、奥の階段を上った先に馬頭観音堂があります。

馬頭観世音菩薩縁起
「当山一帯の地は古来より観世音菩薩のご出現になられる霊地であると言い伝えられて参りました。
その昔房州嶺岡に「今の千葉県江見町のあたり」に凶暴な馬が現れ住みつき村人はこの馬を「荒潮」と名付け恐れて近寄りませんでした。
しかしこの馬がしだいに畑の作物を荒らすので村人が追い払うことを決めました。
馬は村人から逃げ海中に飛び込み当時の相模の国、小原台の地にたどり着きました。
馬は疲れと渇きを癒すため傍らの岩を足で掘った処、清水が湧きだしその水で渇きをいやし見事な駿馬に生まれ変わりました。
この噂を聞いた時の領主三浦荒次郎義澄はこの馬を捕獲し時の将軍源頼朝公に献上したところ大変お慶びになられ、「池月」と命名されました。
寿永二年、宇治川の合戦に際し頼朝公はこの池月を佐々木四郎高綱に与えられ「平家物語」に語られるように梶原景孝の愛馬「磨墨」と先陣の争いとなりこの世に名声を残すことになりました。
当初の馬堀という地名はこれより起こり、馬の掘った井戸は霊水が今も尚尽きることがありません。」

蹄の井の跡の碑です。
走水水源地
走水水源地は、横須賀水道の始まりの水源地として知られており、桜の開花時期には一般公開されます。

この走水水源地は国の有形文化財にも指定されています。

走水の湧水は、ミネラルを豊富に含み美味しいことでも有名です。また、通り沿いは桜の名所としても知られています。
破崎緑地
うみかぜの路を観音崎方面に進んで行き、坂を上った場所にあるのが「破崎緑地」の展望台です。

展望台にはベンチ置かれてあるので休憩できます。

展望台から馬堀海岸や横須賀の港を見ることができます。天気が良いと富士山が見えることもあります。
御所ヶ崎
破崎緑地から坂を少し下ると、左に「御所ヶ崎」と呼ばれる場所があります。
御所ヶ崎は、日本武尊が上総に渡った場所という伝説が残ります。
上総に渡る際に、仮の御所を設け、軍旗を立てたことから御所ヶ崎、旗山崎と呼ばれるようになったそうです。

「横須賀風物百選 御所ヶ崎」

公園の名前は「旗山崎公園」といいます。

武田家に仕えた向井氏は有名ですね。走水奉行になった向井忠勝は有名な正綱の子のようです。

この岬から日本武尊が旅立ったのでしょうか。

公園の左手に見えるのは走水小学校です。海に隣接してる学校なんて何ともうらやましいですが、2025年に廃校になるようです。
走水神社
走水神社の歴史は古く、日本武尊の伝説が残ってます。
走水神社は、横須賀随一のパワースポットといわれており、恋愛運や夫婦関係にも効果があるようです。

横須賀風物百選
「走水の地名は、すでに古事記(712年)や日本書紀(720年)の中に表れています。大和朝廷の時代には、上総(千葉県)を経て東北地方に渡る最も便利な道として、この地方に古東海道が通じておりました。
走水の祭神は、日本武尊とその后、弟橘媛命の二柱です。神社の創建された年代については、享保年間の火災で、神社の記録や社宝が焼失してしまったので、わかりません。伝説では、景行天皇の即位40年(110)東夷征討の命を受けた日本武尊が、この走水から上総へ渡られるにあたり、村民に「冠」を賜りましたので、冠を石櫃(いしびつ)に納めて、その上に社殿を建て、尊を敬ったことに始まると伝えています。日本武尊が渡海の際、海上が荒れて、いまにも舟が沈みそうになりました。海神の怒りであると考えた弟橘媛命は、
さねさし さがむのをねに もゆるひの ほなかにたちて とひしきみはも
の歌を残し、尊に代ってうみに身を投じ、風海を鎮めました。
弟橘媛命は、もと旗山崎に橘神社として祭られていましたが、その地が軍用地に買収されたため、明治42年、この神社に祭られました。
明治43年6月、弟橘媛命の歌碑が、東郷平八郎、乃木希典など7名士により、社殿の裏手に建てられました。
社殿の階段下の右側にある「舵の碑」は、弟橘媛命の崇高な行いにあやかり、船海の安全を願って国際婦人年(昭和五十年)を機に、また、左側にある「包丁塚」は、走水の住人・大伴黒主が、日本武尊に料理を献じて喜ばれたとの古事により、包丁への感謝と鳥獣魚介類の霊を慰めるため、昭和48年に建てられたものです。」

庖丁塚は、庖丁で調理された鳥や魚を慰めるためのものです。庖丁塚は全国にあります。

ご神木です。

階段を上った先に拝殿があります。

階段を上って振り返ると、走水の海が見えます。なかなか良い景色です。アニメやドラマに出てきそうな画です。

「別宮」
日本武尊が上総に渡る際、海が荒れて船が沈みそうになったため、弟橘媛命が海の怒りを鎮めるために海に身を投げました。すると、海は静まって日本武尊は上総に上陸できたといいます。弟橘媛命が海に身を投げる際に一緒に身を投げた侍女を祀ってあるのが別宮です。

さらに奥へと続く階段があったので行ってみました。

「古代稲荷社」110年10月、日本武尊一行が上総に渡る際に蝦夷征討を祈願した場所と伝わっています。

奥まで行くと「須賀神社」「神明社」「諏訪神社」の三社があります。
横須賀美術館
走水神社を出て再び観音崎方面に進むと、通り沿いに「横須賀美術館」があります。

横須賀美術館では、横須賀と縁のある作家の作品を多く展示しています。
屋上からは、東京湾を行き交う船や房総半島を眺めることもできます。

「横須賀風物百選 観音崎公園」の碑は美術館の前に立ってます。
県立観音崎公園
横須賀から観音崎までの海辺の道は「うみかぜの路」と呼ばれています。
終点の観音崎には、「県立観音崎公園」があります。
県立観音崎公園は「かながわの景勝50選」にも選ばれており、バーベキューもできます。
公園内には、日本最初の洋式灯台があり、明治に作られた洋式砲台の跡も残ってます。
-

-
観音崎灯台から見える東京湾の眺望が素晴らしい!
横須賀の観音崎は、横浜から車で40分で行けるお気軽な観光名所です。 横浜横須賀道路の「馬堀海岸」出口から車で5分とアクセスしやすく、三浦半島をツーリングしてるたくさんの人が立ち寄ります。 実際に歩いて ...

観音崎の海です。

海の向こうに見えてるのは房総半島です。

観音崎灯台は登ることができる珍しい灯台です。
さいごに
馬堀海岸駅から観音崎までは、約7キロなので1日もかからずまわることができます。
馬堀海岸にある横須賀温泉「湯楽の里」に入ってから帰りました。