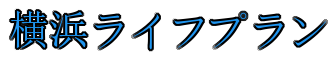日経平均株価も19,000円を超え、株式市場の景気が戻りつつあります。
景気が回復しつつある中で、証券会社や銀行がCMを使って営業する等、ラップ口座の販売を頑張っているようです。
おかげでラップ口座の売上がうなぎのぼりのようで、今日の日経新聞には残高が6兆円を超えたと書いてありました。
最近とても人気のラップ口座ですが、デメリットはないのでしょうか?
ラップ口座はデメリットも多い
ラップ口座では、証券会社や銀行に運用額の〇%の年間手数料を支払うことで、その人に代わって商品を選択してくれます。
ラップ口座は、投資の知識がない人でも投資を始められ、また分散投資の効果も期待できます。
ここ2,3年で急激にラップ口座が増えたわけですが、人気のラップ口座にはいくつかの問題があります。
まず、第一にラップ口座はコストが高いということです。
ラップ口座では、1%~2%かかる信託報酬に加えて年間の手数料が2%程度かかるのが平均なので、ラップ口座を利用するだけで年間計3%~4%のコストがかかることになります。
このコストを上回る利益を出すことができなければ、目減りしていくことになります。
たとえ5%の利益を出したとしても、3%~4%の費用がかかることから、手元には2%~1%しか残りません。
投資の専門家が口をそろえてラップ口座はやめた方がいいというのは、この手数料が高いことが原因です。
分散投資は、リスクを抑えられる反面、リターンも抑えるので、年間コストが高いのは致命的です。
自分で商品の選択をしなくてよいからといって、値下がりした時の損失を負ってくれるわけではありません。
投資を一任したからといってリスクを負わないわけではないのです。
証券会社や銀行がラップ口座の販売に力を入れてるのは、何も投資家のためを思ってやってるわけではありません。
ラップ口座は、投資家のための商品というよりも、証券会社や銀行が儲けるための商品といえます。
インデックス投資やETF
コストが高いと利益が失われてしまうので、年間コストを抑えることは重要です。
投資信託は、複数の商品を組み合わせるのでリスクを抑えることができますが、やはりコストがかかります。
投資信託の運用には、目安となる指標を上回る成績を目指すアクティブ運用と、目安となる指標に連動するパッシブ運用とがあります。
アクティブ運用とパッシブ運用とでは、アクティブ運用の方が手数料が高く、パッシブ運用が手数料が安いのが一般的です。
パッシブ運用の代表的なのが、インデックス投信やETFです。ETFは上場しているインデックス投信のことをいいます。
インデックス投信やETFは、目安となる指標に連動するので、指標が上昇すれば商品も値上がりするという分かりやすさがあります。
長期の運用になるほどコストが及ぼす影響は大きくなりますが、インデックス投信やETFはラップ口座と比べてコストを安く抑えることができます。
ネット証券ならさらに手数料を抑えることも可能です。
「ウォール街のランダムウォーカー」と「敗者のゲーム」という投資初心者におすすめの本があります。
この本の著者はパッシブ運用を支持しており、この本にはアクティブ運用がどうしてパッシブ運用に及ばないのかが書いてあります。
年金不安には確定拠出年金がおすすめ
老後の資金が不足するのが分かっている場合は、掛金は60歳以上にならないと受け取れない制約がありますが、「確定拠出年金」の利用がおすすめです。
確定拠出年金は、将来の年金を自己責任により、自分で運用して作る制度です。
自分で運用するので、受け取れる年金は運用結果によって左右されることになります。
確定拠出年金は、3つの税制上の優遇があります。
その3つとは、掛け金を拠出したとき(所得控除)、運用時の運用益に対しての(課税の繰り延べ)、受取時に公的年金と同じ扱い(雑所得)、といったタイミングでそれぞれ税金の優遇があります。
掛け金を拠出したときは、掛け金が所得税の計算から控除されるので、適用される税率が大きい(所得が多い)ほど、また掛け金が大きいほどより効果が期待できます。
ただし、将来の年金給付を作る目的なので、確定拠出年金に加入するには年齢制限があります。
確定拠出年金について、雑誌や専門家がたびたび取り上げるのは、それだけメリットがあるからです。
現在の平均寿命と貨幣価値では、老後に必要なお金は2,000万円~3,000万円以上といわれています。
現役の人なら確定拠出年金を利用するメリットはあるのではないでしょうか。
おわりに
ラップ口座はプロに投資を任せることができますが、手数料が高いです。
また、リスクや損失を負ってくれるわけではないので、利用する際はメリットとデメリットを検討することが大切です。