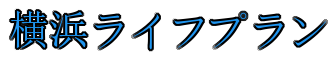不動産の購入では、物件ばかりに目が向きがちですが、物件選びと同じくらい重要なのが住宅ローンに関することです。
不動産購入後の相談を今まで受けてきましたが、住宅ローンに関して誤解したまま利用している人は多いです。
低金利だと見直しをする必要はないと思ってる人は多いですが、住宅ローンは金額が大きいので、見直しすることで総額費用を何十万円軽減させることが可能です。
住宅ローンの節約方法には、繰り上げ返済、借り換えがありますが、借り換えについては別の機会にするとして、ここでは繰り上げ返済について触れてみたいと思います。
繰り上げ返済の特徴
現在は史上空前の低金利といわれていますが、住宅ローンは借金ですので借り入れている間は低金利とはいえ利息が発生します。
住宅ローンは長期間返済していくものなので、利息の負担は低金利でもそこそこの金額になります。
利息については、余剰資金があるときに繰り上げて返済すれば将来の利息を抑えることができます。
住宅ローンの見直しには、繰り上げ返済や借り換え、条件変更といったものがありますが、最も簡単にできるローンの見直しが繰り上げ返済です。
繰り上げて返済することで、本当ならかかるはずだった繰り上げ分の利息をカットすることができます。
今100万円繰り上げ返済を行えば、その100万円にかかる将来の利息を支払わなくて済みます。
繰り上げ返済の特徴として、早く行えば行うほど利息の節約額が大きくなります。
ローンの返済期間が残り10年よりも30年ある人の方が繰り上げ返済の効果は大きくなります。
10年分の利息と30年分の利息を単純に比較すれば、30年分の利息の方が大きいのは当然です。
昔は、繰り上げ返済に手数料がかかる金融機関が多かったのですが、現在は手数料がかからない金融機関も増えました。
また、以前は繰り上げ返済を行うには100万円単位からが一般的でしたが、インターネットであれば少額から行える金融機関も増えています。
2つの繰り上げ返済
繰り上げ返済には、「期間短縮型」と「返済額軽減型」の2種類のタイプがあります。
「期間短縮型」による繰り上げ返済では、毎月の返済額はこれまで通り同じですが、返済期間を短縮させることができます。
「返済額軽減型」による繰り上げ返済では、返済期間は変わらずに、毎月の返済額を減少させることができます。
期間短縮型と返済額軽減型を利息の軽減効果で見てみると、期間短縮型の方が利息軽減効果は大きくなります。
家計が安定して無理がないのであれば期間短縮型を使い、家計が厳しいようであれば返済額軽減型を利用するといった使い分けもできます。
| 繰り上げ返済のタイプ | 期間短縮型 | 返済額軽減型 |
| 返済期間 | 減少 | 変わらない |
| 毎月の返済額 | 変わらない | 減少 |
| 利息の軽減効果 | 大きい | 少ない |
定年後に住宅ローンの返済に追われるのが嫌という理由で、借入期間を定年までにする人は多いです。
例えば、40歳の人が60歳の定年までに返済をしたいと考えてローンの返済期間を20年に設定するといった場合です。
金利が1.5%で3000万円を借入れた仮定した場合、返済期間が35年だと9.2万円ですが、返済期間が20年だと月々14.5万円になります。
返済期間を短く設定したとしても20年の間には様々なことが起こる可能性があります。
返済期間を短くするよりも、返済期間を長くしておいて適時繰り上げ返済をしていく方が返済に無理がありません。
繰り上げ返済の手数料が無料であれば、借り入れを長くした方がメリットが多いケースもあります。
期間短縮型の返済期間が短くなる特徴を利用すれば、返済期間を縮めることができます。
利息がもったいないからと最初から厳しい返済計画を立てるより、長期間の返済計画をたてて余裕が出たら繰り上げ返済をするということをした方が無理のない資金計画といえます。
借入時と現在の金利に差がある場合は、繰り上げ返済よりも借り換えの方が効果が高いケースもあります。
最近は繰り上げ返済の手数料が無料になる金融機関が増えているので、その辺も考慮したうえで総合的に検討するのがいいと思います。
おわりに
住宅ローンの実際の借入期間は20年そこそこと言われており、これはローンを35年組んでも実際は繰り上げ返済や借り換えをする人が多いからです。
団体信用生命保険があるから住宅ローンの繰り上げ返済はしないという人も多いです。
重要なのは、住宅ローンの返済は長期になるので無理のない計画を立てることです。