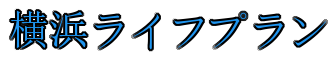横須賀に用事があったので、早めに出て横須賀市北部にある追浜周辺をまわってきました。
追浜は、横浜ベイスターズの2軍本拠地の横須賀スタジアムや日産工場があり、駅前は商業施設が充実するなど生活には便利ですが、隣の横浜市金沢区と比べるとややマイナーな感があります。
横浜の金沢区は、鎌倉時代は鎌倉の外港として栄え、金沢の地も北条氏一門の重鎮が治めたように歴史ある場所です。
しかし、追浜の歴史はというと……あまり聞いたことがありません。
横須賀市追浜
横須賀市にある追浜(おっぱま)は、北は横浜市金沢区、西は逗子市と隣接しています。

追浜駅前は、商店街が賑やかです。ただ、最近はシャッターを閉めている店も目立つようになってきました。
横須賀市は、数年前に人口の流出が全国2位になって話題になりましたが、現在も横須賀市の人口流出は改善されておりません。
横須賀市全体で見ると人口流出が続いていますが、追浜エリアは人口が増加した年もある横須賀では比較的人気のエリアです。
京浜急行線の「追浜」駅からは、都心まで約1時間とアクセスも良好です。
追浜は海に隣接してるので海を身近に感じることができますが、追浜の海側は工場地帯になっていて海水浴には適してません。
しかし、北は金沢八景、西は逗子と隣接しているので、週末に訪れればレジャーやリゾート気分を満喫することができます。
スポンサーリンク
朝倉能登守
浦郷村(追浜)を領地とした武士として知られているのが、後北条氏に仕えた朝倉能登守です。
朝倉氏というと、織田信長に滅ぼされた越前朝倉氏が有名ですが、信長に敗れた朝倉氏の一族は各地に散り、朝倉能登守は北条氏に仕えたそうです。
朝倉能登守は、玉縄十八衆の一人として活躍し、北条家滅亡後は徳川家康の次男結城秀康に仕えました。
結城秀康といえば、関ケ原の戦い後に越前に転封され、越前宰相と呼ばれました。
こうして朝倉能登守は、越前の地に戻り、故郷の地で没したそうです。
雷神社
雷神社(いかづちじんじゃ)は、追浜駅を出て、国道16号沿いに横浜方面に進んで行くと右側にあります。
正式名称は「いかづちじんじゃ」ですが、地元の人からは何故か「かみなりじんじゃ」と呼ばれています。

雷神社前の交差点にある交通標識も、かつてはかみなりじんじゃでしたが、現在はいかずちじんじゃに変わってました。
雷神社の祭神は、火雷命(ほのいかづちのみこと)で、創建は931年とのことです。
天正9年(1581年)に、北条家の家臣として浦郷村の領主であった朝倉能登守が、築島にあった社殿を現在の場所に移して雷神社としました。
横浜市金沢区にあった浜空神社は、現在はここ雷神社に移設されています。
-

-
横浜市金沢区の公園「富岡総合公園」の紹介
横浜市金沢区には、かつて横浜海軍航空隊の基地があった場所に「富岡総合公園」があります。 公園の広さは約22ヘクタールになる大きな公園で、桜や梅、あじさいといった花も見れます。 桜の名所として知られてま ...

雷神社の前がいつもより賑わってると思ったら、ポケモンGOが目的の人たちでした。

雷神社の鳥居

鳥居横にある戦没者の「慰霊碑」

浜空神社は、富岡総合公園の敷地内にありました。浜空神社の社殿です。

階段を上がると雷神社の社殿があります。
良心寺
朝倉能登守の館は、良心寺から追浜駅にあったと伝わっています。
朝倉能登守は、夫人の願いで荒れ果てていた良心寺を整備し、夫人は良心寺にまつられています。

良心寺は、踏切を渡ったらすぐです。


良心寺のお地蔵さんと庚申塔
墓石形態は宝筺印塔で塔身総高約2m余、基礎正面「当寺建立、大旦主大慈院殿法誉良心大姉朝倉能登守奥天正十一年未六月十一日」の刻銘がみられるが、造立年代については塔形式の上から江戸初期建立と考えられる。
朝倉氏は戦国期小田原北条氏の家臣で、玉縄衆に属し、浦郷村追浜を初め、伊豆や上総にも所領を有する武将であり、天正18年(1590年)豊臣秀吉の小田原攻めの折は、箱根の山中城を守った。
朝倉能登守景澄入道犬也がその人であると言われている。
この能登守が夫人の菩提を弔らう為、開基となって夫人の法号を寺号として良心寺を建立したと伝えられている。
追浜駅から国道16号線を横須賀方面に少し進むと踏切がありますが、踏切を渡った先に浦之郷陣屋がありました。
今は住宅地しかなく面影はありませんが、令和になって案内板が設置されました。

「浦之郷村と呼ばれたこの辺りは、戦国大名北条早雲を始祖とする小田原北条氏の家臣朝倉能登守の居館があったところといわれています。能登守は長年にわたり浦之郷村の領主としてこの地を支配し、雷神社の再興、良心寺の再建など随所に足跡を残しています。以下略」
首斬観音
天保年間(1830~43年)の頃のこと、全国的に干ばつが続いてひんぱんに飢饉が発生すると、各地で百姓一揆や打ちこわしが起こったそうです。
浦郷村(追浜)でも干ばつや飢饉が原因で犯罪が横行し、捕らえられた犯罪者は浦郷陣屋で裁かれた後に処刑されたそうです。
大正末期に行われた国道16号線の工事では、頭蓋骨が十数個発見されましたが、その際に供養碑として石塔が建てられたそうです。

首斬観音の碑は、良心寺よりもさらに田浦よりに進んだ住宅地にあります。

真ん中の碑には「首斬観音」の文字が刻まれ、左の碑には「南無阿弥陀仏」、右の碑には「南無妙法蓮華経」と刻まれてました。

首斬観音の碑の裏側
観音寺
追浜にある「観音寺」は、三浦三十三観音第二十二番札所になっています。
途中の道は狭く、坂も急なので、歩いていくのが無難です。

途中の道が狭いため、車は通れません。自転車なら通れますが、自転車でもギリギリ通れる狭さです。
観音寺は、貞享4年(1687)に日本橋の商人鎌倉屋市左衛門によって創建されたと伝わっています。

観音寺は、丘の上にあります。

観音寺は誰もいませんので、御朱印は良心寺で行っているそうです。

境内にある水子地蔵尊、新しく感じました。
おわりに
今回追浜をまわってみて思ったのは、思った以上に寺院が多かったことです。
また、追浜は海軍航空隊の発祥の地といわれ、名前は忘れましたが以前読んだ小説でも山本五十六が訪れていたのを思い出しました。
横須賀に海軍が置かれたこともあって、追浜は特に幕末以後の貴重な歴史ある町でした。

貝山緑地にある予科練誕生の地碑