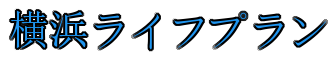みなさんは、「摩崖仏(まがいぶつ)」をご存知ですか?
摩崖仏というのは、自然の岩や岩壁を彫った仏像を指します。
歴史のテキストで、中国の雲崗石窟や敦煌、インドのアジャンター石窟といった摩崖仏を見たことはありませんか?
歴史で勉強するのは外国の摩崖仏ですが、日本にも摩崖仏はあります。
摩崖仏というと、大分県が有名ですが、横浜市にも摩崖仏が存在していたそうです。
調べてみると、横浜市にあった摩崖仏は、金沢区に集中しているとのことなので、休日を利用して訪れてみました。
鼻欠地蔵
最初に訪れたのは、「鼻欠地蔵(はなかけじぞう)」という神奈川県横浜市金沢区大道1丁目にある摩崖仏です。
住所 神奈川県横浜市金沢区大道1丁目
アクセス 京浜急行線「金沢八景」駅からバスに乗車し「大道中学校前」バス停で下車、または京浜急行逗子線「六浦」駅から徒歩18分
前の通りを走る「原宿ー六浦線」を挟んだ反対側が大道2丁目で、鼻欠地蔵の横の道を歩いていくと、高舟台に出ます。
鼻欠地蔵は、「大道中学校前」バス停から見えます。

鼻欠地蔵の案内板
『崖に彫り込まれた像の高さが4m余りのお地蔵様の摩崖仏で、風化して鼻が欠け落ちているため、このように呼ばれました。いつごろ、だれが彫ったかは分かりません。
江戸時代に出版された『江戸名所図絵』には、この地蔵の挿絵があり、やさしそうな顔立ちや膝元で組んだ手などが描かれていますが、今はその輪郭を見ることができます。また、江戸時代の地歴が書かれている『新編鎌倉誌』には、この地蔵について、武蔵国と相模国の境界にあることから「界(さかい)地蔵」と言われたこと、この場所から北へ向かう道は釜利谷や能見堂へ通じたことが書かれています。
また、地蔵の前の道は、六浦道と呼ばれた金沢と鎌倉を結ぶ、中世からの大切な道であることから、この地蔵が交通の要所に祭られ、広く人々の信仰の対象となっていたことがわかります。』

現在の鼻欠地蔵の写真がこちらです。
風化してしまって何があったのかもはや判別できませんでした。

鼻欠地蔵がいつ頃、誰が彫ったかは分かりませんが、鎌倉と六浦を結ぶこの地は、鎌倉時代は既に交通の要衝でした。
六浦湊から鎌倉に塩を運んだことから、鎌倉ー六浦間は塩の道とも呼ばれ、金沢の地は横浜市でもっとも古くから栄えたそうです。
白山道奥摩崖仏
横浜市にあるもう一つの摩崖仏が「白山道奥摩崖仏」です。
住所 神奈川県横浜市金沢区釜利谷南2丁目
白山道奥摩崖仏は、釜利谷の住宅地を抜けたところにあります。
鎌倉と称名寺を結んでいたこの付近の道が白山道(はくさんどう)だったそうです。

歩いていくと、周りにそれらしきものが全くないのにこんな看板が出てきました。

ふと、振り向いた先にあったのが木々の生えた崖でした。

写真の丸で囲んだあたりが中段ですが、何も見えません。
かつてあった摩崖仏は、現在は風化していて崖の一部が出っ張ってるくらいしか分かりません。

白山道奥摩崖仏の案内板
『白山社は白山堂とも呼ばれ、南北朝~室町時代には称名寺の管理下におかれ、その末寺となっていました。
堂社の旧位置は不明ですが、北条氏が鎌倉と金沢の称名寺とを山越えに往復する古道が、このあたりを通っていたことは疑いありません。
この古道は「白山道」と呼ばれ、鎌倉時代後期に瀬戸橋ができる以前は、鎌倉と称名寺の往復に使われていました。
この山腹に刻まれている磨崖仏は、その旧跡を推定するための好資料であり、周囲が削平されていますが、現存顔面長4メートル、中世末期の彫刻です。
また、応仁年間(1468)に鎌倉大塔宮からこの地に移った白山東光禅寺に関するものとすれば、御姿は薬師如来をかたどったのでしょうか。』
横浜市の摩崖仏をめぐってみて

もし、横浜市周辺で摩崖仏を見たいのであれば、横須賀市にある「鷹取山」に行くのがいいと思います。
難点は、ちょっとアクセスが悪いという点です。



小さいかもしれませんが、同じ金沢区にある「朝夷奈切通(あさいなきりどおし、朝比奈切通とも)」沿いにも摩崖仏を見ることができます。
今回のまとめ
・横浜市にある二つの摩崖仏は、二つとも金沢区にある。
・金沢区にある二つの摩崖仏「鼻欠地蔵」「白山道奥摩崖仏」は、現在は風化していて判別できない。
・金沢区の隣にある横須賀の鷹取山に摩崖仏がある。