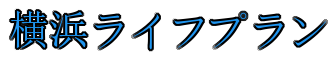金沢区役所に行った際、「横浜金澤七福神」のパンフレットを見つけて興味がわいたので、休日に横浜金澤七福神をまわってきました。
七福神めぐりは、横浜市金沢区にある七福神に関係する寺院を尋ね歩くことです。
横浜市は、幕末になってから発展した街ですが、金沢は鎌倉時代から発展していました。
六浦湊から鎌倉に続く道は「塩の道」と呼ばれ、途中にある「朝夷奈切通(あさいなきりどおし)」は、鎌倉に続く七つの切通しの一つです。
北条家も金沢の地を重要視しており、金沢の地を北条氏一門の金沢北条氏に治めさせることで、有事の際はすぐに鎌倉に兵を送り込むことができました。
源頼朝も北条政子も金沢を訪れていて、特に瀬戸神社の境内にある琵琶島神社は、政子によって創建されました。

横浜金澤七福神の寺院
七福神信仰は、日本各地にあり、七福神めぐりは各地で行われています。
七福神は、いずれの神様も縁起が良い神様なので、七福神をめぐることは庶民によって広まっていったそうです。
七福神の神様には、弁財天、大黒天、毘沙門天、福禄寿、蛭子、布袋、寿老人がいます。
蛭子だけが日本の神様で、ほかの神様はインド・中国の神様といわれています。
弁財天は、七福神で唯一の女神さまで、恋愛運や金運の徳があるといわれています。
大黒天は、商売繁盛や福運アップの神様です。
毘沙門天といえば、戦の神様ですが、勝負運アップのご利益があるそうです。
福禄寿は、財産運や長寿のご利益があります。
蛯子は、日本の神様で商売繁盛にご利益があるとされる神様です。
布袋は、広い度量の神様で、忍耐・富貴のご利益があります。
寿老人は、長寿のご利益が期待できる神様です。
横浜金澤七福神に数えられる寺院は、「瀬戸神社(弁財天)」、「龍華寺(大黒天)」、「傳心寺(毘沙門天)」、「正法院(福禄寿)」、「富岡八幡宮(蛭子)」、「長昌寺(布袋)」、「寶蔵院(寿老人)」の7つです。
七福神めぐりのルート
七福神の寺院は、富岡から金沢八景の範囲にわたっていますが、決まった順番があるわけではなく、北と南のどちらから始めてもよいみたいです。
横浜金澤七福神めぐりのルートは、一つは金沢八景駅から始まって、もう一つは八景島から始まります。
金沢八景駅から始める場合は、
スタート → 瀬戸神社 → 龍華寺 → 傳心寺 → 正法院 → 京急線「金沢文庫駅」 → 京急線「京急富岡駅」 → 富岡八幡宮 → 長昌寺 → 鳥浜 → 海の公園柴口 → 寶蔵院 → 八景島(ゴール)の順です。

瀬戸仁社

龍華寺

傳心寺

正法院

富岡八幡宮

長昌寺

寶蔵院
八景島から始める場合は、
スタート → 寶蔵院 → 海の公園柴口 → 鳥浜 → 長昌寺 → 富岡八幡宮 → 京急富岡駅 → 金沢文庫駅 →正法院 → 傳心寺 → 龍華寺 → 瀬戸神社 → 金沢八景駅(ゴール)の順番です。
横浜金澤七福神をめぐる
私は、パンフレット通りに行かず、北にある「富岡八幡宮(蛭子)」からまわりました。
富岡八幡宮は、建久二年(1191)源頼朝公が鎌倉幕府の守護神として祀った神社です。鎌倉の北東は鬼門にあたるそうですが、弘明寺にも似たようなことが書いてあった気がします。

「富岡八幡宮」の鳥居

富岡八幡宮の境内 イチョウの葉が散ってました。イチョウの葉は、黄色い部分と青い部分が半々でした。

境内にある看板 「絹本著色 八幡神像 一幅」

案内板2 「祇園舟」

富岡八幡宮の次に向かったのが長昌寺なのですが、途中にある「孫文上陸の地」に立ち寄りました。
第二革命に際し、袁世凱に追われて中国を脱出した孫文が上陸した地が、富岡八幡宮から長昌寺に向かう途中にあるこの場所です。

「長昌寺(布袋)」 長昌寺の境内には、直木賞のもとになった直木三十五(なおきさんじゅうご)の墓があるそうです。
次に向かったのが「寶蔵院(寿老人)」です。

寶蔵院は、鎌倉時代の末期に開山したそうです。入口がどこかで迷いました。
寶蔵院から称名寺前の道を抜けて行ったのが「正法院(福禄寿)」です。

境内には、弘法大師が掘ったとされる赤井の井戸があります。
正法院の次は、旧16号を通って「傳心寺(毘沙門天)」に向かいます。

傳心寺は、曹洞宗の寺院です。

大永峯嗣法山傳心寺というのが正式な名前のようです。
本堂には、北条家の家紋である三鱗が刻まれていて、北条一門の北条氏繁の墓があるそうです。
次は、旧16号沿いにある「龍華寺(大黒天)」に行きます。

通るたびに立派な寺院だと思ってました。

龍華寺は、源頼朝が六浦山中に浄願寺を建立したのが始まりとされています。また、泥亀新田で知られる永島家の墓があるそうです。
龍華寺の次は、七福神最後の「瀬戸神社(弁財天)」に向かいます。

瀬戸神社は、1180年に源頼朝が伊豆の三島大社を勧請したのが始まりとされています。

蛇混柏(じゃびゃくしん) 金沢八木の一つ。

瀬戸神社の石柱

「放下僧」の遺跡 六浦港は、今の平潟湾あたりにあって、現在の六浦の地とは少し離れてるんですね。
琵琶島神社
ついでなので瀬戸神社の向かいにある琵琶島神社にも寄ってきました。

島の奥には、北条政子が近江の竹生島から勧請した弁天を祀っているそうです。
金沢八景の一つ「瀬戸の秋月」とはこのあたりから見た景色のことのようです。

琵琶島は、平潟湾に浮かぶ小さな島です。 シーサイドラインの運賃は相変わらず高いです。

島の先から国道16号線方面を見た様子です。 人気ないのか、島には自分の他に中国の人しかいませんでした。

弁天様を祀っていると入口の案内板に書いてありました。

太陽の光が海水に反射してきれいでした。

島の外からの眺めも、なかなか美しいと思いました。

金沢四名石の一つ「福石」 頼朝が着ていた服をかけたことから服石→福石?
金澤七福神めぐって
金澤七福神をめぐって分かったのは、金沢には史跡がたくさんあるということです。
また、富岡八幡宮の近くに「海水浴発祥の碑」があるように、現在のシーサイドライン沿いは埋め立てによってできたということも改めて分かりました。
孫文が上陸した地や、直木三十五の墓、北条氏繁の墓、が金沢区にあったということにも驚きです。
歴史的資産を調べてみると、思わぬ発見があって面白く、ご利益のことは忘れてしまったほどでした。